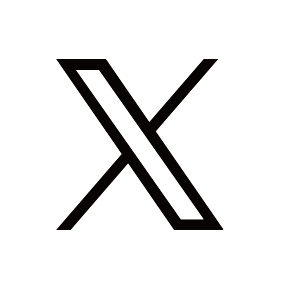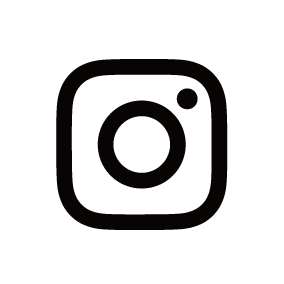カテゴリー: プログラムノート (2ページ目 (2ページ中))
「今年はモーツァルトの生誕250周年!」皆さんもうお馴染みのフレーズでしょう。世界中の演奏会場でモーツァルトの音楽が鳴り響き、日本でも空前のモーツァルト・ブーム。頭が良くなるだとか健康に良いだとか、何やら怪しげな謳い文句とともに、企画CDや関連書籍が大いに売れています。確かに、モーツァルトの音楽には、広く人びとの心に訴えかけて止まない簡明な美しさとでも言うべき魅力が溢れていますし、BGMとして流しっぱなしにしても煩くない一方で、一対一で厳しく対峙して切り込んでいくような聴取態度にも底を割らない懐の深さが備わっています。
結成以来、古典派・ロマン派の二管編成の管弦楽曲を中心的レパートリーに据えて活動してきたブルーメン・フィルにとって、モーツァルト・イヤーの今年、例えばオール・モーツァルト・プログラムで定期演奏会を開催することも容易に考えられたに違いありません。もし実現していたなら、聴衆、団員の双方にとって、それはそれできっと幸せなひと時となったことでしょう。ところが、これまでも一筋縄ではいかないプログラミングを提案・実現してきたブルーメンの選曲委員の面々は、おいそれと時流に乗ることを潔しとしなかったようです。むしろ、演奏の難しさでは定評のあるモーツァルトですから、聴衆、団員の双方にとって幸せであるどころか、不幸を招きかねないとさえ危惧したのかもしれません。……と冗談はともかく、ここに選ばれたのがサリエリであるというところに、得も言われぬ面白みを感じます。
アントニオ・サリエリ。ほとんど「モーツァルトを毒殺した男」としてのみ名前を伝えられてきた不運な音楽家です。ベートーヴェンの筆談帳にその噂が書き記され、プーシキンには劇詩の題材として利用され、それを元にリムスキー=コルサコフにオペラまで作曲され、挙句の果てには映画『アマデウス』の世界的大ヒット。いくら「根拠のないデタラメなんだけどね」と注釈を付けられても、やはりその週刊誌の見出し的インパクトの強力さには敵いません。ようやく近年になって、古楽の復興と足並みを揃えるかのように、サリエリ研究が進み、その音楽も演奏される機会が増えてきたようですが、完全な名誉挽回にはまだまだ時間を要することでしょう。
1750年、J. S. バッハ死の年に北イタリアのレニャーゴに生まれたサリエリは、16歳の時にウィーンの宮廷作曲家だったガスマンに見出され、弟子としてウィーンに移住します。以降、早くも20歳でオペラ作曲家として彼の地で名前を馳せ、24歳で宮廷作曲家、38歳で宮廷楽長の地位に就き、1825年にウィーンで亡くなる前年まで同職を全うしました。当時の音楽家としては最高に恵まれた生涯を送ったといえるわけです。ただし、流行の変化の凄まじい時代にあって、50歳半ばにはほとんど作曲から手を引き、以後は主に教育者として、幾多の音楽家を世に送り出す手助けをしたのでした。
サリエリに師事した生徒たちの名前の豪華なこと。有名どころだけ挙げても、ジュスマイヤー(一時モーツァルトの弟子でもあり、レクイエムの補筆で知られます)、フンメル、チェルニー、マイヤベーア、モシェレス、さらには何とリストまで! サリエリがいかに音楽的に幅の広い時代を生き抜いてきたかが分かります。そして、今夜お聴きいただく他の2人の作曲家、ベートーヴェンとシューベルトも、サリエリの教え子でした。
1770年にボンに生まれたベートーヴェンがウィーンに定住したのは21歳の時。当初ハイドンの教えを受けていましたが、ウィーンで音楽活動を続けているうちにサリエリとの知遇を得て、1795年には、サリエリの指揮する演奏会において、ベートーヴェン自身のピアノでピアノ協奏曲第1番が初演されています。すでにボン時代に作曲の基本的な素養を身に付けており、後年「ハイドンからは何も学ばなかった」と語っているベートーヴェンですが、こと声楽曲の作曲においては自信を欠いており、この点でサリエリは最適な教師だと見えたようです。1800年頃からおよそ3年間にわたって、イタリア歌曲とイタリア・オペラの様式に関して系統的なレッスンが行われ、その習作は、《サリエリのもとでの多声イタリア歌曲練習曲》WoO99として、25曲が現在にまで伝えられています。その後は、気難しいベートーヴェンのことですから、オペラ《フィデリオ》に対するサリエリのアドバイスを無視したり、自身の演奏会の開催日を、サリエリが指揮する音楽家協会慈善演奏会の開催日にぶつけてみたり(その時に初演された作品の1つが、今夜お聴きいただく交響曲第6番です)、ベートーヴェンが一方的に絶交を宣言するに至った時期もあったようですが、サリエリの大人の対応で事なきを得て、後年も交流が続いたと言われています。ベートーヴェンがウィーンで亡くなったのは1827年、サリエリの死後わずか2年のことでした。
一方シューベルトは、1797年に生まれて1828年に31歳で没するまで、生涯をウィーンで過ごしました。シューベルトとサリエリが初めて出会ったのは1808年、ウィーン帝室宮廷礼拝堂少年合唱団の団員補充試験でのこと。試験官がサリエリで、応募者の中の1人がシューベルトだったのでした。合格したシューベルトは、同時に寄宿神学校に入学することになり、やがて合唱団や学校のオーケストラでその音楽的才能を存分に発揮するようになったのです。その才能に驚いたサリエリは、自ら進んで週2日の個人レッスンを施すことを決め、それは1812年から3年間続いたのでした。ベートーヴェンと同様に、イタリア様式の声楽曲の手ほどきを始め、オーケストラ総譜のピアノでの初見演奏法なども教授したと伝えられています。結果的に見て、シューベルトはオペラの分野では成功せず、歌曲においても、イタリア様式とは対極的なドイツ・リートの開拓者として独自の道を歩んでいくことになったわけですが、師サリエリに対しては生涯変わらぬ尊敬と感謝の念を抱き続けたのでした。
このように、音楽家として頂点を極めながらも、その立場に安閑とせず、自分の得た知識と経験を若い世代に積極的に伝えようと尽力してきたサリエリ。教え子の代表格2人の作品とともにその音楽を聴いて、しばしこの不運な音楽家に思いを馳せる。今夜の演奏会は、まさにモーツァルト・イヤーに相応しい企画だと言えるのではないでしょうか。開演が楽しみになってきました。
シューベルト 「魔法の竪琴(ロザムンデ)」序曲
ウェーバーの歌劇《オイリュアンテ》の台本作家として知られる女流作家ヘルミーネ・フォン・シェジーの新作戯曲『キプロスの女王ロザムンデ』上演のために、1823年12月、シューベルトは劇音楽の作曲を依頼されます。しかし本番までほとんど期間がなかったために、劇中の10曲は何とか作曲できたものの、序曲は間に合わせることができませんでした。そこで初演に際しては、前年に作曲していた歌劇《アルフォンゾとエストレッラ》の序曲をそのまま転用して急場を凌いだのですが、その後、1820年に作曲していた劇音楽《魔法の竪琴》の序曲のタイトルを《ロザムンデ》序曲に変更して、4手用のピアノ作品として出版しました。そういった経緯から、管弦楽版の劇音楽《ロザムンデ》の序曲としても《魔法の竪琴》序曲が演奏される形が一般化し、現在に至っています。
曲は、展開部を欠く序奏つきソナタ形式で書かれています。悲劇的な序奏、軽快な第1主題、優美な第2主題、そして心沸き立つコーダ、いずれの部分においてもシューベルトならではの明快にして繊細な音楽が堪能できます。
サリエリ 「ラ・フォリア」の主題による26の変奏曲
サリエリ晩年の1815年の作品で、作曲に至った経緯、初演の様子などは明らかになっていません。主題が提示されたあとに26の変奏が続き、最後にコーダが付された、全体で20分ほどの作品ですが、これほど大部の管弦楽のための変奏曲は、おそらく空前にして、後を継ぐのはようやく1873年になってから、ブラームスの《ハイドンの主題による変奏曲》の登場を待たねばなりません。
フォリアとは、もともとはポルトガル起源の3拍子系の急速な踊りを指す言葉でしたが、17世紀に入るとむしろ落ち着いたリズムを持つ舞曲へと性格を変えたばかりか、固定された低声部と旋律の枠組みを持つ、1つの定型へと収斂していったのでした。この素材を世に広める嚆矢となったのが1700年に出版されたコレッリのヴァイオリン・ソナタ作品5-12「ラ・フォリア」で、以降、ヴィヴァルディ、バッハ、ケルビーニ、リスト、ラフマニノフなど、数多くの作曲家がそのフォリアを取り込んだ作品を書いています。サリエリの変奏曲もまさにこの流れの中に位置づけられるもので、クラリネットとファゴットの四重奏で提示されるフォリアの主題は、コレッリのソナタの冒頭で聴ける形とまったく同じものになっています。
もともとの主題が帯びている哀調ゆえに、過ぎ去った日々を回顧する老境のサリエリの姿が目に浮かぶかのようですが、1つひとつの変奏曲は、管弦楽を扱う確かな技法の上に創意工夫が溢れ、間然とするところがありません。
ベートーヴェン 交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
交響曲第5番と並行して作曲が進められ、1808年に完成したこの曲、今夜演奏される3曲の中で最も早い時期の作品であるという点が、やや意外に感じられるかもしれません。前述したように、サリエリと衝突するきっかけともなった初演の日程、1808年12月22日、その日のプログラムは、交響曲第5番と第6番にピアノ協奏曲第4番、そして合唱幻想曲、その他、全体で4時間を超えるという凄まじいもので、会場となった真冬のアン・デア・ウィーン劇場は寒く、演奏者、聴衆ともに集中力を欠き、散々な出来に終わったことが伝えられています。
交響曲第5番がそれこそ絶対音楽の権化であるかのような隙のない構造を持つ厳しい音楽であるのに対し、ベートーヴェン自身が各楽章に標題を与え「田園交響曲」と明記したこの第6番は、情景を思い浮かべながらリラックスして聴ける穏やかな音楽であることは確かでしょう。ただ、第1楽章における徹底的な動機の活用、第1楽章の素材の後続楽章での再利用、複数楽章の切れ目なしでの接続、終楽章における到達点としての音型の類似などなど、作曲技法の点では、第6番は第5番の双生児であると言える特徴を備えています。同様の手法を用いながら、かくも対照的な情感を呼び起こさせる音楽を創り出す、まさにベートーヴェンの天才のなせる業です。
(文責:麻生哲也)
モーツァルト ディヴェルティメント第2番 変ロ長調 KV.137(Ambarvalia)
モーツァルトはその短い35年という生涯のうち、約10年2ヶ月を旅に費やしたという。特に幼少期の忙しさは尋常ではない。父レオポルドはモーツァルトの神童ぶりを各地にアピールし、彼の就職先を早くから決めておこうと、ヨーロッパ各地を精力的に飛び回った。旅はモーツァルトが6歳の頃から開始され、1762年ミュンヘン、1762~1763年ウィーン、1763~66年ヨーロッパ広域、1767~69年ウィーン、1769年12月~1771年3月イタリア、1771年8月~1771年12月イタリア、という、超がつくほどのハードスケジュールだった。
本日演奏するディヴェルティメント第2番は、その慌しい旅行の束の間の帰国期間、故郷ザルツブルグで作曲された、愛らしい小品である。それは、折しもモーツァルトがちょうど16歳の誕生日(1772年1月27日)を迎えた頃であった。16歳は、日本でいえば高校1年生。その早熟ぶりには、いつもながら圧倒される。
「ディヴェルティメント」とは、イタリア語の「divertire」(楽しませる)に由来する言葉で「喜遊曲」とも訳される。室内で夕食時に演奏されることが多く、軽快で明るい、くつろいだ雰囲気を持つ曲がふさわしいとされている。
しかし、このディヴェルティメント第2番に、その基準は、あまりあてはまらない気がする。
まず変わっているのは、曲の楽章構成である。普通のディヴェルティメントの楽章構成は「急→緩→急」が一般的だが、この2番に限っては「緩→急→急」という構成。つまり楽章ごとにテンポが上がっていく構成となっている(ストレッド型というそうだ)。
また、曲想的に変わっているのは、その第1楽章である。冒頭は、ひとりひっそりと呟くようなヴァイオリンのモノローグで始まる。それは少しずつ悲しみの翳を帯びていくが、だんだんと他の楽器が寄り添うように重なっていき、それから、心のもやもやを、さっと吹き払うような上昇音型が一斉に奏でられる。その頃には、曲全体に幸せな光が満ちていて、これが16歳の少年の手から生まれたものかと思うと、驚きを禁じえない。
第2楽章は一転して、溌剌としたアレグロ。ヴァイオリンが鮮やかな下降音型で駆け巡り、展開部は伸びやかな旋律が広がる。強弱の対比も鮮やか(なはず)。そして、第3楽章は8分の3拍子の愛らしい舞曲風。思わず踊り出しそうな躍動感のなかにも、堂々とした風格が失われていないのが印象的である。
ハイドン チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.Ⅶb-1
ハイドンの全作品をまとめたホーボーケンの作品目録には、真偽不明の1曲も含めると、6曲のチェロ協奏曲が記されている。しかしそれらの中で真作と認められているのは第1番から第3番までの3曲で、しかも第3番は楽譜が失われてしまっている。このため現在、真にハイドンのチェロ協奏曲といえるのは第1番と第2番だけであるが、これらの作品も作品発掘からその真贋をめぐる論争まで紆余曲折がある。第1番はおよそ200年間も貴族の書庫や図書館に眠っていたが、1961年にチェコの音楽学者プルケルトによってハイドン時代の写譜が発見され、使用されていた紙の透かしをはじめとする資料的側面から信憑性の高い筆写楽譜と判定されると共に、冒頭主題をハイドン自身が「草案作品目録」に記載していることから真作であると実証された。第2番も、自筆譜の所在が明らかでなくなっていた19世紀以降、自筆譜が発見されるまでの約1世紀に渡り真贋が真剣に議論された時代があった。
本日演奏されるチェロ協奏曲第1番は作品の様式研究などの結果、1765~1767年頃に作曲されたと推定されている。当時30代になったばかりのハイドンは、エステルハージ侯の楽団の副楽長に就任していた。ハンガリー貴族の中で最も裕福で、代々の当主が音楽愛好家であった侯爵家の宮廷楽団には多くの優れた奏者がおり、彼らのためにハイドンは様々な協奏曲を作曲した。チェロ協奏曲第1番は1761年から1769年まで同団のチェロ奏者を務めたヨーゼフ・ヴァイグルのために作曲したのではないかと考えられている。この協奏曲は、トゥッティとソロを鋭く対比させるリトルネッロ形式や単調な伴奏音形など、多くの点でバロックの協奏曲の名残をとどめているが、第1楽章と第3楽章がテンポの速いソナタ形式で書かれているなどバロックと全古典派を融合しつつあった初期のハイドンの姿勢が示されている。
第1楽章 Moderato ハ長調 4分の4拍子
協奏風ソナタ形式をとっているが、ソロとトゥッティを鋭く対比させるリトルネッロ形式の名残が見られる。トゥッティによる快活な第1主題はやがて第1ヴァイオリンを中心とした旋律的な第2主題へと引き継がれ、再びトゥッティによるコデッタにより管弦楽提示部が結ばれると、独奏チェロが華やかに登場する。再現部は独奏チェロを中心に進められ、カデンツァを経て華やかなコーダで締めくくられる。
第2楽章 Adagio ヘ長調 4分の2拍子
三部形式。独奏チェロと弦楽のみで演奏される叙情的な楽章。弦楽合奏による魅惑的な2つの主題を独奏チェロ中心に展開させていく。中間部で用いられる短調の淡い哀愁を漂わせたメロディーが、ハイドンが旋律の大家である事実を感じさせる。そして主調による主題再現から作曲者自身による短いカデンツァを交え、静かに結ばれる。
第3楽章 Allegro molto ハ長調 4分の4拍子
協奏風ソナタ形式。バロック的要素を残す第1楽章とほぼ同じ構成をとっている。動機的な第1主題からより旋律的な第2主題が管楽器によって提示されたのち独奏チェロが登場する。展開部の長時間に渡り保持されたハイ・ポジションの使用は当時の習慣を超えるもので、ヴァイグルが如何に名手であったかが窺い知れる。再現部で主題がより華やかな形で奏され、華麗さ極まったところでトゥッティによる短いコーダで結ばれる。
メンデルスゾーン 交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」
メンデルスゾーンは1809年、非常に裕福なユダヤ人実業家の家に生まれ、何不自由のない環境のもと、17歳で「真夏の夜の夢」序曲を完成させるなど、早くから際だった音楽の才能を発揮した。1847年に38歳で夭逝してしまった点を除けば、(音楽家としては例外的に)順風満帆な人生を送ったとされている。
しかし、こと交響曲というジャンルについてはそう単純な話でもなかったようだ。「真夏の夜の夢」や「フィンガルの洞窟」を中心とした演奏会用序曲、協奏曲、声楽曲を発表することで名声を確立し、ライプツィヒ・ゲヴァントハウスの音楽監督・指揮者として活躍していた彼にとっては、交響曲のみがその業績から欠けていた。
ベートーヴェンは「第九」を1824年に初演し、その3年後に没した。以後おびただしい数の交響曲が作曲されたが、ついに彼の9曲の交響曲に比肩するものは生み出されなかった(「超えられない壁」というやつだ)。現存するオーケストラ・レパートリーとしてあげられるのは、ベルリオーズの「幻想交響曲」くらいのものであろう(シューベルトの大ハ長調「ザ・グレート」ですら、「しまいこまれたまま行方不明になっていた」)。メンデルスゾーンにとっても、ゲヴァントハウスの定期演奏会で取り上げる新作交響曲がどれもひどいということへの苛立ちがあった。「…手元に6曲の新作交響曲がある。それがいかなるものか、神はご存知だろうが、私の気に入るものはないだろう。しかし、この件について悪いのは誰よりも私なのだ。他のものはともかく、この私が交響曲の分野において成功できないとは。なんてこった!」と知人にもらしている。
このイ短調交響曲は、そのような状況の中、円熟した芸術家・メンデルスゾーンが後世に残せるものと唯一認めた交響曲である。若書きとして扱われがちな第1番や、声楽を伴ったカンタータ風の第2番「讃歌」はさておき、今日第4番とされる「イタリア」の校正作業はついに生前終わらず(あきらめたという説も)、第5番「宗教改革」に至っては「まったく我慢できず」「燃やしてしまいたい」とまで吐き捨てている(これらは生前発表・演奏はされているが、出版されたのは彼の死後しばらく経ってからである)。
メンデルスゾーンがこの曲の着想を得たのは1829年7月30日の夕刻、エディンバラのホリルード宮殿を観光中のことであった(詳細な記録が残っている)。作曲家としての自己を確立しようと強く意識した旅行中のことであり、これを自らの個性と実力を示す交響曲として完成し、早い時期に披露して世に問うことを強く望んでいた彼だったが、完成までには実に13年を要した。
彼が「スコットランドの霧とメランコリーを多分に含んだ、スコットランド交響曲のはじまり」と呼んだこの着想は、リート風の楽節で、16小節からなる。当初彼の頭にはクラリネットとフルートの音があったようだが、最終稿ではオーボエとヴィオラが旋律を担当している。続いて、レチタティーボ風のヴァイオリンがこれに応える。ヴァイオリンと2本のフルートによる印象的な応答を経て、ソナタ形式の主部(第1主題=クラリネット1本とヴァイオリン)が導かれている。第2主題はクラリネットによって奏されるが、全曲を通じたこの楽器の重用が目立つ。
第2楽章はスコットランドの民俗楽器であるバグパイプを想起させる節回しが多用される、軽快なスケルツォである。管楽器のタンギングにご注目あれ。
第3楽章のアダージョでは荒々しい付点動機が連続するが、途中チェロとホルンに現れる旋律の美しさはこの曲の白眉である。
前楽章を断ち切るようにはじまる終楽章は、勢いのある跳躍と「刻み」とが競演している。コーダで明快な長調に転じるが、「人類愛」や「苦悩から勝利へ」といった、わかりやすい(大団円的な)感動を喚起するものではなく、「スコットランド」という通称から受けるイメージから遠くない、清々しさを伴ったエンディングであるといえるだろう。
オーケストラは標準的な二管編成であるが、彼にしては珍しく、ホルンを4本用いていることが注目される。調性の異なるホルンを二対用いることで和声的厚みは倍増し、ホルンをソロ楽器として扱った際の管弦楽の響きも損なわれない。実際、第3楽章には3番ホルンに大ソロが控えている。
メンデルスゾーンは、1842/43年にこのイ短調交響曲を発表する際に、着想の起源を厳格に伏せ、存命中はそれを貫き通した。「スコットランド」という通称は、彼の知人や友人たちが作品を語りだすことによって公の場に持ち込まれたものであった。
彼は、音楽を言葉で表現すること自体が不可能だと悟っていた。言い換えれば音楽によってこそ彼の意図が明確に再現されるということになるだろう。
「…真の音楽は、言葉よりも千倍も良いもので私たちの魂を満たしてくれます。…もし私がその時に何を考えていたのかと問われるならば、そこにあるがままの歌そのものだと答えましょう。…音楽であれば、私たちは両者とも真に理解できるでしょう。…」
※参考文献: 星野宏美著『メンデルスゾーンのスコットランド交響曲』(音楽之友社、2003)
メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」序曲
4つの和音が誘う、ファンタジーの世界。
かすかな森のざわめき。飛び交う妖精たち。
突然のまばゆい陽光。祝祭の喜び。愛の幸福。
見える世界と見えない世界のクロスオーバー。
やがて、すべてはまどろみ、眠りにつく。
メンデルスゾーン、17歳。シェークスピアの戯曲「真夏の夜の夢」を題材とするこの序曲は、なんと霊感と才気に満ちあふれていることか。
裕福な銀行家の家に生まれ、また、バッハを敬愛し、古典への造詣の深かったメンデルスゾーンの作品は、端正で優美、上品さを感じさせるものが多い。その中でも、この「真夏の夜の夢」序曲は、前年に作曲された弦楽八重奏曲と並んで、若きメンデルスゾーンの生んだ傑作といえる。シューマンは、「この曲は、この作曲家の他の作品には見られないほどの青春の輝きを発している。熟練した大家が、最も幸福な瞬間に、最初で最高の飛躍をしたのである」と語ったという。
この曲でのメンデルスゾーンの管弦楽法は、ほとんど室内楽のような精密さと、常識を超える大胆さが表裏一体となっており、それが曲にみずみずしい色彩感と面白さを与えている。冒頭の木管の和音や分割されたヴァイオリンの刻み、独特の和声配置や最弱音の多用、テューバ(本来は、オフィクレイドという現代では廃れてしまった金管の低音楽器)の効果的な使用、などなど。
それだけにこの曲は、オーケストラの実力が問われる、ある意味とても恐ろしい作品なのだが、同時に、あまりにも魅力的な作品だ。ブルーメン初の再演曲にこの曲が選ばれたのも、単なる偶然ではあるまい。
なお、メンデルスゾーンは34歳の時に、この序曲に続く一連の劇音楽を作曲し、ポツダムの宮殿でこの劇音楽によるシェークスピアの「真夏の夜の夢」が上演された。序曲とこれらの劇音楽は、17年もの時の流れを感じさせない連続性、一体感があり、「スケルツォ」、「間奏曲」、「夜想曲」、そして有名な「結婚行進曲」など、序曲の霊感を受け継ぐ魅力的な作品が含まれている。現在は、組曲の形で演奏されることが多いが、これまたいつか演奏してみたいものだ、と個人的に思っているところである。
ハイドン 交響曲第100番 ト長調 「軍隊」
ブルーメンがハイドンの作品を取り上げるのは、交響曲第99番(第5回定期)、同97番(第16回定期)に続き、三度目である。
ハイドンは1761年(29歳)からオーストリア東部の小都市・アイゼンシュタットに居を構えるエステルハージ侯爵に仕える身となった。侯爵は熱狂的といってよいほどの音楽愛好家であり、その宮殿には400人以上を収容できるオペラ劇場をはじめ、それぞれ専用の喜劇場、人形劇場が備わっていた。盛時には年間250を超える上演回数をこなしたとの記録もあり、もはや一つの文化発信拠点であったといえるだろう。宮廷楽長ハイドンは作曲だけでなくあらゆる音楽の指揮を任され、お抱え音楽家たちの下稽古を助け、オーケストラにおいては自身クラヴィーアを担当し…といった超人的な活躍を28年に渡って続けたのであった。この間、午前中に鍵盤楽器の前に座って即興演奏に興じることでテーマを探し、昼食後はいわゆる「お仕事」、夜には午前中にメモした主題を元に作曲を行う、と極めて規則正しい生活を送っていたという(青年期のエピソードが少ないのも頷ける。妻はいたが不仲だった。子供もない)。
金銭的には恵まれた待遇であり、作曲家としての名声は宮廷を通じてヨーロッパ中に轟くようになったが、片田舎アイゼンシュタットから離れられない自分にとってウィーン、パリ、ロンドンといった大都市への憧憬が常にあった、と後年述懐している。
1790年に侯爵が亡くなり、自由の身となったハイドンのハートを射止めたのはロンドンで活躍していたヴァイオリンの名手・ザロモンであった。自ら大オーケストラを編成し、コンサートマスターとして演奏会を主催していたボン出身の彼は、新作の交響曲を含む作品を、作曲者自らの指揮で演奏するという企画をもってハイドンを訪れたのである。入場料を払って演奏会場を埋め尽くす大観衆を前に演奏できるという機会はハイドンの目にも大いに魅力的に映ったのだろう。既にモーツァルトが没し、ベートーヴェンがウィーンで活躍しはじめた年代において、ハイドンはイギリスへの進出を果たし、また自らと大衆のために音楽を作れるようになったのだ。
今回取り上げるト長調交響曲は、ウィーンで着手され、ロンドンで完成された。初演は1794年。ザロモンの依頼による12曲の新作(ザロモン交響曲)の中でも特に好意的に迎えられたという。
第一楽章は他のザロモン交響曲同様、アダージョの序奏に導かれたソナタ形式のアレグロである。第一主題は二本のオーボエを伴奏に従えたフルートによって奏される。ヴァイオリンにあらわれるチャーミングな第二主題は、ボッセ氏いわく、「ボッティチェルリの絵画『春』にある花(Blumen)のように」。
第二楽章は行進曲風のアレグレット。この楽章のみクラリネットが加わる。後半にはオーストリア軍の進軍ラッパを模したファンファーレが登場し、打楽器群を伴ったトルコ風のマーチが続く。
第三楽章はオーソドックスなメヌエットとトリオ。ボッセ氏の笑顔に応えられるか。
第四楽章はプレスト。ハイドン特有のユーモアが散りばめられている。コーダでは再び打楽器群が加わり、華やかに曲を締めくくっている。「軍隊」というよりは、「軍楽隊」といったところが正しいように思う。
なお、ハイドンにとっては「100番目の交響曲」という認識はなく、もちろん「軍隊」という副題もなかった。いずれも後世名づけられたものであることを付記しておく。
ベートーヴェン 交響曲第1番
作曲:1799~1800年
初演:1800年4月2日 ウィーンのブルク劇場にて、ベートーヴェン自身の指揮で。
献呈:スヴィーテン男爵
ある日のブルーメン・フィルの練習で、トレーナーのS先生がベートーヴェンを始める前にこうおっしゃった。「みなさん、この曲はハイドンの105番のつもりで弾いてください」。
104曲の交響曲を残したハイドン(「交響曲の父」と呼ばれた)の愛弟子であるベートーヴェン。受け継ぐところは多かったかもしれない。ベートーヴェンは1770年ドイツのボンで生まれた。音楽家を志望していた彼は、1787年に音楽の都ウィーンへ旅行。当時ウィーンでは、ハイドンとモーツァルトという二大巨匠が活躍中であった。ベートーヴェンはモーツァルトに面会を求め、彼の前で即興演奏を披露。モーツァルトは「今に彼は世の話題となるだろう」と周囲の人たちに語っている。ベートーヴェンはそのままウィーンに滞在したかったが、母親の危篤のためボンに帰った。そしてそれを待っていたかのように彼女は亡くなった。
1792年、1回目のロンドン旅行からの帰り道、ボンに寄ったハイドンはベートーヴェンに会い、彼の作品を見た上で、彼の弟子入りを許した。そしてその年の11月、ベートーヴェンはウィーンに旅立ち、ハイドンの許で本格的に作曲の勉強を始めた。しかし、ベートーヴェンは必ずしもハイドンの教えに満足してはいなかったようだ。課題に対する添削をちゃんとやらなかったらしい。ハイドンは、1794年からの2回目のロンドン旅行にベートーヴェンを連れていくつもりだった。少なくとも、ハイドンにとってはベートーヴェンは弟子のつもり。ベートーヴェンがハイドンのロンドン旅行に何故同行しなかったのかはわからないが、あるいはそんな感情が働いていたのかもしれない。あこがれの地ウィーンで音楽家として生活することを夢見ていたベートーヴェンは、精力的に活動する。ハイドンがロンドンへ行ってしまったのをいいことに、他の先生を探し出し、勉強を重ねた。そんな彼のウィーンでの集大成がこの第1番の交響曲だった。完成は1800年。ハイドンやモーツァルトといった大先輩たちの影響を脱却すべく、数々の技巧と個性を駆使して作曲された。
ハイドンとベートーヴェンが決定的に仲違いをしたのは1801年のこと。ベートーヴェンの気持ちを何となく察していたハイドンは、ベートーヴェンのバレエ音楽「プロメテウスの創造物」を見た際「なかなかいい作品だ」とそれでも弟子を褒めたのだが、それに対してベートーヴェンは「あれは長い間かかった創造ではないですよ」と、ハイドンが苦心をして作り上げた大作「天地創造」を皮肉ったために、ついにハイドンも怒り心頭、「君のは創造物でもなんでもない、とんでもない作品だ」とけなしつけたのだった。
ある日の練習でボッセ氏がこうおっしゃった。「この曲を作ったころは、ベートーヴェンも若かったんだよ」。
確かに曲からはベートーヴェンの若さと自信がしっかりと感じられる。あまりにも偉大な「105番」が完成したといえるだろう。しかし、この時期すでに彼は耳の変調を感じはじめていたのだった……。
第1楽章 Adagio molto – Allegro con brio
当時としては珍しく長い序奏を伴う。しかも、ハ長調といいながらもハ長調を認識できるのはしばらくたってからのこと。Allegroに入ってからはソナタ形式。第1主題をヴァイオリンで演奏するのは当時のセオリー通り。第2主題は木管楽器が流れるように歌う。
第2楽章 Andante cantabile con moto
初演当時、この楽章はモーツァルトの交響曲第40番に似ていると話題になったそうだが、もっと爽快でチャーミングなもの。流れるような部分とリズミックな部分の組み合わせが印象的。ソナタ形式。
第3楽章 Menuetto : Allegro molto e vivace
従来の優雅なメヌエットとは違った、躍動的な音楽。メロディーは音階が中心のシンプルなもの。トリオ(中間部)は一転して同じ音を繰り返す管楽器に風のようにヴァイオリンが飾りをつける。
第4楽章 Finale : Adagio – Allegro molto e vivace
強打一発。しかし、第3楽章をひきずるかのように、しつこく音階を作ろうとする序奏が続く。Allegroに入ってからも、音階から始まるメロディーが高揚感を感じさせる。ソナタ形式。各楽器に出てくる音階の絡みからは、緊張感とともに音楽の素晴らしさがあふれ出る。曲の締めくくりは、ベートーヴェンならではの立派なものがすでに確立されている。
エルガー 序奏とアレグロ
エドワード・エルガー(1857-1934)は大器晩成タイプといえる。プロの作曲家として認められるようになったのは40歳半ば過ぎ。楽器屋の息子と して生まれ、楽器に囲まれて育ったものの、正規の音楽教育は受けることなく育った。しかし、音楽をこよなく愛し、独学で学んだピアノ、ヴァイオリン、ヴィ オラ、ファゴットの腕を活かして、近所の病院や教会で演奏したり、ヴァイオリンやピアノを教えたりしながら、空いた時間に作曲をするなど、音楽的には充実 した生活を送っていた。27歳のときには、地元のウースター大聖堂で行なわれた「三大合唱祭」にヴァイオリン奏者として参加。ドヴォルザークの指揮のも と、彼の『スターバト・マーテル』と交響曲第6番を演奏している。
32歳のときに8歳年上のアリスと結婚。結婚後、本格的に作曲活動を始めることを決意したエルガーは、妻アリスを連れて、ロンドンに移住する。作品はなか なか受け入れられず、苦しい生活を余儀なくされたが、1899年42歳のとき『エニグマ変奏曲』が成功し、世間の名声を得てからは、王室音楽主任に任じら れ、数々の勲章や位を受賞するなど、とんとん拍子。次々に力作・大作を発表し、イギリスを代表する作曲家として不動の地位を築いていった。
この『序奏とアレグロ』は、エルガー48歳、円熟期の作品である。友人アウグスト・ヨハネス・イェーガー(『エニグマ変奏曲』の第9変奏のモデル)の「ロ ンドン響のために"輝かしく速い"スケルツォ作品を書いてみてはどうか」という提案が、この曲を作曲する直接のきっかけとなった。主題となった旋律は、エ ルガーが西ウェールズを旅行したときに耳にした民謡のモチーフ。曲は華やかでドラマティックな導入から始まり、牧歌的な美しい序奏を経て、きびきびとした アレグロに突入する。わずか15分たらずの中に、生き生きとした躍動感と生命感がぎっしり詰まった、香り高い名品である。
この曲の初演は1905年3月8日、ロンドン響。この曲はエルガー自身「出来がいい」と自信を持っていたにもかかわらず、聴衆にはまったく受け入れられな かった。それは当時のロンドン響の弦セクションのレベルが、この曲を演奏するには低すぎたせいではないか、と言われている。私たちの演奏がそうならないよ う祈るばかりである。
シベリウス 交響曲第7番
ジャン・シベリウス(1865-1957)の生涯の最後の30年余りは謎に包まれている。交響曲第7番の完成が1924年、その後大作といえば交響詩『タ ピオラ』、劇音楽『テンペスト』を翌年ものしたくらいで、その後数曲の小品を書いているものの、創作はぱったりと止んでしまう。いくつかの証言によれば、 シベリウスは自らの創作力に衰えを感じつつも交響曲第8番を作曲しようとしていたらしい。1931年の日記にも、「私は『第8番』を書いている。青春の 真っ只中だ」とある。しかしこれは結局完成することはなかった。その理由は不明だが、有力な説は「自己批判の強さから、断片的に書いては破棄してしまって いたのではないか」というものである。なるほど言われてみれば、交響曲第5番の初演が成功を収めたにもかかわらず大幅な改訂作業をしたり、交響詩『タピオ ラ』を出版段階で「書き直したいから返して欲しい」と語ったりしたというエピソードは、彼の自己批判の強さを物語っているようだ。
計らずも彼の最後の交響曲となってしまった第7番は、第5番、第6番とほぼ同時に着想された。1918年の手紙には「第7交響曲、生命と活動の喜び、情熱 的なパッセージを伴って。3楽章制で、フィナーレはヘレニック(ギリシャ風)・ロンド」とある。しかし書き進めてゆくうちに、第7番は単一楽章の曲とな り、『交響的幻想曲』と名づけて発表する予定であったが、初演の段階になって再び『交響曲第7番』に戻した。当時、このような独創的な交響曲は他に例がな かった。あらゆる動機は非常に単純かつ素朴なもので、それが有機的に一点の無駄もなく発展していく。また、一度は幻想曲と名づけたように、フィンランドの 自然の森羅万象を映し出したかのごときある種の標題性をも持ち合わせている。この絶対音楽的性格と標題音楽的性格の二重構造こそが、交響曲第7番の魅力を 不動のものにしていると言ってもよいだろう。
さて、聞く側に立ってみると、この曲には重要な2つの主題が計5回、アーチ状に登場するのに気付く。すなわち、序奏部の木管による主題、要所要所で現れる3度の長いトロンボーン独奏、そして終わりに登場するフルートとファゴットによる主題である。
まず、弦とホルンの神秘的な和声進行の中から木管が初めて主題らしきものを提示する箇所において、聞く者を深い雪と氷に包まれた森の中へと迷い込ませる。 この主題が一段落すると、弦による静謐な歌が優しく包みこみ、次第に全楽器が加わっていく中から1回目のトロンボーン独奏が登場する。この箇所は3度登場 する独奏の中でも最も印象的で崇高な部分であり、フィンランドの叙事詩『カレワラ』に登場する原初の神々を想起せずにはおれない(管弦楽におけるトロン ボーンの独奏といえば、モーツァルトの『レクイエム』から、マーラーの交響曲第3番、リムスキー・コルサコフの序曲『ロシアの復活祭』に至るまで、何がし かの宗教的な意味合いをもって用いられてきたわけだが、このシベリウスの用法も同様の意味があると考えられる)。その後もこのトロンボーン独奏を媒介とし て場面転換が行われるが、3度目の独奏が終わった後から曲は最大の混沌と盛り上がりを見せ、やがて沈黙の中から冒頭の主題の変形がフルートとファゴットに よって奏される。いつまでも見ていたい夢から覚めたような一抹の寂しさを覚えるが、それをコントラバスのピツィカートの先導によって弦が慰撫するように波 打ち、全楽器がハ長調の永遠の音を奏でてこの曲を終える。なお、完全にハ長調の和音に解決するのは最後の一瞬だけであり、直前までハ長調の和音にない音 (ニ音、ヘ音、ロ音)がどこかしらで鳴っている。最後の最後まで不思議な音の世界を聞き取ることができるだろう。
ところで―シベリウスは「交響曲やその他の大曲の構想が自分の脳裏をおとずれるのは厳冬に限られている」(1941年、ヘルシンキにおける近衛秀麿との会見で)という談話を残している。ここにはシベリウスの音楽の本質、その一端が現れているように思えてならない。
エルガー エニグマ変奏曲
エニグマとはラテン語で「謎」。この曲の正式名称は『オリジナル主題による変奏曲』だが、エルガー自身がスコアに「ENIGMA」と書き込み、初演のプ ログラムノートに彼自身が「この曲にぼくはエニグマ(謎)を含ませた」と言及したことから、『エニグマ(謎)変奏曲』と呼ばれている。「謎」とは、いった い何なのだろうか?
*第1の謎:誰を表しているか、という謎
「私は1つの変奏曲をスケッチした。それは1つの主題に基づいており、私はその作曲を楽しんだ。なぜなら、それぞれに友人たちのニックネームをつけたから。君はニムロドという名前で出てくる」byエルガー。
このエニグマ変奏曲は14の変奏曲から成り、その変奏曲の冒頭には、それぞれアルファベットのタイトルが付けられている。上記のエルガーの言葉によると、 そのアルファベットは変奏曲中に描写された人物のイニシャルらしい。このイニシャルが具体的に誰を指しているかは研究が進んで、第13変奏「***」を除 いて、すべて明らかにされている。
*第2の謎:「演奏されない主題」、という謎
「全曲を通じて別の大きな主題があるのだが、それは実際には演奏されない」byエルガー。
この「演奏されない」主題、いわば「沈黙の主題」については諸説あって、いまだ解明されていない。有名な説としては①曲の冒頭で提示される主題のリズムが 「Edward Elgar」の自然な発音のリズムを表していることから「沈黙の主題=エルガー本人」という説、②主題の最初の音が「B」、2小節目の最後の2音が「A」 「C」、7小節目の主題の最終音が「H」であることから「沈黙の主題=Bach」という説、③エルガーが友人を描きこんでいることから「沈黙の主題=エル ガーの友情」という説、などが挙げられる。あとは、どことなく似ているという理由から、『蛍の光』、『イギリス国歌』、モーツァルトの交響曲第38番『プ ラハ』、グレゴリオ聖歌の『怒りの日』、スタンフォードの『レクイエム』なども挙げられている。しかし、いずれの説も決定打に欠けており、これからも議論 が続くことが予想される。
それでは曲を具体的に見ていきたい。
0.主題
ため息のような旋律が、問いと答えのようにひっそり交わされる。この最初の9小節の主題が、以下14曲に変奏される。
第1変奏 「C.A.E.」=キャロライン・アリス・エルガー(♀)
エルガーの妻。主題から切れ目なく演奏される。内省的でつつましい美しさにあふれた変奏。
第2変奏 「H.D.S-P. 」=ヒュー・デイヴィッド・スチュアート=パウエル(♂)
ピアニスト。小刻みに跳ね回る16分音符は、彼がピアノを弾いている様子を描写しているよう。
第3変奏 「R.B.T.」=リチャード・バクスター・タウンゼント(♂)
俳優。エルガーのゴルフ友達。ユーモラスなクラリネットのソロが、彼の裏声を使う様子を描写する。
第4変奏 「W.M.B.」 =ウィリアム・ミース・ベイカー(♂)
地主。スフォルツァンドは、彼が大声でまくしたて、大きな音を立てて扉を閉めて部屋から出ていくさまだと言われている。
第5変奏 「R.P.A.」=リチャード・ペンローズ・アーノルド(♂)
詩人の息子。物悲しい旋律と、軽やかな旋律の交錯は、彼の気まぐれな性質を表しているよう。
第6変奏 「Ysobel」= イザベル・フィットン(♀)
ヴィオラ奏者。ヴィオラのソロは、イザベルが跳躍の音型に挑戦している様子だと言われている。
第7変奏 「Troyte」=アーサー・トロイト・グリフィス(♂)
建築家。打楽器が活躍する賑やかな曲。ピアノを練習するが、うまくいかず癇癪を起こしている様子、という説と、サイクリング中、雷に襲われ木陰に避難している様子、という2説がある。トロイトはのちにエルガー夫妻の墓石を設計した。
第8変奏 「W.N.」=ウィニフレッド・ノーペリー(♀)
オーケストラの事務局員。温かい家庭的な雰囲気の曲。彼女の明るい笑い声と、彼女が住んでいた屋敷が描写されている。
第9変奏 「Nimrod」=アウグスト・J・イェーガー(♂)
音楽出版社ノヴェロ社の社員。エルガーは彼には「謎」のことを話し、「僕は君の外見上の姿ではなく、善良で愛すべき正直な魂だけを描いた」と伝えている。全曲中最も有名で、単独で演奏されることも多い。
第10変奏 「Dorabella」=ドーラ・ペニー(♀)
夫妻の友人。弦楽器のトリルは、彼女の「どもり」を表していると言われている。ヴィオラの朗々としたソロが印象的。
第11変奏 「G.R.S.」=ジョージ・ロバートソン・シンクレア(♂)
オルガニスト。川に転落した彼の愛犬ダンが、必死に泳ぎ、岸にたどり着く顛末が描写される。
第12変奏「B.G.N.」=バージル・G・ネヴィンソン(♂)
チェリスト。彼と、第2変奏に登場したスチュアート=パウエルと、エルガーは、3人でピアノトリオを組んでいた。
第13変奏 (***)(♀)
この変奏だけ、誰がモデルか、はっきり分かっていない。①船旅で知り合ったメアリー・ライゴン夫人②昔の婚約者ヘレン・ウィーバー③エルガーと相思相愛 だったジュリア・H・ワシントン、という3人が候補として有力である。ティンパニが船のエンジン音のような音を、クラリネットがメンデルスゾーンの『静か な海と楽しい航海』の引用を奏でているため、「船旅」と関係があることが予想される。
第14変奏 「E.D.U.」= エドワード・エルガー(♂)
作曲者本人。勇壮なフィナーレ。途中、妻アリス(第1変奏)とニムロド(第9変奏)が顔をのぞかせ、最後はオルガンも加わり豪華な響きのうちに締めくくられる。
ブラームス 悲劇的序曲
ブラームスはその作曲活動において、同時期に相反する性格の2つの曲を書くという傾向を持っていた。例えば、「ベートーヴェンの9曲の交響曲に匹敵する ものを」と考え、構想から20年もかけて作り上げた交響曲第1番と、それまでの長い道のりがまるで嘘であったかのように、その翌年に早くも完成させてし まった交響曲第2番が挙げられる。今回取り上げるこの『悲劇的序曲』についても同様のことが言える。作曲されたのは1880年であるが、ちょうど同じ年 に、ブラームスはブレスラウ大学から名誉博士号を贈られた返礼として『大学祝典序曲』を書いている。名前からしてもその対照性は明確である。
さて、『大学祝典序曲』と『悲劇的序曲』だが、ブラームスのこんな書簡が残されている。「大学のための曲は私をなおも別の序曲へと誘惑しています。私は それを『劇的な』とだけ名づけていいと思っています。」「この機会に私の孤独な気持ちに、『悲劇的序曲』を書くのを誓わざるを得ませんでした。」また、作 曲の数年前から直前にかけて、生涯愛を寄せたクララ・シューマンの息子フェリックスの死、親友の画家フォイヤーバッハの死、同じく親友だったヴァイオリン 奏者ヨアヒムとの不和(実際に絶交状態になったのは作曲後だが)といった出来事が続いていた。こうしたことが積み重なり、長年続いてきたメランコリックな 気分を表現すべく、ブラームスは『大学祝典序曲』を媒介として『悲劇的序曲』を作曲するに至ったと考えられる。
このように書いてくると、いかにも字面通りに悲劇的で、およそ演奏会の幕開けとしてはふさわしくないのではないかと思われるかもしれないが、実際聞いて みるとそんなことはなく、ブラームスの心情とは裏腹に、この曲には強靭な意志の力が満ちていて、悲劇的とは言いながらも決して涙は見せていない。よって、 「悲劇的」という名を冠するよりは、むしろ彼の書簡にあった「劇的」という言葉の方が的を射ているのかもしれない。曲はソナタ形式に基づき、激しい跳躍で 力強い第1主題、朗々と歌う第2主題が様々に展開していき、結尾ではニ短調の力強い和音で終わる。
最後に、この曲の編成はブラームスにしては大きい方で、ピッコロ、3本のトロンボーン、テューバを含んでいるが、これらの楽器の出番はきわめて限定さ れ、しかもそのほとんどが弱音であり、曲の経過部において神秘的で美しい効果を出す役割を果たしているということを付け加えておきたい。
R. Wagner:《トリスタンとイゾルデ》~前奏曲と愛の死
あらすじ:寡夫の老マルケ王の甥・家臣で国の英雄であるトリスタンは、かつて他国の王女イゾルデの許婚を殺し重傷を負ったが、他ならぬイゾルデに助けら れ、互いに知れず愛し合うようになる。忠義心の厚いトリスタンは、自らの思いをよそにイゾルデこそマルケ王の後妻に相応しいと考え、自ら船で迎えに行く。 イゾルデはトリスタンと共に毒薬を飲んで死のうとするが、侍女が偽って媚薬を飲ませたため、二人は赤裸々に愛し合うようになる。密会の現場をマルケ王と家 臣たちに押さえられ重傷を負ったトリスタンは、故郷に帰るものの息絶え、追ってきたイゾルデもこれに続く。
以上簡単に書いたが、細部での感情や思想により重きが置かれており、内面的な劇と言える。
さて、内面劇と書いた「トリスタン」であるが、音楽的には調性が不明確であることが対応しており、それこそが画期的、かつ音楽的な大事件であるとされる。 つまり、音楽的な自然欲求である和声的解決や主和音が得られず、絶えずそれを求めつつも手が届かない状態が作られている。ワーグナー得意の無限旋律や半音 階進行も多用される。こういった手法を用いることで、「愛」といった明確に定義しにくい複雑な感情や、相反的な要素(「本音と建て前」「可愛さ余って憎さ 百倍」など)を内包した曖昧・微妙な感情をも表現している。結果的に、従来のオペラにありがちな「善玉」「悪玉」の二元論的なシンプルさとは全く異なるも のとなっている。
ちなみにワーグナー自身もこの作品には相当の自信があったようで、「驚くべき作品になる(第1幕作曲中)」「私の今までの芸術の最高峰(第2幕作曲終了 時)」「お前は悪魔の申し子だ!(第3幕作曲中)」「トリスタンは今もって私には奇跡だ(作曲後)」などと述べたそうである。作品成立の背景には、ドレス デン革命での指名手配中といった状況、ライフワークの「ニーベルングの指環」における行き詰まり、妻ミンナとの不仲、そしてなによりも、彼に隠れ家を提供 した恩人ヴェーゼンドンクの夫人マチルデとの「愛の耽溺」と、ショーペンハウアーの「生命への意志の究極の否定」といった思想への接近があった。
「前奏曲と愛の死」は、全3幕の最初と最後を接続したもので、本来「愛の死」にはイゾルデの独唱が入る。短いながらまさに全曲のエッセンスといえる曲である。
前奏曲:劇中の特に主要な動機で構成されている。冒頭のチェロ、続いて木管が有名な「トリスタン動機」を出す。ffまで到達した後、チェロに2つの「愛の 動機」が順に現れ、不吉な「運命の動機」がこれに絡む。以後これらの動機で展開し、「法悦の動機」も入って最高潮に達し、爆発した後、やや憂鬱なまま冒頭 の雰囲気へと戻っていく。
愛の死:冒頭、バス・クラリネットで出る「愛の死の動機」が次々に転調し、「愛の浄化の動機」も加わって恍惚と盛り上がる。楽劇中の密会時には阻まれた頂 点をようやく得て、イゾルデは「世界の息の通う万有の中に/溺れ、沈んで/意識なき至高の悦び」の中に息絶える。ワーグナーはこの曲を「隔てなき永遠の不 安なき合一」であると言っている。
ベートーヴェン 交響曲第7番 イ長調 作品92
この曲が作られたのは、1811~12年。
1812年は、それまで破竹の勢いで勢力を拡大してきたナポレオンが、ロシアで初めて敗退し、フランス革命から続いてきた革新の時代が終わり、新しい時代へと歴史が回転し始めた年。
音楽の世界でも、歴史が回転しつつあった。古典派を代表してきたハイドンは3年前に亡くなり、サリエリなども62歳となった一方で、新時代のロマン派を になう人々は、シューベルトがかろうじて15歳、あとはメンデルスゾーンが3歳、シューマンが2歳という幼児であり、まさに"はざ間の時代"だった。
■1812年当時の年齢
- ハイドン(1809年没)
- サリエリ 62歳
- ベートーヴェン 42歳
- シューベルト 15歳
- ベルリオーズ 9歳
- J.シュトラウス(父) 8歳
- メンデルスゾーン 3歳
- シューマン 2歳
- ショパン 2歳
- リスト 1歳
- ワーグナー(1813年生まれ)
- ヴェルディ(1813年生まれ)
そんな中、ベートーヴェンは42歳。人生的にはともかく、音楽的にはまさに脂ののった時期で、それまでの古典派の音楽を自分のものとし、次の時代への準 備をしていた。ベートーヴェンの作品を通して見たとき、1810年頃から1816年頃までが中期から後期への移行期間とされており、この頃から作品の中に 哲学的なものを含んでいるようなものが増えていく。
■1810~16年の主な作品
- 交響曲第7番 1811~12年
- 交響曲第8番 1811~12年
- 弦楽四重奏曲第11番「セリオーソ」 1810年
- ピアノ三重奏曲第7番「大公」 1811年
- チェロソナタ第4番 1815年
- チェロソナタ第5番 1815年
- ピアノソナタ第27番 1814年
- ピアノソナタ第28番 1815~16年
そうした期間の作品の中では、この交響曲第7番は、とても勢いのある曲で、より中期に近い"華やかさ"を感じられる作品だ。音程・リズム・強弱を3大要素としたとき、そのうちのリズムが特に強調されており、とても躍動感のあるイキイキとした交響曲になっている。
第1楽章は、繰り返し現れる上行音型が印象的な序奏部を経て、8分の6拍子の主題に入っていく。ここからは「ターンタタン」というリズムが、常に現れ る。ソナタ形式だが、第1主題も第2主題も同じように「ターンタタン」というリズムを基本にしているので、第2主題の始まりには気付かないかもしれない。 聞いているうちに「ターンタタン」というリズムが身体に染み付いて、この楽章が終わっても、頭の中で鳴り続けてしまいそうだ。
第2楽章は、短調と長調の入れ替わりがとても印象的。短調部分は縦のリズムが、長調部分は横のメロディが大事にされているので、両者の違いがさらに浮き立ってくる。
第3楽章は、出だしから飛び跳ねるようにして進んでいく。第2楽章のイ短調に対して、ヘ長調であるというのも鮮烈な印象を与えてくれる。
第4楽章は、アレグロ・コン・ブリオ。すさまじい数のfやsfが書き込まれていて、ベートーヴェンの情熱が伝わってくるようだ。調性もイ長調に戻り、今 までの第1~3楽章をがっちりと受け止めて、この終楽章のための第1~3楽章だったのか、という勢いで感動的な終焉を迎える。
ディーリアス 間奏曲「楽園への道」~歌劇「村のロメオとジュリエット」より
幼なじみの年若い二人が、山中の酒場「楽園」を目指して山道を登っていく。醜い諍いの果てに零落していく両家の陰でひっそりと芽生えた恋を携えて・・。
歌劇「村のロミオとジュリエット」の英国初演に際し、ディーリアスがこの美しい間奏曲を書き加えたのは1910年のことであった。指揮にあたったトーマ ス・ビーチャム卿はこの曲をことさら愛し、作曲家の死後二管編成に縮小編曲して本日のような管弦楽演奏会でたびたび取り上げている。(ちなみに歌劇は、世 をはかなみ「楽園」を後にした二人が川舟に乗り、常世の国へ旅立つ場面で幕を閉じる。)
ヴィクトリア朝の英国で富裕な商家に生まれたフレデリック・ディーリアスは、若き遊蕩遍歴の日々ののちアールヌーボーのパリに漂着し、やがて画家で聡明 な妻を得てからは、その半生を郊外の美しい水辺の村グレで作曲の日々に暮らした。形式的常套手段を嫌い、常に自身が感じ取ったものを優先させ、それでもな お彼のスコアのもつ美しさは、往時の音楽学生モーリス・ラヴェルにヴォーカル譜作成を引き受けさせるほどであったという。
ディーリアスをなぜ好きか。この問いに私は当惑する。彼の作品にはしばしば、耳の官能を満たす甘美な旋律が見られず、特徴ある音型が意志の力により展開 しつくされることもなく、また理知的な導き手となるソナタ形式のような楽式も見当たらないからである。私たちは淡い彩色を施された絵画をのぞき込むように その音楽に立ち会うことになる。そこに見出されるものはうつろいゆく季節や風物の美しさと残酷さ、そしてそれらに感応する力を享けてしまった人間への ディーリアスの深く柔らかな眼差しである。 Man is a mystery; Nature alone is eternally renewing.(人間のことは分からない。ただ自然だけは永遠にめぐり続ける。) とは、その思想の最も深い意味合いにおいてフリードリヒ・ニーチェを敬愛した彼の生前の口癖であった。
過去に当団でディーリアスの最晩年の作品を取り上げたシーズンでのこと。初めての練習が終わって周囲がさざめき始める中、あるオーボエ奏者がかすかな声 で「ほんとうに美しい音楽だ…」とつぶやいた夕刻の情景を、私は今も幸せな気持ちで思い出す。時が流れ、彼をその席に見ることはなくなったが、そんな小さ な記憶とともに皆と再びディーリアスで演奏会を始められる今を、私はやはり幸せに思う。
ラヴェル バレエ音楽「マ・メール・ロワ」全曲
例えば〝優しい音楽〟とは、と訊かれたら、誰の曲を思い浮かべるだろう。シューベルト? サティ? 少なくともラヴェルを真っ先に挙げる人は多くはなさそうだ。
しかし、モーリス・ラヴェル(1875-1937)の晩年の弟子・友人であったロザンタールはこう語っている。「ラヴェルのあらゆる音楽には、どんな時 期に書かれたものであろうと、心地よい、無垢な優しさの輝きを見出すことができる」 本当に全部の作品(『スペイン狂詩曲』や『ラ・ヴァルス』や…)が 〝優しい〟のか……、それは分からないが、しかし『マ・メール・ロワ』ならば、多くの人の耳に優しさをもたらしてくれるのではなかろうか。
「マ・メール・ロワ Ma Mere l'Oye」とはフランス語で「がちょうおばさん」、英語でいうところの「マザー・グース」である。つまりは童謡集だ。ご存知のように、原曲は4手のピア ノのための5つの小品を集めたシンプルなものである。無類の子供好きだったラヴェルは、この曲を友人の子2人のために作った。難しい奏法を極力避け、オク ターヴでさえも用いていない。子供たちへと向けられた心の優しさが、ラヴェルにこの曲を書かせたといってよい。童話の一頁一頁をめくるように、一曲一曲、 一音一音が丁寧に作られている。この曲はラヴェルが、演奏する子供たち自身に語り伝えた優しいお伽話なのだ。
オーケストラ版は原曲の2年後にバレエ音楽として作られた。現在では、もともと在った5曲のみを演奏する「組曲」版と、曲を6つに増やし(順序も少し入れ替わる)前奏曲と4つの間奏曲をも加えた「全曲」版(本日のバレエ版)の両方が演奏されている。
ラヴェルのオーケストレーションは神業のように美しく完璧である。彼はモチーフの多くを他の作曲家から拝借しているが、出来上がった作品、独特の響き は、ラヴェルその人のものである。彼は「聴衆を惑わす」ことがオーケストレーションだと語る。例えば〈眠りの森の美女のパヴァーヌ〉の冒頭。フルートがメ ロディーを奏でる裏で静かにホルンが対旋律を歌う。これだけでも十分に美しいのだが、ラヴェルはさらに、ホルンの音の中にヴィオラのピチカートを「密か に」加える。するとホルンとは少し違った音色が聞こえてくるわけだが、聴き手にはすぐにヴィオラだとは分からない、という仕組みである。極めて薄い作りで 進められていく『マ・メール・ロワ』だが、実はこのような繊細な技巧がたくさん散りばめられている。だからこそ、シンプルなのにこんなにも優しく魅惑的な 彼の音楽に、私達は引き込まれてしまうのだろう。
眠りの森の美女のパヴァーヌ

余談であるが、ラヴェルは、シューマンが、ほとんど白い鍵盤しか使わずにあんなにも人間味のある表現ができたことに、大きな感動を覚えていた。音楽は違えどもそこに共通するある種の〝優しさ〟に、今日は耳を傾けていただけたらと思う。
〈前奏曲〉神秘的な夜明け。遠くから信号ラッパ (ホルン)。後に出てくるモチーフが順に奏されてから曲は一気に高まりを見せ、幕が開ける。
〈紡ぎ車の踊りと情景〉バレエ版のために挿入された曲。『眠りの森の美女』の前半部分である。意地悪な仙女の呪いにより、糸を紡いでいた王女が指に怪我をするシーン。最後のオーボエのカンタービレで王女は気を失い、百年の永い眠りにつく。
〈眠りの森の美女のパヴァーヌ〉イ短調自然音階(エオリア旋法)。簡素で美しい曲。
〈間奏曲〉2人の黒人の子供。王女の眠りを小話で慰めるよう命じられ、劇中劇が始まる。
〈美女と野獣の対話〉まずはワルツによる美女のテーマ(クラリネット)。おどろおどろしい雰囲気に変わり、野獣の登場(コントラファゴット)。曲の後半で は両者が絡み合い、曲の最高潮で野獣は倒れるが、ハープのグリッサンドで野獣は王子に変身する。コクトーの映画を髣髴とさせるような、激的ながらも静かで 端正な音楽。スコアの冒頭には、美女と野獣との会話が書き込まれている。
〈間奏曲〉再び黒人の子供。次の物語への予感。
〈親指小僧〉7人の子供たちが道に迷う物語。末っ子の親指小僧が道しるべにパンを撒いていくが、鳥たちに食べられてしまう。ゆっくりとした変拍子が子供た ちの不安を表す。途中にヴァイオリン、フルート、ピッコロによる小鳥やカッコウの鳴き声も聞こえる。唯一フォルティシモになる箇所は、全曲を通して最も美 しいシーンの一つである。
〈間奏曲〉ハープ、チェレスタ、フルートのカデンツァ。全曲版ならではの聴き所。
〈パゴダの女王リドロネット〉「パゴダ」とは中国の首振り人形。女王がお風呂に入ると、人形達が楽器を弾きながら歌い始める。途中、銅鑼とともに女王の登 場。ここから曲はいっそうの異国情緒を漂わせる。女王も一緒になって踊り、賑やかに曲は終わる。スコアには、元になった『緑の蛇』という童話からの引用が 書かれている。
〈間奏曲〉冒頭の、夜明けの音楽の再現。
〈妖精の園〉森が優しく目覚め始める。王子の登場。音楽が静かに頂点に達したところで夜が明ける。それに続くソロヴァイオリンとチェレスタは王女が目を覚ます姿を表している。最後にはこれまでの全ての登場人物が集まって、輝かしいフィナーレとなる。
シューマン 交響曲第1番「春」 変ロ長調 作品38
1840年、シューマン30歳。この年、シューマンは大きな転機を迎えた。長らく果たせずにいたクララとの結婚が実現したのである。それは、クララの父親 の強硬な反対(妨害)に遭い、裁判にまで持ち込んで、ようやく達成された結婚であった。この結婚の4ヶ月後に、この交響曲第1番「春」は作られた。作成に 要した期間はわずか4日間。ほとんど寝ずに一気に書き上げられたと言われている。
この曲はシューマン自身によって「春の交響曲」と呼ばれ、当初は楽章ごとに「春のはじめ」「黄昏」「楽しい遊び」「春たけなわ」という標題が付けられてい た(出版の段階で削除された)。たしかに、この曲では、随所に、春らしい躍動感と喜びを見出すことができる。冒頭で高らかに鳴り渡るトランペットのファン ファーレは春の訪れを告げているようだし、それに続く序奏は、雪が溶け、木々の芽が芽吹き、花のつぼみが膨らみ、風と陽光が柔らかくなっていく、早春の雰 囲気を表しているようだ。そして、主部は圧倒的な喜びの賛歌。そのうれしそうなことといったら、少し病的な躁状態?と思ってしまうほどである。それに続く 2楽章の優しい詩情に満ちた雰囲気、3楽章の力強さとコケッティッシュさ、4楽章の蝶が戯れているような旋律と悪魔が踊っているような旋律(『クライスレ リアーナ』第8曲の旋律)の交錯……それぞれ、どれも印象的である。しかし、最も印象的なのは、全楽章を通じて見られる、前へ前へと進む駆動力の強さ、テ ンションの高さ、ではないかと思う。執拗に繰り返される付点のリズム、不自然なアクセントなどは、この駆動力やテンションを強めているようだ。ここでの 「春」は、「春眠、暁を覚えず」「ひねもすのたりのたりかな」「ぼあーんぼあーんと桃の花見ゆ」といった、のどかな、そして、そこはかとない憂いを秘めた 日本の「春」とはだいぶ違う。もっと色彩が鮮やかで、陽光の強い「春」である。
さて、この「交響曲」が作られた重要な背景としては、1839年に発見・初演されたシューベルトの交響曲第9番の影響が挙げられるだろう。確かにシューベ ルトの交響曲第9番「グレート」と、この交響曲第1番「春」は、冒頭の金管の旋律、序奏、主部の雰囲気など、類似点が多い。一方、「春」のインスピレー ション源としては、アドルフ・ベッドガーの「汝、雲の霊よ」という詩が挙げられる。ただし、注意すべきは、ベッドガーの詩が、決して「春らんまん」の詩で はないということである。それは、暗い冬の情景を描いた詩であり、春の描写があるのは、最後の2行だけ、唐突ともいえるかたちで出てくる「おお、変えよ、 おんみの巡りを変えよ ―谷間には春が萌え出ている!」という詩句だけである。1840年に、ゲーテ、ハイネ、リュッケルト、といった詩人の詩に曲を付けて、140曲もの歌曲を 作曲しているように、シューマンは詩に関して非常に深い造詣を持っていた。そのシューマンが、あえて、この無名詩人の詩に強く惹かれたのは、なぜなのだろ うか。
1810年、シューマンは5人兄弟の末っ子として生まれ、家族や近隣の人にかわいがられ、幸せな幼年時代を過ごした。しかし、10代半ばから次々と不幸な 事件に襲われる。16歳のときに姉エミリーリエが自殺。その10ヶ月後に父アウグストが急死。シューマンは激しいショックを受け、この年に最初の精神発作 を起こす。それからは続けざまである。22歳…右手の第三指麻痺(ピアニスト断念)。33歳…兄ユリウスと義姉ロザリエの死、最初の自殺未遂。34歳…親 友シュンケの死。36歳…母ヨハンナの死。38歳…兄エデュアルドの死。このような、たびかさなる肉親の死を経て、シューマンは、病気(例えばコレラ)や 死(例えば自分の自殺)に対して強い恐怖を抱くようになったと言われている。日記や手紙には「これまでお金を使うことぐらいしかしていないのに、今20歳 で死ぬのかと思うと気が狂いそうになります(1831)」「頭への血の逆流、言い表せないほどの神経過敏、息切れ、突然の失神に見舞われます (1833)」「僕はどうなっていくのだろう、死ぬほどのつらさに笑い出したいくらいです(1837)」といった記述も見られる。
そのような精神状態のなか、シューマンは常に依存と愛着の対象を探し、さまよった。とくに恋人には、精神的な支えだけではなく、経済的な支えも求めたよう だ。シューマンは、クララの前に婚約していたエルネスティーネと1836年に婚約を破棄しているが、その理由について、次のように書き送っている。「今こ そ言ってしまうが、医者は優しく慰めて、結婚が唯一の治療法だから結婚したまえ、と勧めたのだ。当時、君(クララ)はまだ子どもから娘への成長期だったの で、僕の眼中にはなかった。ちょうどその時エルネスティーネが現れたのだ。とてもいい娘だった。僕は全力で彼女にしがみつこうとした。だが僕は彼女が貧し いことを知った。僕自身どんなに頑張っても稼ぎが少ないとなると、先行きどうしようもないことが分かった。君は僕を非難するだろうが、僕はそんなことで、 だんだん気持ちが醒めてしまったのだ。エルネスティーネは一文も稼げなかった。僕は母と相談して、彼女と結婚すれば苦労ばかりが増えるだろうということで 意見が一致したのだ(1838)」。このような手紙を悪びれずに書き送るシューマンもすごいし、読んで愛想をつかさないクララもすごい。クララはシューマ ンより9歳年下であったが、すでに一流のピアニストであり、稼ぎもシューマンの比較にならないほど多かった。シューマンがクララに宛てた手紙には「君はす べてにおいて僕より優っている(1838)」「君は最高の尊敬にふさわしい素晴らしい少女だ(1839)」「英雄的な少女はその恋人をも英雄的にします (1839)」という記述もあり、シューマンにとってクララは、年下のかわいい恋人という以上に、経済的にも精神的にも自分を支えてくれる、非常に大きな 存在であったと思われる。
1835年、シューマンとクララは互いを恋人と認識するようになるが、クララの父親はこれに猛反対し、1840年、裁判所で判決が下されるまでの5年間、 常に激しい妨害を続けた。これはシューマンにとって非常なストレスであった。加えて、この頃、クララのピアニストとしての活躍は目覚ましく、演奏旅行で各 地を飛び回るクララに対して、シューマンは焦燥感を募らせている。この時期には「クララはお前のものだ ―お前のものなのだと、僕は思いました。それなのに彼女のところに行って手を握ることもできないのです(1837)」「これが最後になるかもしれません (1837)」「君の婚約の記事を新聞で見ることを想像しました ―床に身体を打ちつけて声をあげて叫びました(1838)」というような不安や焦燥を吐露した手紙が非常に多い。
シューマンにとって、クララはまさに「春」だったのだろう。ベッドガーの詩のラストで詠われる、寒くて暗い冬に終わりを告げる「春」だったのだろう。この 曲には、長い不安の時代を抜けて、ようやく「春」を得ることができたシューマンの喜びが満ちている。この13年後にライン川に身を投げ、その2年後に精神 病院で生涯を閉じるシューマンの、最も幸せだった時期の「春」を、今日、皆様と共有することができれば、幸いである。
モーツァルト 歌劇「魔笛」序曲 変ホ長調 K.620
この歌劇『魔笛』序曲が作曲されたのは、W.A.モーツァルトが死去するまさにその年、1791年のことであった。
初演間近にかろうじて脱稿した頃には病魔が体の深部へ達しており、モーツァルトは常に自らの死を意識しつつ作曲を推し進めていったに違いない。そのため、この曲は彼の遺書であると考えるむきも少なくない。
話はさかのぼるが、モーツァルトは1784年に大きな転機を迎えていた。かねてから強い関心を示していた秘密結社フリーメイソンへの入団を許されたので ある。晩年のモーツァルトを精神的に支えたのはその理念であり、物質的に支えたのはそこで交わる仲間達であったわけだ。そのため、この遺書としての性格が 強い『魔笛』にはフリーメイソンの理念・象徴体系がそこかしこに現れてくるだけでなく、あらすじも、主人公タミーノがその参入儀礼を乗り越えてゆく過程の 話だと考えて差し支えない。
それでは、そもそもフリーメイソンの目指す理念とは一体何なのか。それは、徳を備えた個人としての人間の完成、そして人種や国家の枠にとらわれず、「自 由・平等・博愛」の精神を持った人々による人類共同体の形成、この2点に集約される。序曲でこの理念が明瞭に反映されているのは、冒頭と中間部に出てくる 「3回の和音」であろう。参入儀礼が「3回のノック」を合図にして始まることからも分かるように、この「3」という数字はフリーメイソンの象徴体系の中で も特別な地位を占めており、歌劇全体を通してこの数字を探し出すのは容易なのだ(序曲の調性もフラット「3」つの変ホ長調!)。そのため、冒頭からフリー メイソンの理念を堂々と披露してみせるモーツァルトの意気込みたるや、もう感嘆を覚えずにはおれない。この「3回の和音」は、モーツァルトがいかにフリー メイソンの理念にコミットしていたかを雄弁に物語っているのである。
以上、モーツァルトとフリーメイソンの関係から曲を見てきたが、この序曲、そんな小難しいことを考えなくても音楽自体が十分に素晴らしい。形式は序奏付 きのソナタ形式で、主部と展開部に見られるフーガ、木管楽器によるデュオなど聴き所・見所満載であり、演奏会の幕明けにこれほどふさわしい曲は少ないであ ろう。
モーツァルト オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314
木管楽器を独奏としたモーツァルトの協奏曲は、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットと、どれも珠玉の名曲ばかりですが、中でもオーボエ協奏曲 といえばモーツァルト、と言っても過言ではないくらい、モーツァルトのオーボエ協奏曲はオーボエの曲の中の名曲中の名曲です。
このオーボエ協奏曲は、1778年、マンハイムで作曲されたと言われていますが、この曲をモーツァルト自身が音程を2度上げてフルート用に編曲し、フルート協奏曲第2番ニ長調となったことでも有名です。
また、このオーボエ協奏曲の第3楽章のテーマのメロディは、1781年に作曲されたオペラ「後宮からの誘拐」(K.384)の第2幕の最初のアリアにも再び利用されています。
第1楽章は、大変さわやかで軽やかな曲で、華やかなサロンに良く似合う曲です。ソロとオーケストラが絶妙に絡み合っていて、緊張感を保ちながら音楽が展開していきます。
第2楽章は、豊かなオーケストラの序奏の後に、秋の空のように青く澄みきった素晴らしいメロディをオーボエソロが奏でます。
第3楽章はロンド形式で、同じテーマが最初を含めて4回でてきますが、さすがはモーツァルト、4回同じことはさせません。それぞれに子どものいたずらのように微妙な細工が施されていますので、是非耳を傾けてみてください。
さて今回は、本日の演奏会の指揮者である古部賢一氏をオーボエ独奏としてお迎えし、独奏をしながらオーケストラの指揮もする、いわゆる「吹き振り」の形をとっております。
とは言っても、独奏者が指揮をする、というよりもむしろ、ソロオーボエを中心に室内楽的な雰囲気が出せればと思っております。何はともあれ、魅惑の古部ワールドを存分にお楽しみください。
ベートーヴェン 交響曲第5番「運命」
ドイツ古典~ロマン派をメイン・レパートリーとするブルーメンだが、その保守本流ともいえるベートーヴェンの奇数番号交響曲への挑戦はこれがはじめてである。
ジャジャジャジャーン、と活字にしただけで連想されてしまうこのハ短調交響曲は、いわゆるクラシックに分類されるすべての曲の中で最も有名なのではないだ ろうか。日々の生活でも時折耳にするこの「・タタタ/ター」というモチーフは、もはや「運命」という言葉の代名詞になってしまった感がある。それは現代に 限ったことではなく、かつてメンデルスゾーンは結婚行進曲(「真夏の夜の夢」)に、マーラーは葬送行進曲(第五交響曲冒頭)にこれを用いているが、対極に 位置する「結婚」と「死」に共通のモチーフが扱われていることは興味深い。
この交響曲の最初のスケッチは今からちょうど200年前、1803年(第三交響曲の完成間近)にはじめられていた。初演は1808年、第六交響曲「田園」と同時に、作曲者自身の指揮で行われている。
「なんてやかましい曲だ。天井が落ちてきそうだ!」
文豪ゲーテはこう評したというが、当時の人々がこの曲をどう受け止めたか良くわかる。それまでの交響曲は形式にのっとった音楽の中に「美しさ」を求め る、ともすればイージーリスニング的なものが多かったのだが(例外はもちろんある)、ベートーヴェンはこれに人々の心に訴えかける感情(熱情?)を盛り込 むことに成功した。それはよく「苦悩/闘争から歓喜/勝利へ」などとされ、この曲の成功を受けて彼に続く多くの作曲家に模倣された効果的なプログラムであ るが、当時の聴衆の期待―適度に心地よいフレーズが流れる社交の場としての音楽会―には大いに反するものだったのだろう。
この曲は様式的にも革新性に溢れている。冒頭の1つの休符と4つの音符からなる、いわゆる「運命のモチーフ」によって曲全体が有機的に統一されており、 ベートーヴェンの作品中各楽章が最も緊密な構成をもっているものといえる。また、短調に始まり長調に終わるという楽章構成は交響曲史上はじめての試みだ が、切れ目なく演奏される3・4楽章の移行部は特に劇的な効果をもたらしている。さらに終楽章ではこれまで交響曲には用いられてこなかった新しい楽器を新 たに取り入れている。すなわちピッコロで高音を、コントラファゴットで低音を補強することにより管楽器の音域を上下に拡大し、宗教的な楽器であったトロン ボーンまで持ち出して(無茶な使い方ではあるが!)荘重な響きを作り出している。
第1楽章 アレグロ・コン・ブリオ ハ短調 4分の2拍子
フォルティシモによる衝撃的な開始(弦5部とクラリネットによる)はあまりにも有名であり、このテーマが徹頭徹尾追求される。畳み掛けるような緊張感の中、オーボエによる一瞬のカデンツァが実に印象深い。
第2楽章 アンダンテ・コン・モート 変イ長調 8分の3拍子
ヴィオラとチェロによるテーマに先導される、やすらぎに満ちた変奏曲。金管によるハ長調のファンファーレを第二主題とみればソナタ形式ともいえる。
第3楽章 スケルツォ アレグロ ハ短調 4分の3拍子
不安感を漂わせる低弦と木管の掛け合いにホルンの悲痛な叫び(運命のモチーフ)が続く。トリオは低弦から高弦へのフガート形式。再現部は徐々に弱々しくなり、心臓の鼓動のようなティンパニを伴った弦に導かれて終楽章へのブリッジ(橋掛け)へと続く。
第4楽章 アレグロ ハ長調 4分の4拍子
溜まりに溜まったエネルギーを一気に放出するかのような、歓喜/勝利と評されるファンファーレによって幕が開く。途中スケルツォの回想を挟み、再現部で気分は一層高揚する。コーダ(プレスト)ではハ長調の和音がこれでもかと続き、壮大な大団円を迎える。
この曲は日本では昔から非常に人気のある曲で、演奏会でも数多く取り上げられ、何十種類ものレコード・CDが発売されてきた。有名すぎるがためか、はたま たより大編成の派手な曲を聴衆が好んだためか、プロのオーケストラでは定期公演以外の「名曲コンサート」などで演奏される程度になってしまった時期もあっ た。一方学生オーケストラなどのアマチュアではアンサンブルを学ぶための格好の教材として盛んに取り上げられており、数回の演奏経験をもつ者も決して珍し くない。しかし、この曲の偉大さは通俗名曲として片付けられるものではなく、演奏するたびに発見があり、特に終楽章ではその都度新鮮な解放感を味わうこと ができる(疲労も相当なものだけれど)。本日はこの曲をこのメンバーで演奏できる、という喜びを皆様にお伝えできれば幸いである。
スッペ:「軽騎兵」序曲
スッペは1819年アドリア海に臨むダルマティア地方の港町スパラート(現在クロアチアのスプリト、2002年のウィンブルドンの優勝者ゴラン・イワニセビッチはこの町の出身)に生まれた。
幼い頃から音楽の才能を発揮し、13歳でミサ曲を作曲した。
一時イタリアのパドヴァで法律を学んだが、その間にもイタリアのオペラに触れ、ミラノに赴き作曲家のロッシーニやドニゼッティ、ヴェルディとも親交を結んだ。
オーストリアの官吏だった父が1835年に亡くなると母の故郷ウィーンに移り、この頃から本格的に音楽家を志した。
スッペは1860年にウィーンにやってきたオッフェンバックに触発され、最初のウィーン風オペレッタを作曲したため、「ウィンナ・オペレッタの父」と讃えられている。
しかしながら1840年、21歳の時に初めて得た職は、ヨーゼフシュタット劇場の第三楽長で、始め無給であったばかりか、指揮者として地方の劇場を回り、また時には歌手として舞台にも上る極めて多忙なものだった。
作曲家としての活動も多忙を極め、5日に1本ともいわれるハイペースで作曲を重ねたが、作品は大衆に広く受け入れられ、当世の人気作曲家となった。
「軽騎兵」は1866年に作曲され、アン・デア・ウィーン劇場で初演された。普墺戦争前夜という時局に乗ったのかどうか定かではないが、この二幕のオペレッタは大いに成功を収めた。
本日演奏する序曲は、大きく分けて5つの部分から成る。冒頭、非常によく知られたファンファーレをトランペットが奏し堂々とした序奏を開始する。
次いで、騎兵の疾走かあるいは剣劇を思わせるようなスリリングなアレグロから、軽快な行進曲へ、それがいったん落ち着くと、ハンガリー風の荘重なメロディーが現れる。最後に一転、行進曲が再現し、華やかな総奏のうちに結尾を迎える。
これに続く本編は現在演奏されることもなくストーリーも忘れられてしまったのだが軍隊をテーマにしたこの作品は色恋沙汰の多いオペレッタの中で一風変わったものだったろう。
参考までに―軽騎兵とは、重装備の歩兵や装甲した騎兵と違い、快速を武器に独立して行動し、偵察や奇襲に威力を発揮した兵科で、第一次大戦以降、飛行機や 軽車輌にとってかわられた。現在では、ウィーンの旧王宮内でのスペイン馬術のデモンストレーションにその姿の名残りを見ることができる。
チャイコフスキー:「くるみ割り人形」組曲
「眠りの森の美女」「白鳥の湖」と並ぶチャイコフスキー3大バレエ曲の最後となるこの曲は、ドイツの文豪ホフマンの「くるみ割り人形とねずみの王様」を原 作とするバレエ曲で1891年から1892年にかけて作曲され、1892年マリインスキー劇場で初演された。尚、バレエ化の際にはホフマンの原作ではな く、内容が簡略化され、よりメルヘンチックにデュマが翻訳したフランス語版を元にしている。
この組曲に含まれる曲は花のワルツを始めとして、いずれも有名な曲であり、CM等で耳に馴染みのある曲も多いだろう。この組曲に含まれる曲のみならず、全 曲に渡って、稀有のメロディストとしての彼の才能が発揮されたロマンチックな、叙情的な曲が散りばめられた名曲だ。実際、くるみ割り人形はバレエとしての 魅力は少々欠けており、その人気はチャイコフスキーの音楽に依るところが大きいという意見も多いようだ。また、この組曲しか知らない者に聞くと、ややもす ると「かわいらしいメルヘンチックな子ども向けの曲」と揶揄されることも多いが、実際のバレエの舞台に接すればその印象は一変することだろう。クリスマス の夜の物語ということで、日本でもクリスマスが近づくと国内外多くのバレエ団の上演が行われる。第九を聴くのも良いが、ぜひ一度実際のバレエでくるみ割り 人形の魅力に触れて頂きたい。
簡単にバレエのあらすじを紹介しよう。
さあバレエが始まる。ステージの幕はまだ降りたままだ。客席の灯が落ち、周りのざわめきも静かになる。暗闇の中、オーケストラピットから華麗な序曲が奏でられる(「Ⅰ.小序曲」)。軽やかなメロディーが流れ始めた瞬間から、これから始まる物語の世界に引き込まれるだろう。
あるクリスマスの夜、ドイツ、ニュルンベルグのシュタールバウム家ではクリスマス・パーティーが開かれる。娘のクララもたくさんのお客様を迎えてのパー ティーやクリスマスプレゼントを楽しみにしている。パーティーが始まり皆はダンスを踊ったりして楽しむ。子供達もダンスを踊る(「Ⅱ.行進曲」)。クララ の名付け親でもあるちょっと変わり者のドロッセルマイヤーは人形劇を観せたり、プレゼントを配ったりして、子供達も大喜び。そのプレゼントの中にくるみ割 り人形があったのだが、それはいかつく、不恰好で子供達は皆嫌がる。しかし、クララだけはそれを一目で気に入り貰うが、弟のフリッツが壊してしまう。やが てパーティーも終わり皆帰途に着く。クララは壊れたくるみ割り人形を不憫に思い、抱いたまま眠ってしまう。
気がつくと居間の時計が12時を告げる。するとどこからか不気味なねずみの大群が現れた。部屋の人形達も動き出し、くるみ割り人形に率いられ、ねずみ達と 戦う。くるみ割り人形とねずみの王様の一騎打ちとなるが、勇敢なクララの助けのおかげで、くるみ割り人形は戦いに勝利する。すると、醜かったくるみ割り人 形は王子様の姿になる。クララの優しさと助けてもらったことに感謝し、くるみ割り人形はクララをお菓子の国へ招待する。
第2幕、お菓子の国の宮殿でクララは、きらびやかな踊りを楽しむ。チョコレート、「Ⅴ.アラビアの踊り」、「Ⅵ.中国の踊り」、「Ⅳ.トレパック」、「Ⅶ.あし笛の踊り」そして「Ⅷ.花のワルツ」、夢のような世界だ。
クララと王子はグラン・パ・ド・ドゥを踊る(「Ⅲ.こんぺい糖の踊り」)。いつしかクララは眠っていた。そう、楽しい夢の旅も終わる時だ。気が付くとクララはくるみ割り人形を大事に抱いたまま寝室にいた。冒険の旅は夢だったのだろうか。
尚、ストーリーは演出によってクララの扱い等異なる。違う演出を見るのもバレエを観る楽しみの1つだ。また、なぜくるみ割り人形が王子様なのだ?と大人気ない疑問を思われる向きにはホフマンの原作を参照頂きたい。
このバレエを彩るチャイコフスキーの音楽は子どもも楽しむことができるものだが、決して「子どものために書いてあげた」曲ではない。それはむしろ、自分達 も昔―いろいろ夢憧れた― 子どもであった大人のための音楽のように感じる。ロマンチックながらも、いや、あまりにロマンチックだからこそ、どこか儚い音楽、そう思わないだろうか? だから、その音楽は大人が聴いても陳腐ではなく、楽しめ、感動できるのだ。
誰しもいつか見た夢の情景、お楽しみください。
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」 (Hr.M.U)
1841年ボヘミア(現在のチェコ)の宿屋兼肉屋の息子として生まれたドヴォルザークは、家業を継がせようとする父親の意志に逆らって音楽学校に進み、 劇場付きの管弦楽団のヴィオラ奏者として活動する傍ら、作曲を続けた。そしてオーストリア政府からの奨学金を5年連続得たことをきっかけに、審査員であっ たブラームスに認められ、以後兄弟のような交流を持つに至った。その後1892年ニューヨークのナショナル音楽院の院長として招かれ、新大陸アメリカに 渡った。そこで書かれたのが、彼の最後の交響曲である「新世界より」である。タイトルになっている「新世界」とは、もちろんアメリカのことである。
初期の曲では、特にワーグナーから、また、中期以降(特に交響曲第6、7番あたり)は親交のあったブラームスからの影響が顕著であったが、この「新世界 より」ではそれらの影響から一歩抜け出し、それまでにないかなり独創的な交響曲となった。今ではオーソドックスな名曲としてすっかり耳慣れたものになって いるが、初演された当時(1893年)は、タイトルのとおり斬新な曲として驚きをもって聴かれたのではないか。
この交響曲の第一の大きな特徴として、アメリカの音楽、特にインディアンや黒人の民謡の影響があげられる(ただし民謡そのものを直接引用はしていな い)。そのメロディは故郷ボヘミアの音楽との親近性を感じさせるものであり、そこにドヴォルザークも大いに共感し、この交響曲に反映させたものと思われ る。ちなみにそのメロディーは、日本人にとっても親しみやすく、どこか懐かしい感じを抱かせるものになっている。各楽章については以下の通り。
*第1楽章 アダージョ――アレグロ・モルト
チェロによる瞑想的な序奏が徐々に盛り上がり、「新世界」の息吹を感じさせるようなホルンの第一主題に突入。この主題は、フルート・ソロによる小結尾主題とともに、他の楽章にも繰り返し姿を見せる。
*第2楽章 ラルゴ
神秘的なコラール(この部分にのみチューバを使用している)に続きゆったりと奏されるイングリッシュ・ホルンの旋律はあまりにも有名。自分も小学校の 頃、下校の音楽「家路」として毎日耳にしていた。楽章後半、だんだんと人数を減らしながら、弦楽器がこの旋律を奏しているところは、本当にしみじみとした 感動を覚える。特にこの部分の最後(113小節目)は、それまでと旋律、和音が少し違っていて、思わず涙がこみ上げてくる。個人的に一番好きなところ。
*第3楽章 スケルツォ:モルト・ヴィヴァーチェ
ボヘミア色の強い、そしてブルックナーをも思わせる無骨な感じのスケルツォ。2つあるうちの一番目のトリオ(中間部)は、速度を少し落とし、フルートと オーボエによって、のどかな、どこか日本的とも思えるような主題が奏される。(練習のときに、この旋律が、「おやつの○~る」のCMの歌に似ている、とい う話が出て、納得!!)
*第4楽章 アレグロ・コン・フォーコ
トランペットとホルンによる有名な行進曲風の第一主題と、クラリネットによる抒情的な第二主題からなる。それまでの各楽章の主題も登場し、全曲を締めくくるにふさわしい壮大なクライマックスを築いている。
ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 Op.56a
変奏曲。「主題に続いてその旋律・和声・リズム・性格などをさまざまな方法で変化させた幾段かを接続して構成した楽曲。独立した楽曲の場合と、ソナタ・交響曲などの一つの楽章をなす場合とがある。(広辞苑 第5版)」
変奏は、最も基本的な作曲技法の一つだが、きわめて奥が深い。「作曲は変奏に始まり変奏に終わる」という言葉があるのかどうか知らないが、あながちウソで はあるまい。一つの主題から、いかに多彩な変化を導き、いかに拡がりと奥行きのある世界を紡ぎ出せるか。バッハの「ゴルトベルク変奏曲」やベートーヴェン の「ディアベリ変奏曲」をはじめ、大作曲家の最大の挑戦が、そこにはある。
ブラームスも、変奏曲を好んで作曲しており、ピアノのための「シューマンの主題による変奏曲」、「ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ」、「パガニーニ の主題による変奏曲」などが知られている。いずれも、他の作曲家の主題を生かしつつ、そこから展開される世界は紛れもなくブラームスのもの。それはこの 「ハイドンの主題による変奏曲」も同じだ。
「ハイドンの主題」は、管楽ディベルティメントHob.II.46(今でも木管五重奏などの形でよく演奏されるが、偽作という説もある)の第2楽章に由来する。「コラール 聖アントーニ」と記され、元は古い賛美歌ではないかともいわれている。
主題は、穏やかで古典的な風格を感じさせる。5+5小節(前半)、8+8+3小節(後半)という、フレーズ構造の「字余り」感が独特。後半に入ってからの和声の翳り、最後に繰り返し鳴らされるB(変ロ)音の鐘のような効果が、印象深い。
変奏は8つ。第一変奏の冒頭から既に、ブラームスのファンタジーが拡がっていく。主題の骨格は何らかの形で維持されているものの、変奏を経るにつれ、テンポの緩急、拍子の変化、長調と短調との移ろいなど、聴く者を飽きさせない。
幽霊のように早足で通り過ぎる第八変奏の後、静かに始まる終曲。低音楽器に現れる5小節の主題が18回も繰り返され、その上に多彩な変奏が展開される。 第4交響曲の第4楽章と同じパッサカリアの形式。最後に至って「聖アントーニのコラール」が徐々に全貌を明らかにしていき、全曲に統一感を与えている。
(なお、この曲には、2台ピアノのための版(作品56b)もある。オケ版(作品56a)とほぼ同一の曲だが、どちらがどちらの編曲という訳でもないらし い。それぞれ、違う世界が聞こえてくるのが不思議。この曲がお好きな方は、是非一度、2台ピアノ版の方も聴いてみてください。)
ブラームス:ドイツレクイエム
『ドイツ・レクイエム』である。<ブラームス・チクルス>シリーズを始めた時から、「いつかはやりたい」と思い続けて来た曲である。その数年来の念願が、 ここに第20回記念演奏会という「時」と、新進気鋭の指揮者・ソリストそして経験豊かな合唱団という「人」を得て、めでたく実現のはこびとなった。御協力 頂いた関係者各位、あたたかいお志をお寄せ下さった方々、そして本日ご来場頂いた皆様に報いることができるよう、団員一同全力を尽くす所存である。ご照覧 頂きたい。
■沿革と音楽性 『ドイツ・レクイエム』は、ブラームスがまだ20代の前半の頃から作り始められながら、35才の時にようやく完成し発表された作品である。完璧主義者の傾向が強かったブラームスには、構想から完成までに何年も要した曲が少なくないが、これはその典型的な例だ。
ブラームスにレクイエムを作らせたのは何か、については緒説あるが、恩師シューマンの悲劇的な死(1856年)に動機を得て構想し、敬愛する母の死 (1865年)を悼む思いに促されて完成をみた…と解釈するのが妥当な様だ。実際、曲の大部分は、1866年から1868年にかけて集中的に書かれてい る。
この曲の成功によって、作曲家ブラームスの名声は決定的なものになった。ドイツでは今日なお、年に何回も演奏され、その度に満員の聴衆を集めるほど親しまれていると聞く。
レクイエムを作るにあたって、ブラームスは通常のラテン語による鎮魂ミサのセットを用いず、ルターが訳したドイツ語の聖書の中から自分で言葉を選び詞を 編んだ。ブラームスが敬虔なプロテスタントだったためでもあろうが、かねてから死と生について深い思索を巡らしていた彼は、それを表現するにあたってお仕 着せのテクストでは到底満足できなかったのだと思う。
こうして己の心に忠実に編んだテクストを、ブラームスは殊のほか大切に音楽にした。例えば聖書に頻出する言葉には、伝統的に(古文における枕詞のよう に)「この言葉にはこういう音形」という約束があるが、ブラームスはこれをふんだんに取り入れている。また、第3曲のフーガは一貫してバスの保続音(オル ゲンプンクト)に支えられているが、これはバロック音楽において確固たる信仰を象徴する表現技法である。
このように古楽の様式によく則ってはいるものの、その音楽性には全く古びたところがなく、紛れもなくロマン派の音楽である。また旋律の傾向は、キリスト 教の宗教音楽としては異色であろう。たとえばフォーレのレクイエムがひたすらに「聖なるもの」への希求を歌い、終には天に昇ってしまうのに対し、この曲は あくまでじっと地に留まっている。特に象徴的な第2曲は、泥濘の中を重い荷を担いで一歩一歩進んでいるかのようですらある(私は初めて聴いた時、とりわけ この部分にしびれた)。
言うなれば、「神」ではなく「人」、「天国」ではなく「人の世」に主眼を置いて書かれた「レクイエム」なのである。それゆえか初演の頃には「信仰心が足り ない」との批判を受けたりもしたそうだが、なればこそこの曲は、キリスト教徒にとどまらずひろく「人間」を惹き付けてやまない。
今回『ドイツ・レクイエム』を演奏するにあたり、私達は付け焼き刃ながら使われているテクストについても学んだ(音楽についてはもちろん?)。その成果 を活かし、ブラームスがテクストと音楽にこめた「思い」を、また私達がそれをどう理解し受け止めたかを、ご来場の皆様に感じとって頂ける演奏ができれば、 これに優る喜びはない。
■曲の構成について
『ドイツ・レクイエム』は、以下の全7曲から成る。
第1曲 合唱 かなりゆっくりと、そして表情をつけて
-ヘ長調、4分の4拍子
第2曲 合唱 ゆるやかに、行進曲風に
-変ロ短調、4分の3拍子
第3曲 バリトン独唱を伴う合唱 アンダンテ・モデラート
-ニ短調、2分の2拍子
第4曲 合唱 適当に運動的に
-変ホ長調、4分の3拍子
第5曲 ソプラノ独唱を伴う合唱 ゆるやかに
-ト長調、4分の4拍子
第6曲 バリトン独唱を伴う合唱 アンダンテ?ヴィヴァーチェ?アレグロ
-ハ短調、4分の4拍子
第7曲 荘重に
-ヘ長調、4分の4拍子
第1曲と第7曲の対応がとりわけ顕著だが、各曲はテクストや音楽的な主題で相互に関連し、全体で-第1曲冒頭の希うような「幸い(Selig)」に始まり、第7曲結尾の噛み締めるような「幸い」で結ばれる-壮大なドラマを形作っている。
前半1-3曲では遺された苦しみを歌い、慰めを希求する。これには第3曲コーダにおいて「ゆるぎなき信仰」という答えが示され、それを承けて第4、5曲 では安らぎが支配する(第5曲はいちばん最後に完成した曲だが、特に母の死を悼んで付け加えられたものと言われている)。
第6曲で曲想は一転して再度「迷い、苦しみ→信仰の勝利」が歌われ、これまでのテーマを総括する。そして第7曲の、すべての悲しみや苦しみが昇華した、静謐な境地に至るのである。
リヒャルト・シュトラウス:メタモルフォーゼン
メタモルフォーゼンは「変容」と訳されるが、その意味するところは「形態を変化させること」である。
完成は、1945年4月12日。
偉大な作曲家シュトラウスが82歳を迎えようとしている時、社会的にはドイツの無条件降伏まであと1ヶ月と迫っていた。
愛したドレスデンは壊滅状態、またミュンヘンとウィーンの国立歌劇場も破壊され、この戦争による破壊に対する深い悲しみを抱きつつ1ヶ月の期間で書き上げられたのである。
スケッチ帳には晩年のゲーテの"温和な諷刺詩集"からの引用が記されている。
「23のソロ弦楽奏者の為の習作」と副題が与えられているように、バイオリン10、ビオラ5、チェロ5、コントラバス3、といわゆる伝統的な弦楽合奏とは異なる編成であり、各奏者は独奏者として動かされる。
シュトラウスは作曲家としてのみならず指揮者としても成功を収めており、この2つの立場が相乗作用をおこし、大編成の管弦楽曲においても各奏者を独奏者として扱うことに秀でていた。
そういった意味では"メタモルフォーゼン"は作曲師シュトラウスのエッセンスとも言えるのではないか。
この曲にはベートーベンとワーグナー、とりわけ"第3交響曲<英雄>"と"トリスタンとイゾルデ"のモチーフが深く刻み込まれている。
最期から9小節目のところには「IM MEMORIAM! 追悼」と書き込まれており、まさにそこからベートーベンの葬送行進曲がコントラバスによって奏でられ、メタモルフォーゼンは終焉を迎える。
ヒンデミット:白鳥を焼く男
なかなか強烈なタイトルだが、決して「白鳥を焼いている男」を描いている曲ではないのでご安心。
この曲にはヒンデミット自身がプログラムノートを記しており、その概略は、「一人の吟遊詩人が楽しい宴にやってきて、遠方の地から携えてきた数々の歌を即興で披露する」というものである。
つまり、ヴィオラソロは吟遊詩人の役割だ。1楽章は、ヴィオラソロの後のトロンボーン、ホルンによる、民謡『山と深い谷の間に』に基づき、2楽章は『小さな菩提樹よ、さぁその葉をふりおとせ』という民謡と(ヴィオラとハープのデュオの後の木管のコラール)、『鶯が垣根の上にとまっている』という民謡(中間部のフガート)から成る。3楽章は、『あなたは白鳥を焼く男ではありませんね?』という踊りの曲による陽気な変奏曲。
Paul Hindemith(1895~1963)は、その音楽がナチスに攻撃され、1939年に米国に亡命した。
『白鳥を焼く男』は、このような彼が受けた政治的迫害に対する抵抗を表している曲とも言われている。(吟遊詩人、すなわちヴィオラは、作曲当時、亡命することを予感していたヒンデミット自身であり、祖国を去る悲しさや、音楽の素晴らしさを謳っている)
音楽を「道徳的、倫理的」と表現し、過度に美しく、甘美になることを警告したヒンデミット。
それゆえ、彼の音楽はどうも「理屈っぽい」と思われがちな気もするが、和声や旋律の力を信じた彼が聴衆に伝えたかった「何か」は、必ずあったはずである。
それを、ヴァイオリンでもチェロでもない(ましてやコントラバスでもない・・)、ヴィオラという楽器を媒体として用いて伝えようとしたことに、彼の魂を感じ取りたい。
そして本日は、そんなヴィオラが持つ魅力を、そしてソリスト須田さんの魅力を、十分に堪能して頂こう。
フォーレ:ペレアスとメリザンド
狩の途中迷い込んだ森の中、謎の美少女メリザンドに出逢った王子ゴローは、彼女を妻とする。
が、メリザンドはゴローの異父弟ペレアスと次第に惹かれ合っていく。
ペレアスは嫉妬に狂ったゴローに殺され、メリザンドもまた、ペレアスの後を追うように、病で命を落とす…
(要約すると身も蓋もないが)この深遠で暗示的なモーリス・メーテルリンク(メーテルランク)の戯曲「ペレアスとメリザンド」を題材として、1900年前後、フォーレ、ドビュッシー、シェーンベルク、シベリウスなどの大作曲家による作品が次々と生み出された。
中でも、同時代のフランスを代表する作曲家、フォーレ(英語版初演のための劇音楽(1898年)とこれを元にした組曲(1901年))とドビュッシー(オペラ(1902年))は、いずれも当時のフランス音楽の空気を反映しつつも、対照的な音楽を創造している。
印象主義的、感覚的なきらめきに溢れたドビュッシー。より古風で簡素、慎ましさと優しさに満ちたフォーレ。
組曲は、「前奏曲」、「糸を紡ぐ女」、「シシリエンヌ」、「メリザンドの死」の4曲からなる。悲劇を暗示しつつ静かに高揚し、寂寥のうちに沈む「前奏曲」。沈鬱な葬送的音楽が次第に悲しみを深め、やがて浄化されていく「メリザンドの死」。
この深遠な両曲に対し、「糸を紡ぐ女」では回転する糸車のような弦楽器を背景にオーボエが、「シシリエンヌ」では涼やかなハープの音色を背景にフルートが、それぞれ控え目でありながら魅力的な旋律を奏でる。
悲劇的な運命のもたらす憂愁、その中での束の間の幸せや喜び、はかない美しさ。そんなフォーレの魅力を味わっていただける演奏にしたいものだ。
ミヨー:屋根の上の牛
バレエ音楽「屋根の上の牡牛」は、ダリウス・ミヨーの「六人組」へのリオ土産とも言うべき作品である。
ミヨーは1917年に友人ポール・クローデルがフランス大使としてブラジルに赴任した際、秘書官として同行し、リオ・デ・ジャネイロに2年間滞在した。
このブラジル滞在はミヨーに多くの刺激を与えたが、特に彼が魅了されたのは街角やカーニヴァルで聴かれる音楽であった。
1918年パリに帰ったミヨーはブラジルの民謡やタンゴ、サンバ、マシーシェをひとつの曲に作曲し、当時のブラジルの流行歌の題名を採り『屋根の上の牡牛』と名付けた。
ミヨーは「六人組」の一員として知られているが、この曲は「六人組」の舵取り役ジャン・コクトーとの最初の共同作業となった。
ミヨーはこの曲をチャップリンの無声映画の伴奏に使えたらと考えていた。
しかしこれを聴いたコクトーは劇場的エンターテイメントに仕立てる事を提案したのだ。
その舞台は現在では当時の写真や証言から想像するしかないのだが、道化役者、軽業師が共演したということから普通に思い浮かべるバレーとはかなり違うものだったろう。
初演は1920年2月21日で3日間の興業は大成功を納めた。
5か月後にはロンドンで2週間に渡って再演され非常な話題になった。
このロンドン滞在中にミヨーはジャズに出合い『世界の創造』という傑作を残すことになるのだが、それはまた別の話になるだろう。
曲は最初に現れるサンバ風の主題を中心に様々な旋律がロンドのように連結されていくもので、途中8分の3拍子の牧歌的な中間部を挟む。
全体に平明な印象だが調性配置が独特で全曲中にすべての調性が出現するように仕組まれていて頻繁に転調するため気が抜けない。
多調性技法(複数の調性が同時に演奏される)が多用され滑稽かつ幻惑的な効果を挙げているが、これまだ演奏者の耳を惑わせる。
ミヨーはロンドン再演の際、練習で現代音楽に不慣れな女性ホルニストを何度も叱りつけたらしいのだが、我々としては彼女に深く同情するばかりである。
このように一筋縄ではいかない曲だが全体に溢れる陽気なラテンのノリと1920年代の幕開きにふさわしい輝きを表現できたら成功だと思うのだが…。ご期待ください。
シューマン:交響曲第3番「ライン」
1850年、ロベルト・シューマン40歳。
この年は彼にとって大きな転機の年であった。長いこと定職のない時代が続いていたが、デュッセルドルフ市の合唱団指揮者に推薦され、散々迷った挙句ついに 引き受けることに決めたのである。シューマンは、このライン河畔の街に転居してから、わずか1ヶ月間でこの交響曲第3番を完成させた。ラインの明るい風光 を反映した作風から、この曲は通常「ライン」と呼ばれている。
交響曲第3番「ライン」は、シューマンの交響曲(全4曲)の中では人気が高く、おそらく最も演奏される機会が多い曲である。しかし、私にとって、この曲 は、長いことよく分からない曲だった。「ラインの明るい風光が反映された曲」と言い切ることのできない、異様な昂揚感、緊張感をこの曲の随所に感じるので ある。
たとえば1楽章。堰を切ったようにあふれる第1主題はヘミオラのリズムを刻みながらうねり、やがて、その合間をぬって、胸がしめつけられるような切ない旋 律の第2主題が現れる。この両者の相克と、お互いを巻き込みながら前に前にと進んでいく、この勢い、ひたむきさに「明るい」などという形容詞はまったくそ ぐわない。
また、2楽章の民謡風の鄙びた旋律は、ほのかな諧謔性を秘めているし、3楽章のささやくような旋律は、温かさに満ちているが、同時にため息の翳を帯びてい る。そして、葬送行進曲のようにモチーフが繰り返し立ち現れる4楽章…。何よりも私が不思議に感じるのは5楽章である。5楽章の第1主題は交響曲第2番の 終楽章のそれとよく似た音形だが、底流をなす心情は2番のそれよりずっと穏やかである。
ダンスのステップを踏むように躍動する若々しい旋律は、幸せの絶頂を歌っているようでありながら、もうその幸せは手中にはないという印象を抱かせる。2番 の終楽章が爆発的な歓喜の歌であるのに対し、3番のそれは過去の幸せを手の中で慈しんでいる、いわば過去形の歌のような気がしてならない。これは単なる思 い込みだろうか。
シューマンが初めてラインを見たのは19歳の春であった。彼はラインの印象を以下の様に書き記している。「目を開けると…前にラインが横たわっていまし た。そっと静かにおごそかに誇り高く、古いドイツの神のように」。このライン旅行は天気に恵まれ、彼は始終、上機嫌だった。「自ら(馬車の)手綱をとった のです。うわあ!馬が走ったことといったら!僕は何もかも忘れて陽気でした。こんな神様のように陽気だったことは今までなかったと思います」。このような 手記から、後年、精神を病み、ラインに身を投げるシューマンを想像することは難しい。彼に何が起こったのだろうか。
21歳、シューマンはピアニストを目指し猛練習を始めるが、無理な練習のせいで(梅毒という説もあるが)23歳で指を故障、ピアニストの道は断たれてしま う。意気消沈したシューマンは深刻な鬱状態に陥った。後に、その時の精神的危機について、シューマンは以下のように書いている。「1833年10月17 日、18日、急に恐ろしい考えに襲われた。人間が持ちうる限りの、天が人を罰しうる最も恐ろしい考えに…理性を失うという考えに。この考えに激しく囚われ てしまうと、慰めも祈りも嘲りも何の力もなくなる。この恐怖から僕はあちこちとさまよい…こう考えて、息が止まった…考えるということができなくなったら どうなる!…クララ、ここまで破壊された人間に病気も悩みも絶望もありはしないのだ…!(中略)…どうにもならない状態にまで追い込まれたら、自分の生命 に手をかけないとも保証できない、その恐ろしさ…」。文献によっては、この年、最初の自殺未遂を起こしたともいわれている。痛ましい限りだが、数ヵ月後、 日記に「正気。文筆の仕事を始める」という言葉が出るように、ひとまず回復。その頃からピアノ教師の娘クララとの間に少しずつ恋が育っていく。やがて二人 は深く愛し合うようになり、1837年に婚約。彼女の父親の猛烈な反対にあうが、裁判にまで持ち込んで、1840年、ようやく結婚にこぎつけた。幸せいっ ぱいのシューマンはこの1840年の1年間に大量の歌曲を作っている(136曲も!)。
しかし、結婚生活を送っていくうちに、シューマンの精神状態は再び悪化していく。9歳年下のクララは華奢で可憐なその風貌に合わず、メンデルスゾーンに 「鬼神のように弾く」と言わしめた実力派ピアニストで、すでに社会的に非常に高い評価を受けていた。それに対し、シューマンは「音楽評論家」兼「指揮者」 兼「作曲家」で、一部の人から高く評価されていたとはいえ無名の青年にすぎなかった。合唱団の指揮をしたり音楽学校で教鞭をとったりすることはあったが、 いずれも長くは続かず、当時、4人の子どもを抱えたシューマン家の生計は、ほとんどクララが支えていたと思われる。演奏旅行に同行すれば「クララの夫」と いう立場に甘んじなくてはいけないことも多かった。シューマンの焦りと悲しみは想像に難くない。
そして34歳、ついにシューマンは鬱、不眠、幻聴、幻覚を伴うひどい精神疾患の発作を起こしてしまう。芸術家によっては精神的危機の時でも(むしろその時 の方が)豊かな創造力を発揮する人もいるが、シューマンは発作が起こるとまったく仕事が手につかなくなってしまうタイプだった。同年、シューマンは音楽評 論の仕事を辞し、療養のためドレスデンに転居する。それから5年近くは、小康状態と鬱状態を行ったり来たりする生活を送ったようだ。
40歳、徐々に健康を取り戻していたシューマンに舞い込んできたのが、前述の、デュッセルドルフの合唱団指揮の仕事だった。この仕事を引き受け、5人の子 どもと6人目を身ごもったクララを連れて、デュッセルドルフに転居してきたシューマンの決意、覚悟の厳しさは想像に難くない。そんな意気込みを持つシュー マンの瞳に、ラインはどのように映ったのだろうか。19歳当時に感動した明媚な風光はそのままだっただろう。しかしそれを見つめるシューマン自身はなんと 変わってしまったことか。あの頃の屈託のなさと快活さは、深い精神疾患を患ったシューマンには、もう決して取り戻すことのできないものであった。
この曲が孕む異様な緊張感と昂揚感の原因は、このあたりにあるのではないだろうか。シューマンの「まだ俺は大丈夫だ」「ここで生きるのだ」という気迫、再 生への祈り、そして、若い日の幸せな思い出に対する憧憬の切実さが、この曲には満ち満ちている。今日の我々の演奏がそこまで表現できれば、これほど嬉しい ことはない。(ちなみに、シューマンはこの曲を作曲した4年後、ラインに身を投げた。救助された後は精神病院に収容され、2年後に死去。享年46歳であっ た。)
シューベルト:交響曲第3番
シューベルトの交響曲を当団が演奏するのは4、8、9番に続いて4曲目となる。
およそ古今の作曲家は天才揃いだが、シューベルトの天才ぶりはモーツァルトと並び群を抜いているように思う。彼は生涯に1000曲もの名曲を残しているが、その人生はわずか31年。つい先日彼の年齢を上回ったばかりの筆者としては、ただただ驚嘆するのみである。
さらに、この交響曲3番が作曲されたのはわずかに18歳の時で、1815年のことである。今で言えば、ちょうど高校を卒業したくらいの年齢だが、彼は既に学校の助教員を務めている。
さて、1815年と言えば今を去ること200年余、日本では江戸時代後期の文化・文政と呼ばれる時代である。時の将軍は11代徳川家斉、二本差しの武士が闊歩していたころである。
日本史の授業めいて恐縮だが、この時代は伊能忠敬が蝦夷地を探検し(1800)、間宮林蔵が樺太を探検し(1808)、異国船打ち払い令なるものが発布さ れ(1825)、わが日本は鎖国の真っ只中にあった。そんな時代に、遥か彼方のオーストリアではベートーベン、シューベルト、ウェーバー達が活躍していた のである。さらに余談だが、シューマンが「ライン」交響曲を作曲した1850年は、ペリーが浦賀に上陸して開国を迫った3年前にあたり、攘夷か開国かをめ ぐる幕末の動乱の萌芽が兆していた時期になる。
曲は型どおり4楽章からなる。1楽章はアダージョの序奏を持ったソナタ形式で、主部ではクラリネットのかわいらしい第1テーマと、オーボエの跳ねるような 第2テーマが印象的である。2楽章は本来は緩徐楽章だが、この曲ではアレグレットであり、同時期に作曲されたベートーベンの第7、第8交響曲の影響がみて とれる。
中間部ではクラリネットの旋律が微笑ましい。3楽章はメヌエットの表示であるが、スフォルツアンドが頻出しスケルツオとしての要素も認め られる。トリオではオーボエとファゴットが鄙びた旋律を歌う。終楽章はタランテラという飛び跳ねるようなリズムにのったプレストで、頻出する転調はシュー ベルトならではである。
さて、この交響曲は演奏によって、様相が一変する。この曲をこよなく愛したトーマス・ビーチャムはゆったりとしたテンポで美しい風景を眺めながら散歩する ような演奏であるが、カルロス・クライバーは一陣の風が吹き抜けるような爽快なテンポで駆け抜けている。われらがマエストロ金山によって当団がどのような 演奏を繰り広げるか、ご期待下さい。
バルトーク:ヴィオラ協奏曲
作曲者が死によって完成させることのできなかった作品を、弟子や学者が本人に代わって完成させるということは数多い。文学や絵画においては希なこの「補筆完成」という作業は、時に非常な困難を伴う。
バルトークは1945年、ヴィオラ奏者ウィリアム・プリムローズからの依頼でヴィオラ協奏曲を作曲したが、草稿の段階で白血病による死を迎える。 遺された草稿はバラバラの五線紙15枚に走り書きされたままのもので、もちろんオーケストレーションはされていないし、楽章の構成さえもはっきりと判別できるものではなかった。
この遺稿を判読、補筆完成させたのが、バルトークの弟子で友人の一人、ティボール・シェルイ(1901-1978)である。 彼はやはりバルトークの未完成作品、ピアノ協奏曲第3番を補筆していたが、こちらは最後の十数小節をオーケストレーションするだけの作業だった。 しかし、ヴィオラ協奏曲は上記のような状態で遺されていたので、音符の判読だけにに4ヶ月もかかり、さらに内容を再構成してオーケストレーションを完成させることになった。
完成したスコアを見てみると、テクスチャーの極端に薄い部分が目立つが、バルトークが死の直前にプリムローズに宛てた手紙の「オーケストレーションはかな り透明なものになるでしょう」という一文に拘束されたものである。そしてヴィオラパートは「プリムローズ編」となっているが、プリムローズは演奏効果が上 がるように(難しく)書き換えた部分もあるようだ(このせいで、後のヴィオリスト達は必要以上に苦労することになる)。
そして1995年、シェルイ版とは別に、ピーター・バルトーク(バルトークの息子)とネルソン・デラマッジョーによる新しい「改訂版」が出版された。 つまりこれからは、モーツァルトの「レクイエム」のように複数のヴァージョンが存在するのである。 今日の演奏はシェルイ版によって行われる。
(バルトークのヴィオラ協奏曲が補筆され、出版されたことの背景には、もちろんバルトークが偉大な作曲家であったことによるが、「ヴィオラ協奏曲」というジャンルの絶対的な曲不足も少なからず影響している。)
第1楽章 Moderato ソナタ形式。アタッカ:
第2楽章 Adagio religioso 変則的な3部形式。アタッカ:
第3楽章 Allegro vivace ロンド形式。
主な未完作品の分類
タイプA:未完の状態のまま演奏されるもの
J.S.バッハ フーガの技法
タイプB:途中の楽章(幕)まで演奏されるもの
マーラー 交響曲第10番 Adagio
ブルックナー 交響曲第9番
シェーンベルク 歌劇「モーゼとアロン」(最終幕は台詞のみで上演)
タイプC:他人によって補筆完成されたもの(括弧内は補筆者)
モーツァルト レクイエム(ジュスマイアー、バイアー等数種)
マーラー 交響曲第10番(クック)
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」(アルファーノ)
ベルク 歌劇「ルル」(ツェルハ)
バルトーク ピアノ協奏曲第3番(シェルイ)
バルトーク ヴィオラ協奏曲(シェルイ、P.バルトーク&デラマッジョーの2種)。
ヴォーン=ウィリアムズ:タリスの主題による幻想曲
T・タリス(1505~1585)、ダウランド、パーセル、とルネサンスからバロックにかけての隆盛のあと、イギリス作曲界には長い空白時代が訪れていた。
その後エルガー(1857~1934)、ブリテン(1901~1976)の登場によって、イギリス音楽界は再度沸き返ることになるのだが、この二人のちょうど中間世代に位置するのがヴォーン=ウィリアムズ(1872~1958)である。
「タリスの主題による幻想曲」は1901年にある音楽祭の為に書かれた弦楽合奏曲で、2つのオーケストラ・グループ(それぞれ別の場所に配置される)とソロ・カルテットの編成により演奏される。 ヴォーン・ウィリアムズは依然よりイギリス讃美歌集の編集を行っており、その中に含まれていたタリス作曲の讃美歌の一遍からこの曲のテーマを得たようだ。
ノルマン様式の荘厳な協会をイメージした、と作曲家自身が語るように、全体を透明で敬虔な雰囲気が統一しており、主題の性格にもよるのかいくぶん中世的で素朴な香りを残している。
曲は冒頭、「ハムレット」劇の亡霊の足音を思わせる低弦ピッツィカートによってタリスの主題を準備した後、"幻想曲"という標題が示すようにテーマを自由に展開していく。
中間、ヴィオラ・ソロに始まるソロ・カルテットから次第に激しさを増していき(この辺の盛り上がりはまさに"悦楽"として取り上げる所以でもある)、三連符を伴う力強いクライマックスを経たあと、徐々に穏やかさを取り戻し、終結へと向かっていく。 ごく小さな編成からなる第二オーケストラは第一オーケストラのエコーの役割を果たしており、その呼応はあたかも聴衆が大聖堂の中にいるような錯覚を生み出すほどの音楽空間を作り出す。
概してイギリス音楽はドイツ的な起承転結や、ラテン的な情熱に欠ける為、とらえどころがなく、一つ間違えば退屈さに転じる性質を持っている。だがしっかりと耳を傾ければ、この憂愁、静謐なロマンティシズムはほかにとって代えがたいものがある。 イギリスには他にもディーリアス、フィンジなど美しい曲を書いた作曲家が数多く存在する。 今回の演奏をきっかけとして多くの方にイギリス音楽への造詣を深めていただければ幸いである。
シェーンベルク:室内交響曲第2番 Op.38
12音音楽の創始者」「現代音楽の父」として知られるシェーンベルクであるが、最近は「浄夜」、「グレの歌」などの後期ロマン派の作風で書かれた作品を中心にポピュラリティを得つつある。
しかし「月に憑かれたピエロ」や「モーゼとアロン」のような専門家にのみ受けのよい作品が一般聴衆に受け入れられるには、「無調」という大きな障壁があるのでやはり難しいであろう。 どうして彼が調整を放棄し、12音技法を生み出したのか、あえてこの議論はここでは省くことにする。 この問題の思想的背景に言及するにはバッハ以後のドイツ・オーストリア音楽を慎重に考察することが必要不可欠であるからだ。
さて、今日の「室内交響曲第2番」は幸いなことに調性を持った作品である。
いわゆる「後期ロマン派に属していた時期」に書き始められ、幾度もの中断を経て、12音技法を擁立した後の時代に完成した。
この過程を彼のほかの作品、私生活と絡めて見ていきたいと思う。
1899年から1903年にかけて大変官能的な作品を3つ続けて作曲する。 「浄夜」「グレの歌」(オーケストレーション完成は1911年)、「ぺレアスとメリザンド」の3作品で、いずれもワーグナーやR・シュトラウスの影響を受けた後期ロマン派風の大作である。 この時期、彼は師匠ツェムリンスキーの妹、マチルデと結婚している。
1904年、単一楽章で40分かかる「弦楽四重奏曲第1番」を作曲。 この年、ベルクとウェーベルンが弟子入りした。
1906年、あまりにも重要な作品といわれている「室内交響曲第1番」を作曲する。 15人で演奏されるこの作品は、従来の交響曲のような多楽章形態をぐっと圧縮して、単一楽章にその要素を詰め込むという手法で書かれている。 「ペレメリ」と「第1番四重奏曲」で試されたこの手法がここで一応の完成を見たことになる。 一方、ハーモニーの点では「四度和音」と呼ばれる特徴ある響きを用いた(完全四度をいくつか積み重ねた和音で、例えば下からレ・ソ・ド・ファなど)。 ドビュッシーも使っている和音だが、シェーンベルグはドミナント、サブドミナントの代わりにこれを終止形にはめ込み、これによって調性感が希薄になった。
「第1番」に引き続きいよいよ「室内交響曲第2番」を書き始める。 第1楽章は「第1番」同様、四度和音の多用によって曖昧模糊とした響きの中にほのかなロマンティシズムを漂わせている。 作業は1908年頃まで続くが、第2楽章の途中で筆が止まってしまう。 この中断には諸説があるが、この1908年、シェーンベルク家に大きな事件が起きている。
実はシェーンベルクは画家でもあった。200点以上の表現主義的作品が残されており、1906年から1912年までの間に集中的に描かれたようである。 ほかの同時代の画家、例えばココシュカ、カンディンスキー等とも親交を温め、互いに影響しあっている。 その中にリヒャルト・ゲルシュトルという若い画家がいた。 彼はシェーンベルクの家族とも親しくなり、「シェーンベルクの家族」と題される作品も残しているが、何とシェーンベルク夫人がゲルシュトルと恋仲になり、家を出てしまうというとんでもない事態に発展してしまった。 結局、友人たちの尽力によって夫人はシェーンベルクのもとに戻ってきたが、ゲルシュトルはこの結果自殺してしまう。 自分の作品を燃やした灰の上で首を吊ったという。 シェーンベルクもこのとき遺書を書いているが、この事件の後彼は何かに憑かれたように絵を描きまくった。
事件のあった頃彼は「弦楽四重奏曲第2番」を完成させている。 第3、第4楽章でソプラノが加わっているのが外面的に大きな特徴だが、第4楽章でいよいよ無調の世界に踏み込んだのも見逃せない。
さて「室内交響曲第2番」の方であるが、1911年と1916年に若干書き進められたがまたしても完成できなかった。 このときに曲をメロドラマ(歌わずに語る歌詞の音楽に伴奏がついたもの。「グレの歌」第3部ですでに採用している。)で締めくくるという着想を得たのだが、結局それは破棄された。 ちなみにその詩は「転回点」と題され、「この道をさらに歩むことはできなかった」と始まる。
1933年ドイツはナチによる暗黒の時代が始まった。 ところでシェーンベルクはユダヤ人である。
当時ベルリンにいた彼は半ば半強制的に国外追放される。 まずフランスに移り、そこでユダヤ教に復帰し、そしてアメリカに向かったのだ。
アメリカ時代のシェーンベルクはすでに手中のものとしている12音技法で作曲するのと同時に「コル・ニドレ」に代表される調的な作品も再び書き始めた。 この時期に、指揮者のフリッツ・シュティードリィーが未完の室内交響曲を完成させるように依頼しに来た。 「室内交響曲第2番」はこれで完成されることになるが、若い頃の様式と、無調、12音技法を経過した当時の様式を見事に止揚した作品に仕上がっている。 しかし、この時期に書かれた第2楽章のコーダは、異常なほどの残虐性を持つカタストロフである。 どうしてここまでする必要があったのであろうか。 忌まわしい過去の事件を思い出したのか、それともヨーロッパで同胞たちに襲いかかる悲劇を思ってのことか。
1939年に完成し、翌年シュティードリーによって初演された。
この後のシェーンベルクの興味は、調性と12音技法の調和、そしてユダヤ人としてのアイデンティティにあったようで、「ナポレオンへの頌歌」、「ワルソーの生き残り」等の名曲を残している。
1951年、死に瀕した彼の最後の言葉は「ハーモニー...」であった。
第1楽章 アダージョ。2/4拍子。変ホ短調。3部形式。
四度和音の多用が印象的な楽章である。 「浄夜」や「ぺレアスとメリザンド」の冒頭の響きにも似た「月明かりの音楽」で始まり、ポーコ・ピウ・モッソの中間部ではロマンティックな旋律が現れるが、パトスに陥るのを慎重な手法で避けている。
第2楽章 コン・フォーコ。 6/8拍子。ト長調。ソナタ形式。
一応ソナタ形式で書かれているが、スケルツォ的性格を持つ。 交錯するリズムと半音階的な動機がソナタ部を支配している。 第1楽章に基づくコーダを持ち、あまりにも生な楽器法がカタストロフを形成する。 最後には地にのめり込んでいくような強烈な下降音型と、変ホ短調の救いようのない絶望的な和音で曲を閉じる。
メンデルスゾーン:交響曲第4番イ長調「イタリア」 (Vn. M.K)
メンデルスゾーンは1890年ユダヤ系ドイツ人としてハンブルクの裕福な銀行家の家に生まれ、幼児から本格的な音楽教育を受けその天才ぶりを発揮した。
この第4番「イタリア」を含め五つの交響曲、演奏会用序曲、たくさんのピアノ作品、室内楽、歌曲、それに何といってもヴァイオリン協奏曲ホ短調など、数々の珠玉のような名曲によって、ショパン、シューマンなどとともに初期ロマンはを代表する作曲家とされている。
当時はほとんど忘れられていた「マタイ受難曲」を演奏し、19世紀におけるバッハ再評価の気運を作った功績も忘れることはできない。
さて彼の音楽の特色は、いわば爽やかに匂いたつような、つまりある種の香気に満ちた作風にあるのではないだろうか。 これは、よくいわれるように彼の生い立ちからくるものであるとともに、ロマン主義的内容ないし精神を古典主義的様式で表現していることとも無縁ではないと思われる。
彼は、20才の1829年から23才の1832年にかけて、イギリスをはじめオーストリア、イタリア、フランスなどを旅し、そのうちローマに30年から翌31年にかけて滞在したが、「イタリア」はこの時書き始められた。 31年に出した手紙には「イタリア交響曲はおおいに進捗している。この作品、特に終楽章のプレスト・アジタートの部分は私の書いた曲の中ではもっとも成熟したものになるだろう。」と述べている。
そしてロンドン・フィルハーモニー協会からの依頼もあって33年に完成され、同年作曲者自身の指揮の下に初演された。 しかし彼はこの曲の出来栄えに必ずしも満足していなかったらしく、ことに第4楽章については書き直したいとさえ言っていたという。 事実生前には出版もせずドイツでは演奏もしなかった。 結局ドイツでの初演は彼の死から2年後の49年、ライプツィヒのゲヴァントハウスで行われた。
第1楽章アレグロ・ヴィヴァーチェ、イ長調、8分の6拍子、ソナタ形式。
2小節の木管による和音の軽快な刻みに続いてあたかもイタリアの空を思わせるように明るく、踊るような第1主題がヴァイオリンで提示される。この動機は60小節にわたって展開され、さらに50小節余りの経過句の後属調のホ長調の第2主題がクラリネット、ファゴットによって奏される。これがクライマックスに達したのち、第1主題が戻り提示部は終わり、反復される。展開部は提示部の経過句の動機から派生した新しい主題によるフガートで始まり第1主題が再現される。そのクライマックスが一旦静まって後、クレッシェンドしつつ再現部に入り、第1、第2主題が再現される。コーダはピウ・アニマート・ポコ・ア・ポーコとなって第1主題ともう一つの主題が弦と管で交互に提示され、スタッカートの3連音の走句は若々しい朗らかな気分を漲らせつつこの楽章を閉じる。
第2楽章アンダンテ・コン・モート、ニ短調、4分の4拍子。
行進曲風のリズムの支配するこの緩徐楽章は、彼がナポリで見かけた宗教的行列の印象から着想したといわれる。 まず、冒頭に木管と弦により重々しく哀愁に満ちたフォルテの楽句が示され、オーボエ、ファゴット、ヴィオラによって叙情味豊かな主旋律が奏でられ、さらにそれはフルートの対旋律を持ったヴァイオリンに受け継がれる。 この間バスは、8分音符の重々しい足取りを聞かせている。この楽章の中間部はイ長調となり、クラリネットは対照的な表情を持つ旋律を歌い始める。冒頭の部分がさらに少し形を変えて再現されこの楽章を終わる。
第3楽章コン・モート・モデラート、イ長調、4分の3拍子。
この楽章はスケルツォではなくメヌエットであるが、単なる美しさを超えた、いわば地中海的優雅さ、明晰さ、あたたかさ、それに香を備えている。 トリオに相当する部分はホ長調となる。
第4楽章サルタレッロ-プレスト、イ短調、4分の4拍子、ロンド形式。
この終楽章こそは彼が最も力を注ぎ、また苦心した部分で、ローマ地方のダンスであるサルタレッロのリズムによる二つの主題が提示される。 さらに3連音が均等に流れる第3の主題はナポリ地方の舞曲タランテッラのリズムである。

 プログラムノート
プログラムノート