ブラームス 悲劇的序曲
ブラームスはその作曲活動において、同時期に相反する性格の2つの曲を書くという傾向を持っていた。例えば、「ベートーヴェンの9曲の交響曲に匹敵する ものを」と考え、構想から20年もかけて作り上げた交響曲第1番と、それまでの長い道のりがまるで嘘であったかのように、その翌年に早くも完成させてし まった交響曲第2番が挙げられる。今回取り上げるこの『悲劇的序曲』についても同様のことが言える。作曲されたのは1880年であるが、ちょうど同じ年 に、ブラームスはブレスラウ大学から名誉博士号を贈られた返礼として『大学祝典序曲』を書いている。名前からしてもその対照性は明確である。
さて、『大学祝典序曲』と『悲劇的序曲』だが、ブラームスのこんな書簡が残されている。「大学のための曲は私をなおも別の序曲へと誘惑しています。私は それを『劇的な』とだけ名づけていいと思っています。」「この機会に私の孤独な気持ちに、『悲劇的序曲』を書くのを誓わざるを得ませんでした。」また、作 曲の数年前から直前にかけて、生涯愛を寄せたクララ・シューマンの息子フェリックスの死、親友の画家フォイヤーバッハの死、同じく親友だったヴァイオリン 奏者ヨアヒムとの不和(実際に絶交状態になったのは作曲後だが)といった出来事が続いていた。こうしたことが積み重なり、長年続いてきたメランコリックな 気分を表現すべく、ブラームスは『大学祝典序曲』を媒介として『悲劇的序曲』を作曲するに至ったと考えられる。
このように書いてくると、いかにも字面通りに悲劇的で、およそ演奏会の幕開けとしてはふさわしくないのではないかと思われるかもしれないが、実際聞いて みるとそんなことはなく、ブラームスの心情とは裏腹に、この曲には強靭な意志の力が満ちていて、悲劇的とは言いながらも決して涙は見せていない。よって、 「悲劇的」という名を冠するよりは、むしろ彼の書簡にあった「劇的」という言葉の方が的を射ているのかもしれない。曲はソナタ形式に基づき、激しい跳躍で 力強い第1主題、朗々と歌う第2主題が様々に展開していき、結尾ではニ短調の力強い和音で終わる。
最後に、この曲の編成はブラームスにしては大きい方で、ピッコロ、3本のトロンボーン、テューバを含んでいるが、これらの楽器の出番はきわめて限定さ れ、しかもそのほとんどが弱音であり、曲の経過部において神秘的で美しい効果を出す役割を果たしているということを付け加えておきたい。
R. Wagner:《トリスタンとイゾルデ》~前奏曲と愛の死
あらすじ:寡夫の老マルケ王の甥・家臣で国の英雄であるトリスタンは、かつて他国の王女イゾルデの許婚を殺し重傷を負ったが、他ならぬイゾルデに助けら れ、互いに知れず愛し合うようになる。忠義心の厚いトリスタンは、自らの思いをよそにイゾルデこそマルケ王の後妻に相応しいと考え、自ら船で迎えに行く。 イゾルデはトリスタンと共に毒薬を飲んで死のうとするが、侍女が偽って媚薬を飲ませたため、二人は赤裸々に愛し合うようになる。密会の現場をマルケ王と家 臣たちに押さえられ重傷を負ったトリスタンは、故郷に帰るものの息絶え、追ってきたイゾルデもこれに続く。
以上簡単に書いたが、細部での感情や思想により重きが置かれており、内面的な劇と言える。
さて、内面劇と書いた「トリスタン」であるが、音楽的には調性が不明確であることが対応しており、それこそが画期的、かつ音楽的な大事件であるとされる。 つまり、音楽的な自然欲求である和声的解決や主和音が得られず、絶えずそれを求めつつも手が届かない状態が作られている。ワーグナー得意の無限旋律や半音 階進行も多用される。こういった手法を用いることで、「愛」といった明確に定義しにくい複雑な感情や、相反的な要素(「本音と建て前」「可愛さ余って憎さ 百倍」など)を内包した曖昧・微妙な感情をも表現している。結果的に、従来のオペラにありがちな「善玉」「悪玉」の二元論的なシンプルさとは全く異なるも のとなっている。
ちなみにワーグナー自身もこの作品には相当の自信があったようで、「驚くべき作品になる(第1幕作曲中)」「私の今までの芸術の最高峰(第2幕作曲終了 時)」「お前は悪魔の申し子だ!(第3幕作曲中)」「トリスタンは今もって私には奇跡だ(作曲後)」などと述べたそうである。作品成立の背景には、ドレス デン革命での指名手配中といった状況、ライフワークの「ニーベルングの指環」における行き詰まり、妻ミンナとの不仲、そしてなによりも、彼に隠れ家を提供 した恩人ヴェーゼンドンクの夫人マチルデとの「愛の耽溺」と、ショーペンハウアーの「生命への意志の究極の否定」といった思想への接近があった。
「前奏曲と愛の死」は、全3幕の最初と最後を接続したもので、本来「愛の死」にはイゾルデの独唱が入る。短いながらまさに全曲のエッセンスといえる曲である。
前奏曲:劇中の特に主要な動機で構成されている。冒頭のチェロ、続いて木管が有名な「トリスタン動機」を出す。ffまで到達した後、チェロに2つの「愛の 動機」が順に現れ、不吉な「運命の動機」がこれに絡む。以後これらの動機で展開し、「法悦の動機」も入って最高潮に達し、爆発した後、やや憂鬱なまま冒頭 の雰囲気へと戻っていく。
愛の死:冒頭、バス・クラリネットで出る「愛の死の動機」が次々に転調し、「愛の浄化の動機」も加わって恍惚と盛り上がる。楽劇中の密会時には阻まれた頂 点をようやく得て、イゾルデは「世界の息の通う万有の中に/溺れ、沈んで/意識なき至高の悦び」の中に息絶える。ワーグナーはこの曲を「隔てなき永遠の不 安なき合一」であると言っている。
ベートーヴェン 交響曲第7番 イ長調 作品92
この曲が作られたのは、1811~12年。
1812年は、それまで破竹の勢いで勢力を拡大してきたナポレオンが、ロシアで初めて敗退し、フランス革命から続いてきた革新の時代が終わり、新しい時代へと歴史が回転し始めた年。
音楽の世界でも、歴史が回転しつつあった。古典派を代表してきたハイドンは3年前に亡くなり、サリエリなども62歳となった一方で、新時代のロマン派を になう人々は、シューベルトがかろうじて15歳、あとはメンデルスゾーンが3歳、シューマンが2歳という幼児であり、まさに"はざ間の時代"だった。
■1812年当時の年齢
- ハイドン(1809年没)
- サリエリ 62歳
- ベートーヴェン 42歳
- シューベルト 15歳
- ベルリオーズ 9歳
- J.シュトラウス(父) 8歳
- メンデルスゾーン 3歳
- シューマン 2歳
- ショパン 2歳
- リスト 1歳
- ワーグナー(1813年生まれ)
- ヴェルディ(1813年生まれ)
そんな中、ベートーヴェンは42歳。人生的にはともかく、音楽的にはまさに脂ののった時期で、それまでの古典派の音楽を自分のものとし、次の時代への準 備をしていた。ベートーヴェンの作品を通して見たとき、1810年頃から1816年頃までが中期から後期への移行期間とされており、この頃から作品の中に 哲学的なものを含んでいるようなものが増えていく。
■1810~16年の主な作品
- 交響曲第7番 1811~12年
- 交響曲第8番 1811~12年
- 弦楽四重奏曲第11番「セリオーソ」 1810年
- ピアノ三重奏曲第7番「大公」 1811年
- チェロソナタ第4番 1815年
- チェロソナタ第5番 1815年
- ピアノソナタ第27番 1814年
- ピアノソナタ第28番 1815~16年
そうした期間の作品の中では、この交響曲第7番は、とても勢いのある曲で、より中期に近い"華やかさ"を感じられる作品だ。音程・リズム・強弱を3大要素としたとき、そのうちのリズムが特に強調されており、とても躍動感のあるイキイキとした交響曲になっている。
第1楽章は、繰り返し現れる上行音型が印象的な序奏部を経て、8分の6拍子の主題に入っていく。ここからは「ターンタタン」というリズムが、常に現れ る。ソナタ形式だが、第1主題も第2主題も同じように「ターンタタン」というリズムを基本にしているので、第2主題の始まりには気付かないかもしれない。 聞いているうちに「ターンタタン」というリズムが身体に染み付いて、この楽章が終わっても、頭の中で鳴り続けてしまいそうだ。
第2楽章は、短調と長調の入れ替わりがとても印象的。短調部分は縦のリズムが、長調部分は横のメロディが大事にされているので、両者の違いがさらに浮き立ってくる。
第3楽章は、出だしから飛び跳ねるようにして進んでいく。第2楽章のイ短調に対して、ヘ長調であるというのも鮮烈な印象を与えてくれる。
第4楽章は、アレグロ・コン・ブリオ。すさまじい数のfやsfが書き込まれていて、ベートーヴェンの情熱が伝わってくるようだ。調性もイ長調に戻り、今 までの第1~3楽章をがっちりと受け止めて、この終楽章のための第1~3楽章だったのか、という勢いで感動的な終焉を迎える。


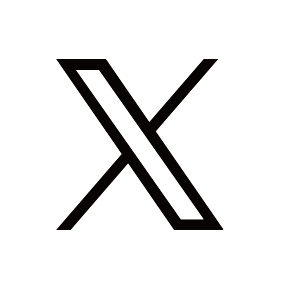
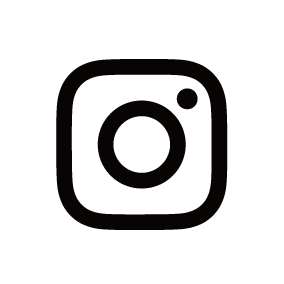

コメントを残す