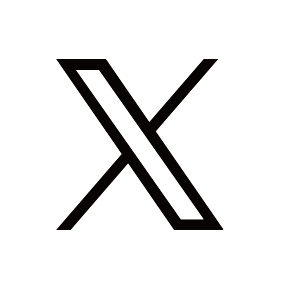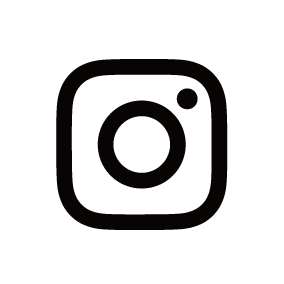カテゴリー: プログラムノート (1ページ目 (2ページ中))
ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」序曲
ドイツに生まれ、父の率いる歌劇団で各地を巡る幼少期を過ごしたウェーバー。13 歳にしてオペラを作曲し、17 歳のときには劇場の楽長に就任、とその才能は早くから開化。その後、プラハの名門歌劇場の指揮者に就任し、傾きかけていた歌劇場を見事に再興させ、ドレスデン歌劇場の音楽監督に抜擢される。ピアノ奏者でもあり、身体は小柄だったが10 度の和音をとらえる長い指を持ち、素晴らしい演奏技術を誇った。
さて、イタリアオペラが主流だった19 世紀初頭のヨーロッパ。そんな中に登場した、ドイツ人による、ドイツ語を使った、ドイツを舞台とし、ドイツの人々に古くから読まれてきた民話が元になっているウェーバーの歌劇「魔弾の射手」。
舞台は深い森―。主人公・狩人のマックスは、恋人アガーテと結婚するため、射撃大会に出るも、一発も命中しない。そんな様子を見たアガーテの父から、明日の射撃会の結果次第ではアガーテとの結婚を認めないと言われる。
悪魔と契約し、アガーテを生け贄にしようと企てていた狩人のカスパール。カスパールはマックスをそそのかし、明日の大会で魔弾の力に使うよう仕向ける。マックスは迷ったが、7つの魔弾を造り大会で使うことに。
翌日の射撃大会。6発は的に的中。7発目をマックスが撃ったとき、その弾はアガーテに!!…と見せかけて、カスパールに命中。
事の真相を打ち明けたマックスは永久追放の処分が下されるが、聖なる隠者の助言により1年間の試練を与えられ、行いが正しければアガーテとの結婚を許されることに。
いつの時代もハッピーエンドとホルンは愛されるものなのでしょうか。日本の童謡「秋の夜半」(あきのよわ)でも使われている冒頭のホルンの旋律。何度聞いてもしびれます。
(Tp. N. I.)
シューベルト/交響曲第5番 変ロ長調
交響曲第5番が作曲された1816 年は、19 歳のシューベルト(1797-1828)にとって大きな転機となる年であった。それまで勤めていた父親の学校での教職を辞し、音楽に生きることを志したのである。当時はまだ出版社から楽譜が出ることもなかったシューベルトを、友人たちは衣食住にわたり惜しみなく援助した。そのおかげでシューベルトは次第に作曲のみに専念するようになり、彼らの家では私的な演奏会が夜ごとに開かれた。
半年ほど前に作曲された交響曲第4番「悲劇的」のドラマチックなメロディーとは打って変わり、この第5番ではシンプルで軽快なリズムやフレーズが印象的である。オーケストラ編成の小ささ、調性の展開、それに個々のフレーズ等、多くの点でモーツァルトとの類似性が指摘されている。シューベルト自身がおそらく意図して、敬愛するモーツァルトへのオマージュとして作曲したのであろう。
実際、シューベルトが同年にモーツァルトの弦楽五重奏曲を聴いた日の日記では、以下のようにモーツァルトを絶賛している。「おお、モーツァルト! 不滅のモーツァルト! どれだけ多くの、おお、どれほど尽きることのない、軽やかでより良い生の刻印を、慈悲深くも我々の魂に刻み付けたことか!」
第1楽章 Allegro 変ロ長調、ソナタ形式
シューベルトの交響曲では初めて緩徐な序奏が存在せず、管楽器による4小節のカデンツのみが導入部である。5小節目から提示される第1主題は、軽快なスタッカートのリズムを伴った上昇形の分散和音であり、楽章を通じたモチーフとなっている。通常のソナタ形式とはやや異なり、再現部では変ロ長調の下属音である変ホ長調で主題が演奏される。
第2楽章 Andante con moto 変ホ長調、ロンド形式
歌曲のような甘美な主題が2回提示されるや否や、変ハ長調へと転調する。この転調はシューベルトの作品に特徴的なものであり、単にモーツァルトの模倣をしているわけではないことがうかがえる。その後も転調を繰り返し、ロ長調、短いながらも印象的なト短調を経て変ホ長調に戻る。
第3楽章 Menuetto. Allegro molto ト短調
シューベルトの他の交響曲のメヌエットとは趣の異なる、スケルツォ風の楽章。むしろ、モーツァルトの交響曲第40 番の第3楽章との類似がしばしば指摘される。ト長調のトリオは全体として穏やかで、低弦楽器の持続音により、どこか田園的な印象も漂う。
第4楽章 Allegro vivace 変ロ長調、ソナタ形式
楽章を通して舞曲のような軽快なモチーフで構成されており、こちらはハイドンの交響曲との類似性が指摘されている。
(Cb. K. W.)
ドヴォルザーク/交響曲第8番 ト長調
ドヴォルザークは、後期ロマン派のチェコの作曲家であり、スメタナと並びチェコ国民楽派の代表格とされる。ブラームスに才能を認められ国際的な人気作曲家となったこと、その後アメリカに渡り活動し、ネイティブ・アメリカンの音楽や黒人霊歌を作品に吸収したが、郷愁に駆られ帰国したことは、逸話として有名である。
一般的にドヴォルザークの作曲家としての特色は、ブラームスとともに標題音楽の支配する新ロマン主義の19 世紀後半において、「古典的な絶対音楽の形式を重んじながら、民族的な要素を結び付けたこと」が挙げられるが、一方でオペラや交響詩にも背を向けず、歌曲・宗教曲等、広範囲な創作を残している。どのような背景の中で、独自の作風を醸造させて行ったのか、生い立ちを追ってみたい。
―1841 年プラハの北部、北ボヘミア地方に生まれる。生家は肉屋と宿屋を営んでいたが、父はツィターを演奏し、民族音楽が周囲にある環境で育つ。小学校に通い始めヴァイオリンの手ほどきを受けると、アマチュア楽団のヴァイオリン奏者となり、音楽的才能を見せ始めたが、父親は家業を継がせるつもりであったため、12 歳で伯父の住むズロニツェという町へ肉屋の修業に行かせてしまう。ところが、この町の職業専門学校の校長は、教会のオルガニストや小楽団の指揮者を務め、教会音楽の
作曲も行う人物で、ドヴォルザークにヴァイオリン、ヴィオラ、オルガンの演奏の他、和声学をはじめとする音楽理論の基礎も教えることとなった。
その後、経済的な理由により、父親はドヴォルザークを退学させ家業を手伝わせようとしたが、伯父の援助により、16 歳でプラハのオルガン学校へ進むこととなる。
19 歳で卒業すると、ホテルやレストランで演奏する楽団のヴィオラ奏者を経て、新しく建設された国立劇場のオーケストラのヴィオラ奏者となる。この頃よりモーツァルト、ベートーベン、シューベルトの技法を学び、室内楽・交響曲の作曲を始めるが、楽団員として実地の音から学び、独学で作曲技術を獲得していく。
またオペラの分野についても、オーケストラピットの中でチェコ国民オペラの誕生に立ち会う中で、創作意欲を高めていく(1866 年には国民劇場にスメタナが指揮者として着任、歌劇「売られた花嫁」の初演には、ヴィオラ奏者として参加している)。ただし、専ら興味を覚え、影響を受けたのはワーグナー作品であった。
作曲に専念するために劇場の職を辞したのは30 歳のときであり、その後、33 歳で教会オルガン奏者の職を得、さらにオーストリアの国家奨学金を受け、金銭的に余裕もできる(当時ボヘミア地方が政治的にハプスブルク帝国の属国下にあり、チェコ人も奨学金の適用対象となった)。
何より、審査員であったブラームスの知遇を得たことの影響が大きく、作風の面でもワーグナーの影響からも脱していく。以後、ドヴォルザークはブラームスの支援を受け、国際的な作曲家としての一歩を踏み出すこととなる。かくして、円熟期のドヴォルザークは、ベートーベン、シューベルトなどの古典音楽に育まれた音感の上に、夢中になったワーグナーの語法、ブラームスから直接学んだドイツ音楽の構成法、幼児(幼時?)から身に着けた民族的な舞曲や民謡の色彩感、それらのものを渾然と消化していったのである。
本日演奏する交響曲第8番は、多忙な音楽家として活躍するなか、1889 年48 歳の夏から秋にかけて、別荘の田園生活のなかで構想を得て作られた。ブラームスの模倣から距離を置き、独自のボヘミア色に溢れている。
1890 年2 月2 日プラハでの初演は、ドヴォルザーク自身によって行われ大成功を収めた。
第1楽章 Allegro con brio ト長調
チェロによる短調の美しい序奏で始まり、フルートによる第1主題から主部となる。副主題は2
つあり、展開部、再現部を経て、最後はト長調で明るく終わる。
第2楽章 Adagio ハ短調
弦のやわらかい旋律で始まる。不規則な三部形式をとり、随所に小鳥の鳴き声のようなフレーズ
が現れる。最後は明るくハ長調で終わる。
第3楽章 Allegretto grazioso ‒ Molto vivace(加えてOK ?) ト短調
美しい旋律で始まるワルツ風の舞曲。中間部の旋律は、歌劇「がんこな連中」からとられたもの。
ト長調・4拍子となる力強いコーダもまた同じ素材をもとにしている。
第4楽章 Allegro ma non troppo ト長調
主題と18 の変奏。トランペットの輝かしい序奏に続いてチェロが主題を奏でる。変奏曲を交響曲の終楽章に持ってくることは、ドヴォルザークの交響曲の中ではこれが唯一である。
(Va. H. S.)
パリー/ブラームスへの哀歌
英国の作曲家というと、多くの場合ホルストやエルガーを思い浮かべるであろう。しかしパリーについて調べてみると、彼らに引けをとらぬ偉大な功績を残していることがわかる。
1848 年に生まれたパリーは、若かりし頃保険会社として知られるロイズに勤務していたが、1884年にロンドン王立音楽大学の創立と同時にその教授に迎えられ、1894 年には学長に就任、その後オックスフォード大学音楽科の教授も兼務。ヴォーン・ウィリアムズやホルストらを育てた教育者であるとともに、その力強い作風はエルガーにも影響を及ぼしており、近代イギリス音楽界の礎を作った作曲家であると言えよう。
彼は5つの交響曲、ピアノ協奏曲、多くの室内楽曲や声楽曲、音楽に関する数々の著作や論文を残している。ワーグナーと親交があったものの、その作風はドイツ・ロマン派においても特にブラームスの影響を受けたとされる。実際に、交響曲の5番を聴いてみると、やはりその響きは純粋なイギリス音楽ではなく、ブラームスの面影が多くの場面で感じられる。また晩年の作品であるオルガン伴奏による聖歌「エルサレム」は、エルガーの編曲によるオーケストラ伴奏版が、ロンドンで毎年開催される「プロムス」の最終夜に国家とともに必ず演奏されており、英国では誰もが知る彼の代表作である。
そして本日演奏する「ブラームスへの哀歌」は、彼が最も尊敬していたブラームスが没した1897年に作曲されたもので、特に展開部におけるクラリネットによる美しい旋律や、ドイツ的ともイギリス的ともとれる、終結部の響きが印象的である。なお、本作品はパリーの生前に演奏されることはなく、1918 年の彼自身の追悼コンサートにおける演奏が初演となった。 (K. T.)
ダルベール/チェロ協奏曲 ハ長調
「オイゲン・ダルベール(Eugen d’Albert)」とは、不思議な名前である。彼はスコットランドで生まれ育ったというが、「オイゲン」という響きはいかにもドイツ風、「d’Albert」というつづりはいかにもフランス風である。ドイツ音楽の演奏で名演を残した大ピアニスト、ウィルヘルム・バックハウスが師事したのが他ならぬダルベールであるが、ではそのダルベールが書いた音楽とは?ドイツ的なものを体現した作品なのだろうか?否、スコットランドで生まれたフランス風の名前の人間が、緊密な構成の曲を書くのだろうか?気になるところであるが、彼のチェロ協奏曲に触れる前にまずはその生い立ちを紐解いてみよう。
ダルベールは1864 年にスコットランドのグラスゴーに生まれた。作曲家である父はドイツ生まれのイタリア系フランス人、母はイングランド人である。幼少期から独学で音楽を学んだ彼は神童と称され、ロンドン王立音楽院に入学した。奨学金を得てウィーンに留学した1881 年にはハンス・リヒターの紹介でフランツ・リストに出会い、翌年からワイマールでリスト門下となる。その後、ピアニスト・作曲家として活躍し、1932 年に67 歳で亡くなった。ドイツ移住後に彼はドイツの文化、音楽に親和性を感じ、自らをドイツ人であると宣言した。私生活では6度の結婚を経験するという波乱に満ちた生涯だったようで、強烈な個性と激情を秘めた人物像が浮かんでくる。
ピアニストとしての彼は幅広いレパートリーを持ち、 中でもベートーベンやリストの評価が高かった。師であるリストのみならず、ブラームスもその才能を認めていたという。劣悪な音質ではあるが、彼が演奏したベートーベンやリスト、ショパン、さらには彼にとっては現代音楽であったドビュッシーの録音が今に残されている。作曲家としての彼は多産であった。現在では演奏される機会は少ないが、交響曲や協奏曲を含むピアノ曲、室内楽や歌劇など多くの作品を残している。彼の唯一のチェロ協奏曲は1899 年に作曲され、名チェリストのフーゴ・ベッカーに献呈された。今日では演奏機会が減ってしまったが、かつてはチェリ
ストにとって重要なレパートリーであったという。
この作品は全曲が切れ目なく演奏される形をとっており、シューマンのチェロ協奏曲からの影響をうかがわせる。曲はまずAllegro moderato で始まり、独奏チェロの分散和音を背景にオーボエが魅力的な旋律を歌い始める。この第1主題はクラリネットに引き継がれた後、ようやく独奏チェロに渡される。
この協奏曲が、独奏の技巧に焦点を当てるというよりは、独奏とオーケストラを一体として扱うという性格を有していることがこの冒頭部分から早くもわかるだろう。中間部のAndante con moto は別世界の音楽である。夢見るような旋律を、またしても独奏者に先立ってオーケストラが提示するところから始まる。曲想は次第に盛り上がり、上昇への意思を見せるような音階の連続、そして沈潜。音楽はtranquillo となり、天上に昇華するようなフレーズが奏されると、突如Allegro vivace に突入する。嵐のような音楽が過ぎ去ると全曲の冒頭部分が回帰し、力強く全曲を締めくくる。
彼の生い立ちに由来しているのだろうか、筆者はこの作品に(切れ目なく演奏されるという点以外にも)シューマン的な要素やイギリス音楽の要素など様々なものを感じる。皆さんはどうお感じになるだろうか? 本日の演奏を楽しみにしていただきたい。 (M. Y.)
ブラームス/交響曲第1番 ハ短調
「僕の交響曲は長ったらしくて、その上ちっとも愛すべき作品ではないんだよ」(カール・ライネッケへの手紙より)
ブラームスの最初の交響曲は、20 年以上に及ぶ構想から産み出されたものであることはあまりにも有名である。
北ドイツ(当時の国名は「プロイセン」)の港町・ハンブルグの貧民街に生を受けたヨハネス・ブラームスは、弱冠ハタチにしてシューマンの熱烈な歓迎とプレッシャーを受けつつも、「ドイツ(語の)・レクイエム」により国内外の知的階級の期待に応えた(33 歳)。「ハンガリー舞曲集」の興行的大成功を経た1872 年には39 歳の若さでウィーン楽友協会の芸術監督に就任していることからも、社会的にも経済的にも充分な地位を得た稀有な音楽家となっていたことがうかがえる。
「長すぎる」作曲期間にまつわるエピソードがあまりにも有名であり、楽聖・ベートーヴェンが打ち立てた「交響曲」という名の金字塔に相対する精神的闘
争や、苦悩からの勝利・解放へ、といった先入観とともに語られがちなこの曲だが、実際に通して聴いて(演奏して)得られる印象はやや異なったものである。
既に楽壇において揺るぎない地位を占めていた青年ブラームスにとって(写真参照)、交響曲の発表は「満を持して」のものであったに違いない。
第1楽章
冒頭、全管弦楽(in Es ホルン2本、トロンボーン除く)により開始される序奏(Un poco sostenuto)では、ティンパニ、コントラバス、コントラファゴットによるC 音の連打が印象的であるが、弦楽器の上昇進行と木管楽器の下降進行とがぶつかり合う緊張感もまた推進力となっている。Allegro となる主部ではヴァイオリンに第一主題が出るが、次第に運命的な動機「タタタ・ター」の支配力が強くなる。
コーダではやや速度を落としながらも序奏よりはやや早く(Meno allegro)、長調に転じた第一主題が穏やかに結ばれる。初演当初、コーダは冒頭と同じくpoco sostenuto であったが、あまりにも「遅く」演奏されてしまうことを恐れ、速度記載が変更されたという。なお、この楽章の草稿は1862 年の段階でシューマン未亡人(嫌な言葉だが)クララに送られている。
第2楽章
柔らかくあたたかいホ長調。哀愁を纏うオーボエによって謳い上げられる旋律を、クラリネットがたゆたいながらも受け流すが、ついには交響曲史上前代未聞ともいえるオーボエ、ホルン、さらには独奏ヴァイオリンのトリオ・ソロによる直球勝負となる。愛するもの、あるいはかつて愛したものへの憧憬、か。
第3楽章
変イ長調。メヌエットでもスケルツォでもないun poco Allegretto e grazioso。前楽章に続きつつも、ややそっけない「うつろい」がたまらない。
第4楽章
弦楽器によるピッチカートが特徴的な序奏に続き、アルプホルン(アルプスの角笛)に由来するとされる雄大なホルンの旋律が現れる。歌はフルートに引き継がれ、ここまで温存されてきたトロンボーンによるコラールの響きを導く。人間目線から 「聖なるもの」 への遷移だろうか。続いて第九『歓喜の歌』 主題をまざまざと想起させる主題が導かれ、ベートーヴェンとの比較を確信犯的に聴き手に強いる。コーダではコラールが再現され、力強く曲を閉じる。
頑迷とも捉われかねないほどに徹底された構成美と、あこがれの発露とも思える剥き出しの感情とが等しく内包され、対立しつつも高次元に昇華された作品であるとは言えないだろうか。
「彼は人間を愛し、また求めていましたが、他人が彼を求めたときには自分の殻に閉じこもってしまうのです。彼は与えることが好きでしたが、自分に対する要求や期待は撥ねつけました」(シューマン夫妻の遺児、四女・オイゲーニエによるブラームスへの回想より)
*
かつてブルーメンでは第12 回( 1998年) ~ 17回定期( 2000年) の4回にわたり「ブラームスチクルス」と銘打って演奏会を行い、その後もドイツ・レクイエム、管弦楽曲のほか、「2番」「4番」は再演の機会にも恵まれた。創立20 周年には幸いにもベートーヴェンの「第九」をとりあげることもできた。当時のチクルスを経験したメンバーは約15 年を経た今も少なくなく、かつ、多くの新しい仲間を迎えたオーケストラとしてこの曲をふたたび演奏できることは極めて喜ばしい。「いぶし銀」などと称されることもある彼の作品には、確かに若かりし頃には気づけなかった「なにか」が含まれているようだ。斜に構えがちな若者はそのような「容易に解釈できないもの」に惹かれるのかもしれない。いまやすっかり「第1番」作曲当時のブラームスと同年代となり、「お○゛さん」の呼称をもはや免れられない者として、「与えられた」音符に刻み込まれたものをそれぞれの「想い」として表現できれば幸いである。
参考文献 ・新潮文庫 カラー版 作曲家の生涯『ブラームス』 三宅幸夫
・音楽之友社『ブラームス、4つの交響曲』 ウォルター・フリッシュ(天崎浩二/訳)
(I. T.)
C. P. E. バッハ生誕300 年記念、ラモー没後250 年記念
ラモー/歌劇「ナイス」より序曲、シャコンヌ
ジャン=フィリップ・ラモー(1683-1764)はJ. S. バッハ(1685-1750)やヘンデル(1685-1759)と同時代に活躍した後期フランス・バロックの巨星である。1722年に音楽理論書として『和声論』を発表し、その2年後には「クラヴサン曲集」を発表して音楽理論家およびクラヴサン(チェンバロ)奏者としての地位を確立した。1733年、齢50にして初めて上演したオペラ「イポリートとアリシ」は大成功をおさめ、以後81歳で没するまでに実に30もの作品を発表し、フランス・バロック・オペラの黄金時代を築いた。
「ナイス」はその中では15番目の作品にあたり、1749年にパリで初演された。スコアに「平和のためのオペラ(opéra pour la paix)」と記されており、オーストリア継承戦争の終結を祝うための曲とされている。ラモーの得意とする悲劇とはまったく異なる「英雄牧歌劇(pastorale héroïque)」のスタイルで作曲されたこのオペラは非常に寓話的で、例えばプロローグでタイタンに勝利するジュピテルなどは、ルイ15世の象徴だといわれる。
さて、ラモーの魅力は何といっても「音遊びの楽しさ」にあるように思う。細かい音の一つ一つに意味があり、うまく鳴らせば、まるで楽器が、そしてオーケストラ全体が生き物であるかのような響きが生まれる(まさに音で「生き物」を表現するような効果のあるシーンも)。本日お届けする序曲とシャコンヌでも、弦楽器、オーボエ、トランペット…楽器ごとの特性と違いを効果的に用いた楽しい表現が随所にちりばめられているので、ぜひ、耳と集中力を研ぎ澄まして楽しんでいただきたい。
今年で没後250年という一つの記念年を迎えるラモー。日本での演奏機会はまだ決して多いとはいえないが、本日の演奏によってラモーの持つ優雅さ、コミカルさ、お茶目さ、様々な魅力を感じ取っていただけたら幸いである。
(Vn. G. Y.)
C.P.E.バッハ/管弦楽のための交響曲 ヘ長調
管弦楽のための交響曲(シンフォニア)ヘ長調Wq. 183/3(H. 665)は匿名のパトロンの依頼により1776 年に作曲され、1780 年に出版された作曲家後期の作品である。C. P. E. バッハの初期の頃の作品はイタリア様式の器楽曲が多い。また、作曲当初は弦楽器での合奏のために作曲され、後になってバッハ自身がトランペットやティンパニなどのパートを加えたものがある。パートの構成としては、ヴァイオリンはほとんどユニゾンで旋律を奏で、時にセカンド・ヴァイオリンが三度下の音でファースト・ヴァイオリンを支えるくらいであった。また、ヴィオラは通奏低音(チェロやコントラバスなどの低音声部)の旋律の1 オクターブ上を奏でる形で曲全体が作られていた。これに対し、後期の交響曲の特徴としては、上声部と内声部のそれぞれが独立したパートとして通奏低音に支えられる構成が多く、木管楽器のオブリガートパートも作曲時から曲に組み入れられている。これはバッハが、1770 年頃の新しい音楽様式の流行を取り入れたことを意味する。また、通奏低音のパートについては、後期の作品になるにつれて、旋律を支える単純な役割から、独立したパッセージを持つ声部へと変化していった。
シンフォニアWq.183/3 は、急-緩-急という構成を持つ、当時の北ドイツ地方でよく用いられた3 楽章の形式で書かれている。主題である旋律に、ヴァリエーションが加えられていく形で各楽章が展開されていく。第1 楽章は、弦楽器による力強いユニゾンで始まり、ヴァイオリンから通奏低音までが、走るように細かい16 分音符を奏でる。主要テーマは、ヴァイオリンや木管楽器による静かな旋律を間に挟みながら4 回繰り返される。どこかメランコリックな第2 楽章のラルゲットは、ヴィオラとチェロが互いに慰め合うようにメロディーを奏でることで始まり、それに他のパートが徐々に追従するように旋律が増えていく。楽章の最後はその憂いが漂い、それが解決しないまま第3 楽章の明るいプレストへ移り変わる。
第3 楽章においては、軽やかな旋律が始まるや否や、ダイナミックに2 つ目のテーマが登場する。転調やヴァリエーションを加えながら、最後は力強いユニゾンで幕を閉じる。
Wq. 183 として知られる4 つの交響曲は、バッハの死後、19 世紀から20 世紀にかけていく度も復刻版が出版されている。そしてこれらは、モーツァルトやハイドンによる作品を除き、18 世紀の交響曲としては珍しく、作曲家の生前から私たちが生きる現代まで広く演奏され続けている。
(Vn. N. S.)
C.P.E.バッハ/弦楽のためのシンフォニア ハ長調
--彼は独創的だ! 彼の作品すべてに、独創的という刻印が押されている(ヨハン・カスパル・ラファーター『観相学の断章』)
C. P. E. バッハの『自叙伝』(1773)には、最新作として「1773 年依頼に応えて6 つの四声のシンフォニアを作曲」との記載がある。これが「弦楽のためのシンフォニア」(Wq. 182, H. 657-662)であり、本日演奏するH. 659 はその第3 曲である。
依頼者のスヴィーテン男爵はバロック楽譜のコレクターであり、また自宅コンサートでこれらの音楽をモーツァルトら当時の音楽家に聴かせ、ウィーン楽友会を設立し、さらには自らも作曲するなど、多数の功績が現在でも知られるオーストリアのアマチュア音楽家である。本業は外交官であり、音楽にとどまらない多彩な教養は、貴族との交渉にも活かされていた。第1 次ポーランド分割(1772)交渉の成功後に作曲を依頼したと考えられる。
「何の制約もなしに、思いのたけ自由に」との要望通り、四声のシンプルな構成ながら、大胆なテーマ・新鮮な和声進行といったC. P. E. バッハらしい仕掛けが緻密に織り込まれている。バロック後の音楽の過渡期に現れた、時に過剰なほどの感情豊かな表現形式は、やがてハイドンやベートーヴェンらに受け継がれてゆくのである。
第 1 楽章:冒頭から強奏のユニゾンで独創的なテーマが奏でられ、その後も疾風怒濤のような旋律が続く。急に弱奏の旋律が一瞬現れたり、突然休止したりする。「ピアノでもハイテンション」(懸田氏談)。冒頭のテーマが再現されたかと思うと、休止なしに第2 楽章に突入する。
第 2 楽章:予想外の減七のドラマティックな和音の強奏から始まる。1 小節の弱奏をはさみ、さらに別の減七の和音が追い打ちをかける(ちなみに冒頭4 小節のバス声部はドイツ音名でB, A, C, H、「バッハのテーマ」である)。その後はヴァイオリンの二重奏とヴィオラの伴奏という三声構成で、半音階を用いた美しい旋律が奏でられる。所々で冒頭の減七の和音が現れ、そのたびに旋律は異なる変化を見せる。
第 3 楽章:ソナタ形式。弱奏と強奏が目まぐるしく入り乱れ、旋律ごとの対比を際立たせている。
(Cb. K.W.)
ハイドン/交響曲第 97 番 ハ長調
交響曲第97 番ハ長調は、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンが1792 年に作曲した交響曲であり、いわゆる「ザロモン・セット」あるいは「ロンドン・セット」と呼ばれる交響曲群の一つに位置づけられる作品である。ハイドンは、彼の音楽家としてのキャリアの長年に渡り仕えてきたエステルハージ家のニコラウス(ミクローシュ)侯爵の死去後、当時ドイツで活躍した興行主であったヨハン・ペーター・ザロモンの招きにより、1791年から1792 年、および1794 年から1795 年にイギリスを訪問している。この折に作曲・初演された第93 番から第104 番の交響曲群が「ザロモン・セット」であり、本作品の他にも交響曲第94 番「驚愕」や第100 番「軍隊」、第104 番「ロンドン」など、現代においてもハイドンの交響曲の中で最も人気のある作品が並ぶ。これらの作品は当時の観客にも非常に熱狂的に受け入れられたという。
交響曲第97 番は、ザロモン・セットの中にあって上述の副題付きの作品と比較すると必ずしも演奏機会に恵まれているとはいえないが、いかにもハイドンらしい創意工夫に満ちた作品である。充実したオーケストレーションで安定感のある構成の中に随所にみられるユーモアと、特に終楽章のジェットコースターのようなスリリングな音楽はさすがであり、ハイドン好きの人にとってもそうでない人にとっても、非常に魅力的な作品である。
第1 楽章:Adagio – Vivace ハ長調 3/4 拍子 序奏付きソナタ形式。緩やかな序奏部の後に、強烈なユニゾンで楽章を貫くテーマが提示される。
第2 楽章:Adagio ma non troppo ヘ長調 4/4 拍子 変奏曲形式(主題と3 つの変奏とコーダ)。途中の変奏で、ヴァイオリンに対し当時としては珍しいal ponticello の指定を付している。
第3 楽章:Menuet. Allegretto ハ長調 3/4 拍子 3 部形式のメヌエット。
第4 楽章:Finale. Presto assai ハ長調 2/4 拍子 ロンド・ソナタ形式。
(Hr. K.S.)
<インタビュー> ゲスト・リーダーの懸田貴嗣さんに聞きました
--今回のプログラムは、ブルーメンにとって新たな領域への挑戦となりますが、意義についてお伺いさせてください。
例えばベートーヴェンを演奏するときに、ベートーヴェンの語法が何なのかということを体系的に知る機会ってなかなかないと思うんです。それを知るためにはその前の時代の音楽を知ることが必要であって、そういう意味で例えばC. P. E. バッハとハイドンというのはベートーヴェンの音楽に非常に大きな影響を及ぼした作曲家ですし、ラモーもC. P. E. バッハもハイドンもそれぞれ独立した作曲家として18世紀においてきわめて重要な作曲家なので、それをきちんと一緒に取り上げるのは、18世紀後半から19世紀前半にかけてのオーケストラの語法を身につける上ですごく大事なことだと思います。
--作曲家の「縦のつながり」を意識したプログラム構成となりましたが、時代を越えた作曲家の関係についてもう少し聞かせていただけますか。
ハイドンは、18世紀当時大バッハよりも有名だったC. P. E. バッハを大変尊敬していて、私はC. P. E. バッハから大きな影響を受けていると自身で語っています。主に中期の「シュトゥルム・ウント・ドランク(疾風怒濤)」といわれている感情表現の激しい作品など、影響は明らかですね。ベートーヴェンはハイドンの弟子でしたが、ハイドンから学んだものは何もないと言ったと伝えられています。しかし例えば交響曲第1番などはハイドンの影響なしには考えられませんし、やはりハイドンの音楽のエッセンスをはっきりと引き継いでいると思います。
--フレンチバロックのラモーの曲が組み込まれているのも今回の演奏会の特徴ですね。
C. P. E. バッハ以前の音楽をやりたかったのです。今年はラモー没後250年のanniversary yearですし、彼の作品の中で「ナイス」の序曲は比較的取り組みやすい曲です。シャコンヌについては、みんなシャコンヌという名前は知っていると思いますが、どんな舞曲かは知らないという人も多いでしょう。そこで、バロック時代のシャコンヌを取り上げたときにみんながどう感じるか、どういう学びをするかというのも面白いと思いました。
--ハイドンの交響曲には懸田さんからの提案でフォルテピアノが加わりましたね。
一連のロンドン・セットでは、フォルテピアノのソロ部分が出てきたり(98番)、初演時にハイドン自身がフォルテピアノを弾きながら通奏低音と指揮を担当したり、とぜひオーケストラの中にいてほしい鍵盤楽器なんです。しかも今回それ以外の曲目はチェンバロが入りますから、2台も通奏低音のための鍵盤楽器を使うという、採算のとれない通常の興行ではありえない(笑)超豪華版です。
--古い時代の曲を演奏するとき、ヴィブラートをかけずに弾くというやり方もありますが、それについてはどのように思われますか。
ノンヴィブラート奏法というのは、ガット弦だからかける必要がないと感じる、もしくは音楽に対して必要ではないと感じるからかけないという内的な動機があるものです。そのような内的必然がなく、単にヴィブラートをかけないで弾くというのは、あまり意味がないと思います。
--西洋音楽の歴史の浅い日本では、今回のような曲目が演奏される機会は必ずしも多くありませんが、ヨーロッパの事情はいかがでしょうか。
ヨーロッパでは、古い音楽とロマン派の音楽は対等にプログラミングされています。その点はやはり西洋音楽の伝統の違いでしょうね。アマチュアのオーケストラは採算にとらわれず冒険できるのだから、古い音楽や現代音楽にどんどん取り組んでいってもよいと思います。
--懸田さんのような古楽の専門家にご指導いただきながら取り組むことができる今回の企画は、ブルーメンが良い方向へ向かうきっかけとなる
有意義な演奏会になりそうです。このたびは貴重なお話をありがとうございました。
ハイドン/交響曲第88 番ト長調「V 字」
ハイドンは1761年から1790年までの約30年間、ハンガリーの有力貴族であるエステルハージ家に宮廷音楽家として仕え、そこで数多くの、そして様々なジャンルの作品を残した。特に交響曲においては、常に大胆な作曲手法を試み、器楽の地位を高めることに成功した。
本日演奏する88番が作曲されたのは1787年とされている。これはちょうど「パリ交響曲(82~87番)」と「ザロモン交響曲(93~104番)」の間にあたり、おそらくハイドンがもっとも「ブイブイ言わせていた」時期でないだろうか。熱狂的ともいえる音楽愛好家であったエステルハージ家の君主から多量な作曲を依頼される、いわば「おかかえ宮廷楽長」だったハイドンの名声がひろくヨーロッパに轟き、外部からの作曲依頼が飛躍的に増加していたような頃のことである。
第1楽章は、雄大なアダージョの序奏からソナタ形式のアレグロへ導かれる。弦楽器によって第1主題が呈示され、小気味よく、しかし緊張感を保ちながら繰り返されていく。
第2楽章はオーボエとチェロの美しい重なりから始まる心地よいラルゴ。身も心も溶かしてしまいそうなその旋律に加え、中盤ではトランペット・ティンパニが独創的に用いられる。
第3楽章は装飾から始まる軽快で明るいメヌエット。途中、民族舞曲風のトリオには奇妙なバクパイプ風の効果があり、それにちなんでドイツでは88番全体が≪バクパイプ付き(mit dem Dudelsack)≫と呼ばれることも。なお日本で名の知れている≪V字(Letter V)≫という呼び名はイギリスの
出版社が付した整理用の番号がたまたまアルファベットの "V" だったからにすぎないとか。(私ははじめ、オーケストラの編成を上から俯瞰すると隊列がVの字に見えたりするのかしら、などとしょうもないことを考えていたが…)
第4楽章はアレグロ・コン・スピーリト。複雑に工夫が凝らされた、輝かしい響きを持った曲である。ソナタ=ロンド形式は美しく、高声部と低声部の弦楽器によってフォルティシモで次から次へとカノンが続いていく。属七の和音でいったん終結すると、なだれこむようにしてコーダに向かい、喜ばしいままに終わりを迎える。
≪戯れたり、興奮させたり、笑いをひきおこしたり、深い感動をあたえる、といったようなことを、ハイドンほどうまくできる人はだれもいません≫
ハイドンと親交の深かったモーツァルトは、1781年から1785年の間に作曲した6つの弦楽四重奏曲(いわゆる「ハイドン・セット」)を献呈する際、そう語ったという。この88番も、まさにそんな曲ではないだろうか。
(Vn. G. Y.)
モーツァルト/オーボエ協奏曲ハ長調
この作品は、1777 年、モーツァルトが21 歳のころに作曲されたものといわれる。当時モーツァルトは、故郷ザルツブルクで、貴族の庇護のもと宮廷音楽家という安定した身分を与えられ、明るく快活な作品を多く生み出していた。しかし、幼少期から父に連れられてウィーン、パリ、ロンドンなどで最先端の文化に触れ続けてきた彼にとって、人里離れた山中にある田舎町のザルツブルクでは物足りなかったのだろう。この年の9月、モーツァルトは宮廷音楽家を辞め、活躍の場を求めて故郷を去っていく。
この作品は、モーツァルトが書いた唯一のオーボエ協奏曲である。世界で最も有名なオーボエ協奏曲であり、今日ではコンクールやプロオーケストラの入団試験でも必ず課題にあげられる曲となっている。巷でオーケストラブームを巻き起こした漫画「のだめカンタービレ」の中でも、普段は武士然と渋い演奏をしていたオーボエ奏者の黒木くんが、のだめに恋して“ピンク色”の演奏をするという場面で使われていた。こうした人気ぶりからは信じられないことだが、この作品の楽譜は長い間行方不明であり、20 世紀に入り発見されてようやく陽の目を見ることとなったのである。
さて、オーボエの魅力といえば何よりその柔らかく深みのある音色にある。加えてこの作品では、華やかな明るさ、軽やかさ、伸びやかさ、優美さなど、オーボエの持つ様々な魅力を存分に味わうことができるだろう。技巧的な部分の多い難曲でもあるが、そこを重苦しく聴かせないところは、さすがモーツァルトである。
本日は、日本屈指のオーボエ奏者である古部賢一氏のオーボエ独奏兼指揮により、オーボエの魅力を満喫していただきたい。各楽章最後のカデンツァ(即興独奏)もお楽しみに。
第1 楽章:Allegro aperto ハ長調 4/4 拍子
協奏風ソナタ形式。オーケストラ伴奏により2 つの主題が提示された後に、オーボエが単独で2 つの主題を演奏する。短い展開部、続く再現部
を経て、カデンツァで終章する。
第2 楽章:Adagio non troppo ヘ長調 3/4 拍子
ソナタ形式。オーケストラ伴奏による序奏の後、オーボエ独奏により2 つの主題が提示されるが、展開部と第1主題の再現を欠くまま第2 主題のみ再現されて、カデンツァで終章する。
第3 楽章:Allegretto ハ長調 2/4 拍子
ロンド風ソナタ形式。冒頭でオーボエ独奏による第1 主題が提示され、第2 主題が演奏された後、これら主題が交互に繰り返されて、カデンツァで終曲する。
(Ob. K. S.)
シューマン/交響曲第3 番変ホ長調「ライン」
1850 年9 月2 日、ロベルト・シューマンはフェルディナント・ヒラーの推薦によってデュッセルドルフ市の音楽監督に就任し、ライン川湖畔の同市に転居した。9 月29 日には妻クララ・シューマンと共にライン川を遡ってケルンに旅をしており、クララの日記にもこの町の観光を楽しむ様子が記されている。
29 日の日曜日、私たちはケルンへと気分転換の旅に出た。ドゥーツの初めの景色からすっかり魅了され、とりわけ大聖堂の壮麗さは素晴らしく、より近くから見るとそれは、私たちの期待をさらに上回るものだった。…(中略)…私たちは見晴らし台へと行った。そこからのラインの眺めも本当に美しいものだった。…
夫妻は11 月4 日から6 日までケルンを再訪しているが、この旅とラインラントの町から受けた印象が変ホ長調の交響曲につながったとされ、「ライン」の名前で呼ばれている(シューマン自身はこういう表題はつけなかった。この呼称も没後のものである。しかし、シューマン自身もN.ジムロックへの手紙でラインラントの生活の様々な姿が作品の中に映し出されていることを認めている)。1248 年から建造が開始されたケルンの大聖堂は19 世紀になっても完成しておらず、高々とそびえる塔は未完成だったが、壮大なドームがシューマンにどのような感想を抱かせたかは、クララの日記や第4 楽章(後述)から想像に難くない。5 楽章からなるこの交響曲のうち、2 つの楽章には当初叙述的なタイトルがつけられた。スケルツォの「ラインの朝」、第4 楽章の「荘厳な儀式の伴奏の性格にて」がそれである。後にシューマンは「自分の心象をあらかじめ公にする必要はない」との理由からタイトルを取ってしまうが、この交響曲とラインラントとの深い関係を見ることができるであろう。また、作曲は1850 年11 月2 日に着手され12 月9 日に完成したが、11 月12 日に執り行われたケルンのヨハネス・フォン・ガイゼル大司教が枢機卿に承認された際の祝典に触発され、第4 楽章が書かれたといわれており、トーヴェイはこれを「対位法を用いた教会音楽としてはバッハ以降、最高の作品」と評している。
初演は完成翌年の1851 年2 月6 日、シューマン自身の指揮によってデュッセルドルフで行われ、同月25 日にはやはりシューマンの指揮でケルンで演奏されている。
第1 楽章
ソナタ形式で書かれたこの第1 楽章は、序奏部なしに全楽器の強奏で力にあふれた第1 主題で始まり、ライン川の雄大さをイメージさせる。95小節目から第2 主題がト短調でオーボエとクラリネットによって現れる。第2 主題を中心とした長めの展開部を経て、ホルンによる第1 主題を契機に演奏は徐々に力を増し再現部に突入する。
第2 楽章
スケルツォと名付けられているが、素朴な民俗舞踊曲風で形式としてはロンド風である。ここでも第1 楽章の主題が浸透し、その明るさと確実さが晴れやかな気分を保たせている。
ライン川沿岸ののどかな風景を彷彿とさせる。
第3 楽章
木管楽器の優しくあたたかな主題で始まり、付点リズムで上下する音型と優美な旋律が交錯する。全楽章の間奏曲のような位置付け。
第4 楽章
ホルンとこの楽章で初めて登場したトロンボーンによる主題により第1 部が始まる。多声部にテーマが出てくるため、大聖堂に響き渡るような宗教的な雰囲気がある。第2 部では主題がカノン風に扱われ派生音型が展開される。第3 部は一層壮麗になり、弦のトレモロにのって主題が壮大に復帰し、オルガン風の和声が響くうちに終結する。
第5 楽章
ソナタ形式による晴朗な楽章。明快な低音部の動きに乗って秋の収穫祭を思わせる主題から始まり、ところどころに響く金管楽器などのファンファーレが祝祭的な気分を盛り上げる。第2 主題は控えめで、展開部に第4 楽章の主題が加わって総合されていく。ホルンによる上昇音型が現れて高潮し、再現部となる。ファンファーレが出てきた後、テンポアップしてコーダに入り、輝かしくも賑やかに終盤を迎える。
(Hr. N. K.)
ベートーヴェン/「レオノーレ」序曲第3 番
一切の光も届かぬ秘密の地下牢、そこに無実の罪で投獄されているフロレスタンは、レチタティーヴォで悲痛な叫びをあげたのち、アリア「人生の春の日に」を歌う──ベートーヴェン唯一のオペラ『フィデリオ(レオノーレ)』第2 幕のこのような冒頭シーンをなぞるかのように、「レオノーレ」序曲第3 番の序奏でも、ユニゾンによるショッキングな強奏から、聴き手を地下深くへといざなうかのようなゆっくりとした下降音型ののち、このアリアの冒頭部分が引用される。ソナタ形式の主部の第2 主題にも使用されるこのアリアは、絶望の淵にあるものの嘆きとは思えないほど悲痛さとは程遠い温和で穏やかな音調にあふれているが、それはまさに自らの正義のために殉ずるというフロレスタンの高潔な精神を、ベートーヴェンが鋭い筆致で描き出したものにほかならない。
『フィデリオ』のストーリーはさらに以下のように進む──悪徳刑務所長ドン・ピッツァロの悪事を大臣に告発しようとして逆に囚われてしまったフロレスタン。その妻レオノーレは男装しフィデリオと名乗り、ピッツァロのもとで下働きをしながら夫を救出するチャンスを狙う。ピッツァロは大臣が刑務所へ視察に来る前にフロレスタンを殺してしまおうとするが、レオノーレは身を挺して夫をかばう。絶体絶命のその時、大臣の到着を知らせるトランペットが高らかに鳴り響き・・・かくしてピッツァロの悪事は暴かれ、フロレスタンの正義と、レオノーレの夫への愛が謳われ、歌劇は大団円を迎える──この、フロレスタンとレオノーレの窮地を救う「デウス・エクス・マキナ(機械仕掛けの神)」としてのトランペットもまた、序曲のちょうど真ん中に引用されている。序曲全体がオペラの第2 幕を凝縮し、予感させるような構造になっているのである。
演奏会の序曲として取り上げられることの多いこの「レオノーレ」序曲第3番だが、こうして劇中のアリアとファンファーレの意味を踏まえてみると、堂々たるハ長調の部分もいっそうの力強さをともなって響いてくるのではないだろうか。
(Perc. W. N.)
モーツァルト/ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調
ヴァイオリンとヴィオラのための協奏曲
コンチェルト
風たちが奏づるよ水無月/永井陽子『小さなヴァイオリンが欲しくて』
モーツァルトをこよなく愛した永井陽子の歌。のっけから短歌の引用で恐縮だが、この曲は私にとってまさに「風」が舞う曲。風がさっと吹くように始まり、風に乗って空を飛んでいくような、のびやかで軽やかな曲である。
この曲はモーツァルト23 歳、1779 年の夏に作曲された。それはモーツァルトにとって、どのような時期だったのだろうか。
この2 年ほど前から、モーツァルトは旅に出ていた。アウグスブルク、ミュンヘンなどを経て、マンハイムとパリに滞在。安定した収入と就職先を求めての長旅だったが、これといった成功もなく、やりがいのある職も得られなかった。しかも、つきそってくれていた母が旅行中パリで病死。悲しみのうちにパリをあとにし、帰国途上で立ち寄ったマンハイムでは恋人の心変わりを知る。母の死と失恋という大きな挫折と喪失を経て、悄然とザルツブルクに帰ってきたのが、この1779 年1 月だった。
帰郷すると、モーツァルトは、父が用意したザルツブルクの宮廷オルガニストという新しい就職先におさまった。当時のモーツァルトの暮らしぶりは、姉や友人の日記に記録されているが、職務以外は散歩したり、友人と室内楽やカード遊びをしたり、平穏で刺激の少ない毎日だったようだ。
さて、そんなもぬけの殻のような時期であるが、当時の作品にはマンハイムやパリの影響が色濃くあらわれていると言われており、傑作も多い。
この協奏交響曲(シンフォニア・コンチェルタンテ)という形式自体、当時マンハイムやパリで流行していたものなので、この曲はモーツァルトの旅土産と言ってもよいだろう。「協奏交響曲」とは、複数の独奏楽器を擁した協奏曲のこと。それぞれの楽器の特性をいかした複数楽器の独奏とオーケストラの協奏は、聴いていてとても楽しい。
なお、モーツァルトはこの曲で、独奏ヴィオラに、半音階高く調弦する指示を残している。弦の張力を強くすることで音色を明るく華やかにするため、と言われているが、本日はこの方法を用いず、普通の調弦で演奏する。ヴァイオリンほどの明るさはないが、穏やかで優しい本来のヴィオラの音と、華やかなヴァイオリンの音の協奏を楽しんでいただきたい。
第1 楽章 Allegro maestoso
堂々とした第1 主題、牧歌的な第2 主題が演奏され、力強いコーダとなったあと、オクターブでふわりと浮き上がるように独奏楽器が登場。2
つの独奏楽器は、万華鏡のように少しずつ色を変えながら交互に歌い、活発な応酬を経て、最後は輝かしく集結する。
第2 楽章 Andante
深い憂いと悲しみをたたえた楽章。独奏楽器が慰めあうように対話する。途中少し光がさすが、すぐ短調に戻る。
第3 楽章 Presto
一転して快活なロンド。独奏楽器の丁々発止なかけ合いは、いたずらを競い合う子どものよう。いきいきと弾むように進んでいき、コーダで独奏楽器のかけ合いが頂点に達すると、曲は多幸感に満ちたまま華やかに閉じられる。
(Vn. S. H.)
シューベルト/交響曲第8(9)番ハ長調「ザ・グレート」
【番号】
シューベルトの7 番目以降の交響曲には、生前には番号が付与されず、番号の扱いが様々である。この交響曲は20 世紀初頭までは「第7 番」と呼ばれ、20 世紀半ばに作成された作品目録では9 番目、そして20 世紀後半に改定された目録では8 番目であり、国際シューベルト協会では「第8番」としている。現在では昔の通称との混乱を防ぐために「第9 番」との併記が多く、今回のプログラムでは「第8(9)番」と記載している。
【副題】
通称「ザ・グレート」と呼ばれている。シューベルトは他にもう一つハ長調の交響曲第6 番を書いており、後世になって区別するために「大きいほうの」ハ長調の交響曲と呼ぶようになったため、この呼び名がついた。
このようにもともとは第6 番に比べて大きいという程度の意味しか持っていなかったが、曲自体はその名にふさわしい曲想や規模を持っている。
指示通りに演奏すると1 時間以上かかる大曲であり、現代では珍しくないが、19 世紀前半においては通常想定される枠をはみ出た存在である。
【初演】
作曲は、1825 年頃と言われている。シューベルトはウィーン楽友協会へ提出したが、長すぎるとの理由で当時は演奏されなかった。
シューベルトの死後の1839 年に、その部屋を管理していたシューベルトの兄フェルディナントの元へシューマンが訪れ、自筆譜を確認した。そしてシューマンの友人メンデルスゾーンの指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏によって初演された。
【天国】
シューベルトは「歌曲の王」として知られている。この交響曲においても、全編に渡って美しい旋律を綴っている。シューマンは「天国的長さ」と評したが、単に長いのではなく、単なる繰り返しでもなく、美しい旋律が「天国のように」どこまでも続いているのである。その美しさをあげればきりがない。弦楽器はもちろんのこと、1 楽章・2 楽章の両楽章とも冒頭から2 フレーズ目を担当するオーボエ、2 楽章中間つなぎの部分のホルンなど。
特に同時代の他の曲に比べて目立つ点は、「神の声」とも言われるトロンボーンの多用である。天使となり悪魔となり、あらゆる箇所にその姿を現す。
【影響】
ベートーヴェンから影響を受けていることは想像に難くない。前年1824 年の作である交響曲第9 番からは、トロンボーンの活用、そして主題の引用など明らかな関連がある。一方、シューマンは自筆譜を確認した翌々年1841 年に交響曲第1 番を作曲、初演を指揮したメンデルスゾーンは翌年1840 年に交響曲第2 番を作曲しており、これらへの影響が想像される。
【楽章】
第1 楽章 Andante – Allegro ma non troppo
序奏は、遠くから鳴るホルンのユニゾンによるテーマから始まる。続いて木管、弦楽器と受け渡され、そしてトロンボーンを中心として最前面にテーマが押し出される。主部は付点のリズムによる主題、物哀しい主題、トロンボーンによって提示される力強い上昇音形の主題があり、それぞれに3 連符を絡めて構成される。
第2 楽章 Andante con moto
スタッカートを特徴とする動機を持つ主題A と、下降音形のレガートを主体とした主題B とによる、ABABA の形式である。1 回目の主題B から2 回目の主題A へのつなぎの部分のホルンは、シューマンが「天の使い」と評した美しさである。
第3 楽章 Scherzo Allegro vivace
同時代としては大掛かりな、スケルツォ楽章である。力強い主部とシューベルトらしい歌で綴られるトリオとで構成されている。
第4 楽章 Finale Allegro vivace
自由なソナタ形式によるフィナーレである。1 楽章と同じく付点のリズムと3 連符の組み合わせで構成される。天国的と称される交響曲の締めに相応しく、ソナタ形式を基本としながらスケールを大きくした構成となっている。ベートーヴェン交響曲第9 番の歓喜の主題を改変して引用しており、ベートーヴェンに対するオマージュと考えられている。
【今日】
ドイツ古典からロマン派を中心として活動してきたブルーメンの、20 周年の記念に相応しい曲である。指揮者を踊らせるような第3 楽章・第4
楽章は、第1 楽章・第2 楽章でじっくり旋律を歌った後でこそのものである。「ザ・グレート」という副題とは相反する、「短すぎる、まだ聴いていたい」という気持ちを、ホール全体に満たしたい。
(Hr. M. S.)
武満 徹/弦楽のためのレクイエム
武満 徹(1930-1996)は20世紀の日本の作曲界で国際的に成功した作曲家のひとり。65年間の生涯を閉じたのが1996年2月20日。現在を生きる我々とも時を重ねている作曲家である。
本日演奏する「弦楽のためのレクイエム」は、タケミツの初期の作品である。1957年5月に東京交響楽団からの委嘱により作曲され、同年6月20日に日比谷公会堂で東京交響楽団の第87回定期演奏会にて上田仁指揮により初演された。当初国内での評価は決して芳しいものではなかったが、1959年に来日中のストラヴィンスキーの耳に留まり Very Intense との評を得たことを機に状況が一転。タケミツの名と作品はアメリカそしてヨーロッパへと広まっていき、ニューヨーク・フィル125周年記念委嘱作品『ノヴェンバー・ステップス』などで国際的な成功を収めるに至る。また、タケミツの作曲の幅はオーケストラ作品のみにとどまらず、勅使河原宏監督「利休」などの映画音楽、テレビ番組、コマーシャルなど多岐に渡っている。
さて「弦楽のためのレクイエム」。レクイエムという曲名がつけられているが、伝統的なレクイエムの形式ではなく、単一主題による、レント-モデラート-レント という自由な三部形式で構成されている。この曲の解説にはタケミツ本人の言葉が最も相応しいと思われるので、一文を引用させていただく。
「はじめもおわりもさだかでない、人間とこの世界をつらぬいている音の河の流れの或る部分を、偶然に取り出したものだといったら、この作品の性格を端的に明かしたこととなります」
我々は三次元の空間と一次元的な時間の流れの中で生きている。しかし、それぞれがこの実在空間とは別の次元で精神世界を持っている。タケミツが偶然に切り出した音の河は、精神世界を絶え間なく流れている音ではないかと。みなさまの音の河はいかなるものでしょうか?
我々の演奏を通じて譜面から浮かびあがるタケミツの音の河。みなさまそれぞれにも何かを感じていただければ幸いである。
シューベルト/交響曲第4番 ハ短調 「悲劇的」
シューベルトの歌曲は、親しみやすい『野ばら』や『音楽に寄せて』の他、『魔王』のように劇的なものや『セレナーデ』のように叙情的なもの、さらには『菩提樹』を含む連作歌曲『冬の旅』等々、有名なものだけでも挙げてもきりがないほど多くの名作にあふれている。そして31年というあまりに短い一生の間に書かれた歌曲は600をゆうに超え、その膨大なレパートリーは、繊細で美しい旋律と妙味に満ちた伴奏とによって、魅力あふれるドイツ・リートの世界を紡ぎ出しており、「歌曲王」の名にふさわしい足跡を音楽史上に残した。もちろんこれら歌曲の持つ叙情性はそのまま器楽曲や管弦楽曲にも通底しており、シューベルトの音楽全体の大きな魅力となっていることは言うまでもない。
1797年ウィーンに生まれ、幼いうちからその音楽的才能を発揮していたシューベルトは、11歳にはすでに親元を離れコンヴィクトと呼ばれる王立寄宿制学校へ入学し、かのサリエーリのもとで作曲を学んだ。そして1813年に16歳でコンヴィクトを去ったのち、初等教員養成学校へ1年ほど通い、父が校長を務める学校で教師の職につく。そして数年の間そこで教鞭を執るかたわら、いつかはモーツァルトやベートーヴェン、あるいは師サリエーリのような大作曲家になれることを夢見て作曲にいそしんでいた。この頃のシューベルトの並々ならぬ意欲は膨大な創作量となってあらわれている。とくに1815年には『魔王』や『野ばら』を含む145の歌曲をはじめ、数々のピアノ曲の他、交響曲2曲やミサ曲2曲なども作曲されたが、なかでも注目すべきはこの年に4つもの劇場作品が書かれていることである。「歌曲王」としての多大な成果の陰に隠れてしまいがちであるが、シューベルトには生涯にわたってオペラあるいはジングシュピールの作曲家としての成功も夢見つつ、結局叶えることができなかったという側面もあったことを見逃してはならない。
さて、今回演奏する『悲劇的』交響曲はその翌年である1816年に書かれたものである。当時のシューベルトが「オペラがダメなら交響曲で勝負だ!」と考えていたかどうかはわからない。しかし自ら総譜に「悲劇的」と書き込んだこの交響曲は、モーツァルトやハイドン、そしてベートーヴェンを範と仰ぎつつ、立派な交響曲を書き上げようという若きシューベルトの意気込みにあふれている。とくに、楽章および旋律を短いモチーフの積み重ねによって構成しようとする意図が明らかであるほか、楽章間に連関を与える工夫として、第一楽章主要主題と第二楽章副次主題、そして第三楽章のトリオが、すべて同じモチーフで開始されている。また他方で、楽器同士の対話や情景描写的な伴奏など、交響曲というよりはむしろオペラを念頭に置いているような書法も随所にあらわれており、シューベルト自身のオペラへの強い関心や、かつての大オペラ作家サリエーリからの強い影響も見受けられる。
第一楽章:アダージョ・モルト-アレグロ・ヴィヴァーチェ 重苦しく沈鬱な序奏がやや長めに続いたのち、憂いを含んだメランコリックな主要主題が弦楽器によって奏される。副次主題は明るく伸びやかだが、そのかげで休むことなく刻む伴奏は安らぎを拒むかのようである。全体にモーツァルトを思わせるような素朴な構成だが、時折姿を見せる劇的で大胆な転調が、聴くものの意表を衝く。そして意外にもハ長調で明るく締めくくられる。
第二楽章:アンダンテ
ベートーヴェンに倣ったのか、長三度下の変イ長調が使用されている。優美な旋律による甘美で情緒豊かな主部と、調を変えて二度あらわれる劇的な要素をもった短調の中間部分とが対照的である。
第三楽章:メヌエット、アレグロ・ヴィヴァーチェ-トリオ
弱拍へのアクセントとヘミオラのリズムが特徴的な、テンポの速いメヌエット。トリオは木管楽器が伸びやかに歌い上げる。
第四楽章:アレグロ
木管楽器の呼ぶ声に導かれ、第一楽章と同じ雰囲気を持った旋律が駆け抜ける。ざわめくような伴奏にのせてヴァイオリンと木管楽器とが対話する副次主題はオペラのワンシーンを見ているかのように魅惑的である。そして第一楽章と同様、短調で開始しながら長調で終止し、決然と(あるいは投げ遣りに?)叩きつけるようなハ音の斉奏で全曲が閉じられる。
マーラー/交響曲第4番 ト長調
ボヘミアの片田舎出身のユダヤ人であったグスタフ・マーラーが、オーストリア=ハンガリー二重帝国の帝都ウィーンの宮廷歌劇場の指揮者に任命されたのは1897年、37歳の春であり、同年秋には同歌劇場の音楽監督、翌年にはさらにウィーン・フィルハーモニー管弦楽団指揮者をも兼任している。当時のウィーンは政治・文化両面において世界の中心のひとつと言ってよく、市民はハプスブルグ家700年の伝統と、建築・絵画・音楽・デザインなどの新芸術の波が共存する世紀末ウィーンの繁栄を謳歌していた。この第四交響曲は、マーラーがそのウィーン音楽界に「指揮者として」君臨したころ、すなわち1899年と1900年の夏季休暇中に作曲され、1901年、ミュンヘンにて自身の指揮で初演されている。しかしながら、第四楽章のみは別途『子供の魔法の角笛』歌曲集の『天上の生活』と題して1892年に書かれ、単独で演奏もされている。当初は第三交響曲の第七楽章に収めることが意図されていたというこの曲のために、新たに第一楽章から第三楽章がいわば「後付け」された。このため先行する3つの楽章には第四楽章の主題が随所に散りばめられており、それぞれが『天上の生活』を導き、あるいは引き立てる役割を果たしている。
第一楽章:ほどよい速さで、急がずに ト長調 4/4拍子 ソナタ形式
印象的な鈴とフルートによってロ短調で開始されるも、フレーズ末尾でリタルダンドされるクラリネット、続く第一主題(ヴァイオリン)とはずれが生じるよう指定されている。主題は装飾音的な動きも含んだハイドン風なものである。第二主題はチェロがゆったりと歌う。展開部では、4本のフルートのユニゾンによって新しい旋律が現れる。これは、第四楽章の主題の先取りとなっている。その後音楽は展開部において混沌とした様相を示し、第五交響曲の第一楽章冒頭を想起させるトランペットによるファンファーレ動機によって強制的に中断される。第一主題の再現は唐突で、しかも主題の途中から再現される。
第二楽章:落ち着いたテンポで、あせらずに スケルツォ ハ短調 3/8拍子 三部形式
長二度高く調弦した独奏ヴァイオリンが登場する。草稿において「友ハイン(死神)が演奏する」と注を入れたこともあるマーラー自身が「このスケルツォは、諸君が聴くとき、髪の毛が逆立つほど神秘的で昏迷した超自然的なものだ」と述べているように、ホルンが先導する素朴な旋律に道化役の木管が絡み、弦楽器のグリッサンドが多用されるなか、彼岸との異常な対話が展開される。
第三楽章:やすらぎに満ちて、少しゆるやかに ト長調 4/4拍子 変奏曲形式
中低弦で静かに始まり、2つの主題が交互に変奏される。第九交響曲の第四楽章を先取りしたかのような雰囲気が漂う。第二変奏から次第に軽快になり、拍子、テンポ、調性がめまぐるしく移り変わる。楽章の終わり近くで突然盛り上がり、ホ長調で第四楽章の主題が勝利を歌うかのように高らかに強奏される。最後は属和音のニ長調となり、静寂のうちに第四楽章を準備する。
第四楽章:きわめて快適に ト長調 4/4拍子
クラリネットが小鳥のさえずりのような音形をもって穏やかな雰囲気を作ると、いよいよソプラノ独唱が天上の楽しさを歌う。弦楽器はゆらゆらと揺れ動き、イングリッシュ・ホルン、フルート、ハープがこれ以上なく牧歌的に響く。
ソプラノはまず、「私たちはいま天上の喜びを味わっている。だから俗世のことなど気にならない。俗世の騒ぎなど天上にいると少しも聞こえてこない…」と天上の幸福な様子を歌うが、突然、騒がしくなり強いリズムが示される。これは第一楽章の冒頭で鈴によって暗示されていたものである。ソプラノは不安げに第二の部分を歌いだす。「聖ヨハネが小羊を連れてくる。屠殺者ヘロデがそれを待ち受ける。私たちができることといったらその純粋な小羊を死に導くことくらい…」。神の小羊、主イエスに対する罪の告白とも取れる。再び鈴による中断があり、今度は穏やかな第三部となる。「あらゆる種類の野菜や果物が天上には生い茂っている。上等のアスパラガスにインゲン豆、リンゴ、梨、ぶどう酒…。なにもかも望み通り…」。みたび鈴がやってきて第四の部分になる。そののちイングリッシュ・ホルンがバグパイプの音をまねる。「この天上には音楽だってある。地上のどんなものも比べ物にならないような音楽が。…すべての感覚を喜びに目覚めさせる。そしてすべてを幸福にさせる」。曲は安らぎに満ちたまま静かになっていき、イングリッシュ・ホルンとハープの響きを残して永遠の彼方に消え去っていく。
ワーグナー/歌劇「リエンツィ」序曲
14世紀のローマ。公証人のリエンツィは護民官(平民の中から選出され特権をもつ公職)に就くが、横暴な貴族階級と対立して貴族達から命を狙われる。リエンツィの暗殺計画は失敗に終わり、首謀者達は捕らえられたものの、妹のイレーネと恋仲にある貴族のアドリアーノの懇願により命は助けられる。しかし命を助けられた貴族達は反乱を起こし、やがて市民との戦争に発展する。リエンツィの率いる市民はこれに勝利するが、その後リエンツィはローマの新しい皇帝、教皇から弾圧されることになり、市民からも反感をもたれるようになる。ついに市民の怒りは頂点に達し、リエンツィの宮殿には火が放たれる。アドリアーノはイレーネを助けに入るが、宮殿は焼けて崩れ落ちてしまう。
以上は歌劇「リエンツィ」の簡単なあらすじです。「リエンツィ」は、稀代のオペラ作家リヒャルト・ワーグナーの完成させた3作目のオペラです。
1842年(当時ワーグナーは29歳)のこの作品の初演は大成功を収め、後にワーグナーが歴史あるザクセン宮廷歌劇場(現在のドレスデン国立歌劇場)の楽長に任命されるきっかけとなりました。いわばこの大作曲家の出世作になります。
しかし、「リエンツィ」は世界中に熱狂的な支持者のいるワーグナーの作品にあっても、今や本日演奏する序曲が独立して演奏されるばかりで、全曲の上演は希少です(と書いてみましたが、この4月にもベルリン・ドイツ・オペラで上演があったようです。あくまで以降の作品に比べると圧倒的に少ない、とご理解ください)。ワーグナーが自身の作品の上演の為に創設したバイロイト音楽祭においてすらも上演されません。
ワーグナーはその生涯において、指示動機の駆使をはじめ、無限旋律の採用や半音階・不協和音(トリスタン和音)の多用などの独特な作曲技法を綿密に張り巡らせた革新的な作品を次々と世に送り出し、歌劇をさらに発展させた楽劇という総合芸術を確立しました。その作品群が後世の作曲家に与えた多大な影響は音楽史上で非常に重要な意味をもっています。
しかし、このような作曲技法の発展は4作目の「さまよえるオランダ人」から顕著にみることができるもので、特に6作目「ローエングリン」以降の作品が楽劇と呼ばれています。そんな中にあって、当時のフランスを中心に既に流行していたグランド・オペラの形式で、作曲技法も未熟な頃に書かれた「リエンツィ」はワーグナーを代表する作品にはなり得なかったのです。
この序曲には「さまよえるオランダ人」や「タンホイザー」などのほぼ同時期に作曲されたといってよい初期の作品に通じるオーケストレーションも随所にみられますが、後期の緻密で重層的な構成の作品に比すれば、その非常に単純なつくりはワーグナーらしからぬ稚拙さというほかないでしょう。しかしその荒削りな才能とエネルギーに溢れる作風はまた別の情熱的な魅力をもっており、大作曲家ワーグナーの作曲技法の成熟の過程を知る上でも重要な作品の一つなのです。
ちなみに3年後に迫った2013年はワーグナー生誕200年にあたります。「リエンツィ」までの最初期の3作品は、日本での舞台つき上演は数えるほどしかないのですが、この機会にスポットが当てられることもあるのではないかと密かに期待しているファンもいるのではないでしょうか。
ハンス・ロット/田園前奏曲 ヘ長調
「ブラームスはお好きですか?」現代の日本で、こんな台詞でデートに誘い上手くOKを貰える可能性がどれだけあるのかわかりません。ただ、昨年のプログラムノートでの「ブラームスはお好きですか?」との問いに様々なお返事を返してくださった皆様でも、「ハンス・ロットはお好きですか?」との問いには、(この曲目当てにご来場くださった方や、マーラー関連の回想記をよく読まれる方を除けば)「それは何ですか?」と答えられる方が多いのではないでしょうか。
本日の演奏会、若がりし20代半ば頃のワーグナーとブラームスの曲に挟まれ演奏される曲目は、これまた20代のハンス・ロットが作曲した田園前奏曲。二人から多大な影響を受けたハンス・ロットの20代は、同じ20代とはいっても他の二人より短いものでした。前後の作曲家と違い知名度が圧倒的に低いと思われるこの作曲家について、まずはご紹介させていただきたいと思います。
【ハンス・ロットその人生】
<音楽への道>
ワーグナーが「トリスタンとイゾルデ」を作曲中で、ブラームスが「セレナーデ第1番」を完成したとされる1858年、ウィーンの郊外。ハンス・ロット(本名はヨーハン・ネーポム・カール・マリーア・ロート)は、喜劇俳優の父と歌手・女優の母との間に(二人が結婚する数年前に)生まれました。父に音楽の素養があったこともあり、小さい頃から音楽に親しみます。1874年に入学したウィーン音楽院では、翌年入学してきた2歳年下のマーラーと出会い、共に刺激を与え合いながら音楽の道を志します。また、オルガンをブルックナーに師事し、音楽院のコンクールでも1位を獲得。ブルックナーはロットのバッハ演奏や即興演奏を高く評価していたようです。その他に音楽院では和声法、対位法、作曲法を学び、この時代の他の生徒同様にウィーンで栄華を誇ったワーグナーの影響を大きく受け、1875年、ウィーン・アカデミー・ワーグナー協会に入り、数々の上演に立ち合ってワーグナーの曲に親しみました。さらに協会の選抜メンバーとして1876年の第1回バイロイト音楽祭も訪れています。
<苦難の道>
と書くと、順風満帆の音楽人生に見えるかもしれません。しかし実際には不幸が続きました。ウィーン音楽院入学前の1872年、彼が14歳の時に母を亡くします。更に1875年、彼が17歳の時には父が舞台上で事故にあい、職を失った上、その治療に財産の大半を費し、翌1876年に父を亡くします。こうして、次々と起こる不幸の末に18歳にして生活の基盤を失い、自らの手で生計を立てなくてはならない事態となったため、その後約2年間、修道院のオルガニストとして働きながら、修道院に一室を借りて音楽院に通いました。そんな彼にとっての生きる道は音楽以外に無く、大きな夢と不安を抱えながら演奏・作曲活動を行っていたのは想像に難くありません。彼は1874年から本格的に始めていた作曲活動を1876年以降精力的に行いますが、その結果、大変残念なことに破滅への道を進むことになります。
<作曲家ロット>
在学中から数曲の管弦楽曲や歌曲を完成し、1878年、その集大成として卒業課題にも出した交響曲第1番の第1楽章をもって、卒業生を対象としたコンクールに応募するも、何とマーラー含む応募者のうちロットのみが落選してしまいます(マーラーは現存しないピアノ五重奏で受賞。ある回想によるとマーラーは自分も一緒に落ちたと言ったようですが、他の年の審査員や受賞者の名前を出したり、ベートーヴェン賞と混同している、というのが近年の研究結果のようです)。屈辱的な状況に追い討ちをかけるように、3ヶ月後には濡れ衣が原因で修道院の職を辞めることになり、経済的にいよいよ追い込まれます。オルガンの師匠であるブルックナーの強い推薦にもかかわらず、ザンクト・フローリアンなどのオルガニストの職は得られず、友人たちの援助や家庭教師で凌いでいたロットが、生まれ故郷のウィーンに居続ける為に大きな望みを托して完成させたのが、残り3楽章が加えられた交響曲第1番と本日演奏される田園前奏曲でした。1880年、彼は国の奨学金にこの2曲を応募すると共に、自分の曲を世に知らしめるべく、積極的に動きます。
<夢と現実>
まず、応募する際に提出するスコアと共にあらかじめパート譜まで準備し、時のウィーン・フィルの首席指揮者であったハンス・リヒター(ブラームスの交響曲第2番を1877年に、第3番を1883年にウィーン・フィルと初演)に掛け合って交響曲を演奏してもらおうと試みました。また奨学金の審査員のメンバーになっていたハンスリックとブラームスに直接会い交響曲を聴かせることで認めてもらおうと試みたのです。しかしながら、独断でチャイコフスキーの序曲を取り上げた経験のあるハンス・リヒターの決断にかける、という楽観的な行為と、幾らブルックナーから高い評価を貰っていたとはいえ、当時の音楽界の構図を考えると突っ込みどころ満載な行為は、成就することなく終わります。ハンス・リヒターには前向きなコメントは貰えて何度か会うものの、演奏の確約はされず、やがては会う約束すらすっぽかされるようになり、その間に会えたブラームスからは曲を酷評されたのでした。
<そして…>
どうしてもウィーンに留まりたかったロットも万策尽きました。そして友人たちや想いを寄せていた(それは作曲の原動力にもなった)女性の説得によりウィーンを離れることを受け入れた時には既に彼の精神崩壊が始まっており、ミュールーズ(当時ドイツ領だった都市で今はフランスの東の端。スイス第3の都市バーゼルにも近い)の合唱協会の指揮の職に就くべく移動していた列車の中でついに発狂します。数日前から「ミュールーズの人やブラームスが自分を監視している」と言っていたロットは「ブラームスが列車にダイナマイトを仕掛けている」と信じこみ、同乗者がタバコに火を点けようとした瞬間それを止めようとピストルを突きつけたのでした。当然取り押さえられたロットは病院の精神科に収容され、翌年には精神病院に移され、「回復の見込み無し」と診断を受け、数回の自殺未遂の後に1884年結核の為亡くなります。その人生わずか26年足らず。精神病院に収容された翌月(数日後という説もあり)にあれほど望んだ奨学金授与の通知が、ブラームスの反対にもかかわらず、届いたというのは、なんと残酷なエピソードでしょうか…。
【田園前奏曲】
さて、大分長い作曲家紹介となってしまいました。曲のご紹介も少しばかりさせていただきます。
ブラームスが『田園交響曲』とも呼ばれる交響曲第2番を書いた1877年、ロットは田園前奏曲の作曲を開始し、1880年に完成しました。前半はのどかな落ち着いたテンポで進み、木管楽器による鳥の鳴き声を思わせるフレーズ(マーラーの交響曲第1番冒頭と雰囲気が似てませんか?)や、木の揺れを思わせる(皆さんはどう感じられましたでしょうか?)低弦の半音下降の後に、金管のコラールや弦のピッチカートによる暗い行進曲風フレーズが登場し、マーラーの交響曲第2番を思いだすような高揚や、低弦の唸り、そして弦の小人数でのアンサンブルとクレッシェンドの後に2ndヴァイオリンの旋律でフーガが登場、フーガはコーダまで続き、最後は全楽器のF-durで曲を締めくくります。盛り上がったところで出てくるトライアングルは、交響曲でも最高潮の場面で何度も登場しており、ロットのオーケストレーションの特徴の一つといえるでしょう。
なお、ロットが作曲家としての成功を願って完成したこの田園前奏曲と交響曲第1番には共通するモチーフがあります。田園前奏曲の冒頭でファゴットとチューバによるF-durの和音に乗っかり出てくるホルンから、その後に重なる形で出てくるヴァイオリン、および続いて出てくる低弦までがこの曲のテーマであり、このテーマを構成するモチーフが曲中で展開し、曲の最後でテーマが回帰します。またその冒頭のホルンによるモチーフ「C-F-A-D(5-1-3-6)」は特に重要で、フーガやコーダなど節目の他にも幾度となく登場します。このモチーフは交響曲においても登場し、4つの楽章を繋ぐテーマのモチーフであることに触れておきたいと思います。交響曲ではフルートと1stヴァイオリンの分散和音によるE-durの和音に乗っかり、トランペットが「H-E-G#-(E-)C# (5-1-3-(1-)6)」と出てきます。この2曲に共通するモチーフが何なのか、オルガンで得意としたバッハへのオマージュでBACHモチーフに倣ったのか(BACHモチーフに倣ったといえばDSCHモチーフが有名ですね)、あるいは私の勘違いか、どなたかご存知でしたらアンケートやその他どんな手段を使ってでも是非ご教授ください…。
【ロットと本日の演奏に関する個人的な思い】
ハンス・ロットは友人への手紙、日記やメモなどから生涯で約80曲を作曲したことが分かっています。その草稿の大半は友人が引継ぎ、その娘がオーストリア国立図書館に寄贈し、マーラー研究の中で偶然発掘されるまで眠ることとなりました。しかし、残念なことにスケッチなどの多くを自ら破棄しているため、演奏可能なものは全て1880年以前に作曲された20曲余りしかなく、録音も多くありません。それでも、1989年に交響曲が初演されて以来、その作品の評価は(特に今世紀に入って)世界各地に広がっており、日本でも2004年に交響曲が初演されその後何度も取り上げられるようになっており(本日指揮いただく寺岡氏は、国内でハンス・ロットの交響曲を2回指揮されています)、「ジュリアス・シーザーへの前奏曲(冒頭の主題の音符の長さがマイスタージンガーと同じ、最後に全楽器が3つのメロディーに分かれるなど大きな影響を受けている)」も2度日本で演奏されております。そして本日の田園前奏曲はおそらく日本初演となりますが、今後、日本で演奏される機会もさらに広がっていって欲しいと考えております。
もし本日初めてロットの名前を知り、興味を持たれた方は、是非交響曲も聴いていただきたいと思います。バッハ、ベートーヴェン、そしてワーグナー、ブルックナー、ブラームス(彼はなぜ酷評したのでしょうか。ただ、ブラームスは他人だけでなく自分にも厳しい人間だったのはご存知の通りです)に対するロットからの若いなりのオマージュと、ロットに対するマーラーのオマージュ(彼が交響曲第1番に着手したのは1884年。1880年時点では、大戦で失われた習作のような交響曲しか書いていません)がそこにはあります。
ワーグナーは数曲あれど、ブルックナーやマーラーを演奏会にて取り上げたことのない当団において、オケの提唱者であり、ロット指揮の第一人者とも言える寺岡氏の手でハンス・ロットを取り上げるというのは、(私は選曲にかかわらず、また全く予想していなかっただけに)一層感慨深いものがあります。ハンス・ロットが作曲した年齢をほとんど(全員?)の団員が超えていますが、その我々が彼の願いをどこまで皆さんにお届けできるか、注目したいと思います。
最後に、本日の演奏が何かしら皆様の心に残ることを祈りつつ、ハンス・ロットに関する逸話的コメントを幾つかご紹介し、結びとさせていただきます。
・ 笑うのを止めなさい。あなたたちはやがてこの若者が創り出す素晴らしい曲を聴くことになるのだから。(ブルックナー)
・ この作品には非常に美しい部分もあるが総じて平凡だ。だから、その美しい部分も君の作曲ではないのだろう。(ブラームス)
・ 彼を失ったことで音楽のこうむった損失ははかりしれない。(中略)僕は彼から非常に多くを学ぶことが出来たはずだし、たぶん僕たち2人がそろえば、この新しい音楽の時代の中身を相当な程度に汲み尽くしていただろう。(マーラー)
『参考文献』
ハンス・ロット 交響曲第1番ホ長調 スコア RIES&ERLER社
セバスティアン・ヴァイグレ指揮 ミュンヘン放送管弦楽団(BMGジャパン:BVCE-38080)ブックレット(井内 重太郎氏訳)
デニス・ルッセル・デイビス指揮 ウィーン放送交響楽団(Cpo:999854)ブックレット
国際ハンス・ロット協会HP http://www.hans-rott.org/
日本ハンス・ロット協会HP http://homepage3.nifty.com/hans-rott/
新日本フィルハーモニー交響楽団 第397回定期演奏会 プログラムノート(山尾 敦史氏)
東京アカデミッシェカペレ 第32回定期演奏会 プログラムノート
京都フィロムジカ管弦楽団 第18回定期演奏会 プログラムノート(遠藤 啓輔氏)
京都フィロムジカ管弦楽団 第25回定期演奏会 プログラムノート(遠藤 啓輔氏)
ブラームス/セレナーデ第1番 ニ長調
ドイツ・ロマン派を代表する大作曲家、ヨハネス・ブラームス(1833~97)。写真(右)のような外見も相まってか、よく言われるところの彼のイメージは「重厚」「哀愁」「内省的」「枯淡」「静謐」、あるいは彼の音楽が苦手な人からすれば「暗い」「重い」「ウジウジしている」といったところでしょうか。
でも、本日演奏いたしますセレナーデの第1番、特に第1楽章を聴いて、「ブラームスはなんて暗いヤツだ!」と思われる方はまずいないでしょう。
自己批判の強いブラームスは、その63年の生涯でわずか13曲しか管弦楽作品を残しませんでした。その記念すべき第1作にあたる本作は、1857年から58年にかけて書かれたとされています。なぜセレナーデを書いたのか、そしてなぜ「このような」セレナーデを書いたのか、背景を少し見てみましょう。
1857年、24歳のヨハネスは、大恩人で心の師でもあった作曲家ロベルト・シューマン(1856年没)の未亡人・クララの紹介もあり、自然豊かなデトモルトの宮廷に初めての定職を得ます。この仕事は、毎年9月から12月までピアノや合唱を教えればなんとか1年は暮らしていけるだけの収入が得られる、つまり残りの8ヶ月間は創作活動などの好きなことに充てられるという、悪くない条件だったようです。なにしろ、それまでの彼は生まれ故郷ハンブルクの場末の酒場で酔っ払い相手にピアノを弾いたり、知り合いのヴァイオリニストと地道に演奏旅行をして名前を売り出そうとしたりしていた訳ですから。この宮廷音楽家という立場が、セレナーデを書くとりあえずのきっかけになったようです。
この頃には、様々な様式を経た末にセレナーデとは「色々な楽器による複数楽章の合奏曲」といった形態に落ち着いていました。なんといっても、あのモーツァルトが宮廷音楽家として綺羅星のごとく名作のセレナーデを書いておりますから、ヨハネスも同じ貴族に仕える身としてそれらの音楽に実際に接する機会があったのでしょう。また、この時期は熱心にハイドンの音楽も研究していましたので、自身もセレナーデを作曲するというのは自然な流れだったに違いありません。
余談ですが、ベートーヴェンを意識するあまり最初の交響曲を書くのに20年以上もかかったのに対し、ハイドン・モーツァルトへのオマージュとも言うべきセレナーデはすぐに2曲仕上がった(第2番も1859年に完成)というのは興味深い事実です。
ともかく、彼はまず小編成の室内楽という形で、この曲の第1、3、6楽章にあたる曲を書きます。このときの編成は、ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・コントラバス・フルート・クラリネット・ファゴット・ホルンという八重奏あるいはこれにクラリネットをもう1本足した九重奏と言われています。なぜ分からなくなってしまったかというと、残念ながら自己批判の強いブラームスによってオーケストラ版の完成後に室内楽版が破棄されてしまったからです。なお、最初から九重奏であったという説もありますが、後述の理由並びにクラリネットだけ最初から2本というのはいささか不自然ということもあり、私は一番初めは八重奏であったと思います。
残りの3つの楽章を完成後、この室内楽版はデトモルトの雇い主の下で無事初演されます。ところがこの曲にシンフォニックな響きを感じ取ったクララ等の薦めによりこれをさらにオーケストラ用に編曲、1860年にはより大きな都市であるハノーファーで早速初演されます。ちなみにこの時彼はこの曲に「交響曲-セレナーデ」という、なんとも煮え切らないというか実に彼らしいタイトルをつけたそうです。
さて、さらに興味深いのが、なぜ「かくも明るい」セレナーデを書いたかです。
というのも、このわずか数年前まで、ヨハネスは件のシューマン未亡人・クララと大恋愛をしてしまい、さらにそれを自分の決断力の無さと自己批判故に泣く泣く諦め、そうかと思えば才能豊かな若い歌手と相思相愛の仲になりせっかく婚約までしたのに、「ボクってこれからあなたとどうすればいいでしょうか」という身も蓋も無いような手紙を書いてしまったのをきっかけに破局してしまったりといった、精神的には不安定極まりないであろう時期だったからです。「自己批判の強い」彼ならば、この作品そのものを破棄してしまったかもしれません。
理由は今となっては想像するしかありません。代わりにと言ってはなんですが、こちらをご覧ください。写真(左)は20歳のヨハネス。真っ直ぐと見据えた瞳に、豊かにたなびく(おそらく)金髪。美青年、と言って差し支えないでしょう。もうひとつは、シューマンが書かせた同じく20歳のヨハネスのスケッチ(右)。やや俯きがちな表情になんとも繊細そうな目ではありませんか。この青年がどんな思いで数年後にこの曲を完成させたのか。ぜひ皆さんも想いを馳せてみてください。
第1楽章:アレグロ・モルト
なんと愉しい曲でしょう!
ヴィオラとチェロの牧歌的な5度の和音が4度鳴った後、これまた牧歌的な楽器であるホルンがまるで朝の草原を散歩しているような清清しい主題を楽しげに口ずさみ、それをクラリネットが「あ、そのメロディーいいね、ワタシはこんな風に歌っちゃおう」とばかりに引き継ぎ、それをオーボエ、さらに弦楽器、そして頂点ではトランペットが高らかに主題を奏でティンパニが軽やかに舞います。なんとも素直、正直なオーケストレーションではありませんか! スコアをながめて初めて「ふむふむそうか、こんなマニアックなことをブラームスは書いていたのか、やっぱり彼は最高だなぁ」なんて思うことは、ここではありません。
ひとしきり盛り上がった後にまずヴァイオリンとファゴットで出てくる第2主題では、二拍三連のリズムに彼らしさが表れています。展開部がまた演奏していてとっても愉しいのです。
第2楽章:スケルツォ(アレグト・ノン・トロッポ)-トリオ(ポコ・ピウ・モート)
1楽章からがらりと雰囲気が変わり、いかにもブラームスらしい「ミステリオーソ」な1曲。ヴィオラが大活躍します。
トリオは一転して明るい響きで、リズムも朗らかです。
第3楽章:アダージョ・ノン・トロッポ
本曲の「核」といえる、ドイツ・ロマン派の王道を行くような緩徐楽章。
様々な旋律が現れては消えて行き、うつろいやすくどことなくとりとめのない印象さえ与えます。メンデルスゾーン・シューマンの本流そのままに、木管楽器の音色が主役です。
第4楽章:メヌエットⅠ-Ⅱ
シンプル極まりなく、スコアにしてわずか3ページの小品ですが、無駄な音がひとつもありません。間違いなくブラームスの最高傑作のひとつでしょう。
メヌエットⅠはファゴット及びチェロの伴奏を従えたクラリネット二重奏にフルートが華を添え、メヌエットⅡはヴィオラの分散和音の上にヴァイオリンが物憂い旋律を奏でます。他の大部分の楽器はお休み。前述のようにこの曲は最初は八重奏であり、この楽章が加えられたときに九重奏になったのではと考える理由は、この楽章にあります。なぜなら、クラリネット2本がここまで効果的に使われている箇所(1楽章最後、3楽章冒頭なども確かに美しいですが)が全曲中他に見当たらない、つまり2本必要であった必然性がこの楽章ほどは感じられないからです。
第5楽章:スケルツォ アレグロ
ブラームスはスケルツォを数多く書いていますが、ベートーヴェンの系譜から連なるいわゆる「直球ど真ん中」のスケルツォはほとんど書いておらず、ましてやオーケストラ作品ではほとんどありません(ヴァイオリンのないセレナーデ第2番や、ピアノ協奏曲第2番くらいです)。
巨匠ブラームスには大変失礼ですが、「なんだ書こうと思えばこんなに素敵なスケルツォが書けるんじゃないか」とつい思ってしまうような、とても楽しい曲です。
第6楽章:ロンド アレグロ
有名な「ハンガリー舞曲集」を挙げるまでも無く、彼は民謡・民族的な曲に強い関心を持っていました。また、前述した「一緒に演奏旅行をしたヴァイオリニスト」もハンガリーの亡命者でした。そうした影響もあってか、民族的な色彩の強い楽章です。
ピアノで演奏するのにもぴったりな力強いリズムが全編を支配する中、なんともチャーミングな第2主題が印象的です。
ちなみに、元の室内楽版にない楽器(オーボエ、トランペット、ティンパニ)の扱いが気になるところですが、ごく自然に音があてがわれています。むしろこれらの楽器の活躍する場面が、逆説的にブラームスのこれらに求める役割を教えてくれます。