メンデルスゾーン:交響曲第4番イ長調「イタリア」 (Vn. M.K)
メンデルスゾーンは1890年ユダヤ系ドイツ人としてハンブルクの裕福な銀行家の家に生まれ、幼児から本格的な音楽教育を受けその天才ぶりを発揮した。
この第4番「イタリア」を含め五つの交響曲、演奏会用序曲、たくさんのピアノ作品、室内楽、歌曲、それに何といってもヴァイオリン協奏曲ホ短調など、数々の珠玉のような名曲によって、ショパン、シューマンなどとともに初期ロマンはを代表する作曲家とされている。
当時はほとんど忘れられていた「マタイ受難曲」を演奏し、19世紀におけるバッハ再評価の気運を作った功績も忘れることはできない。
さて彼の音楽の特色は、いわば爽やかに匂いたつような、つまりある種の香気に満ちた作風にあるのではないだろうか。 これは、よくいわれるように彼の生い立ちからくるものであるとともに、ロマン主義的内容ないし精神を古典主義的様式で表現していることとも無縁ではないと思われる。
彼は、20才の1829年から23才の1832年にかけて、イギリスをはじめオーストリア、イタリア、フランスなどを旅し、そのうちローマに30年から翌31年にかけて滞在したが、「イタリア」はこの時書き始められた。 31年に出した手紙には「イタリア交響曲はおおいに進捗している。この作品、特に終楽章のプレスト・アジタートの部分は私の書いた曲の中ではもっとも成熟したものになるだろう。」と述べている。
そしてロンドン・フィルハーモニー協会からの依頼もあって33年に完成され、同年作曲者自身の指揮の下に初演された。 しかし彼はこの曲の出来栄えに必ずしも満足していなかったらしく、ことに第4楽章については書き直したいとさえ言っていたという。 事実生前には出版もせずドイツでは演奏もしなかった。 結局ドイツでの初演は彼の死から2年後の49年、ライプツィヒのゲヴァントハウスで行われた。
第1楽章アレグロ・ヴィヴァーチェ、イ長調、8分の6拍子、ソナタ形式。
2小節の木管による和音の軽快な刻みに続いてあたかもイタリアの空を思わせるように明るく、踊るような第1主題がヴァイオリンで提示される。この動機は60小節にわたって展開され、さらに50小節余りの経過句の後属調のホ長調の第2主題がクラリネット、ファゴットによって奏される。これがクライマックスに達したのち、第1主題が戻り提示部は終わり、反復される。展開部は提示部の経過句の動機から派生した新しい主題によるフガートで始まり第1主題が再現される。そのクライマックスが一旦静まって後、クレッシェンドしつつ再現部に入り、第1、第2主題が再現される。コーダはピウ・アニマート・ポコ・ア・ポーコとなって第1主題ともう一つの主題が弦と管で交互に提示され、スタッカートの3連音の走句は若々しい朗らかな気分を漲らせつつこの楽章を閉じる。
第2楽章アンダンテ・コン・モート、ニ短調、4分の4拍子。
行進曲風のリズムの支配するこの緩徐楽章は、彼がナポリで見かけた宗教的行列の印象から着想したといわれる。 まず、冒頭に木管と弦により重々しく哀愁に満ちたフォルテの楽句が示され、オーボエ、ファゴット、ヴィオラによって叙情味豊かな主旋律が奏でられ、さらにそれはフルートの対旋律を持ったヴァイオリンに受け継がれる。 この間バスは、8分音符の重々しい足取りを聞かせている。この楽章の中間部はイ長調となり、クラリネットは対照的な表情を持つ旋律を歌い始める。冒頭の部分がさらに少し形を変えて再現されこの楽章を終わる。
第3楽章コン・モート・モデラート、イ長調、4分の3拍子。
この楽章はスケルツォではなくメヌエットであるが、単なる美しさを超えた、いわば地中海的優雅さ、明晰さ、あたたかさ、それに香を備えている。 トリオに相当する部分はホ長調となる。
第4楽章サルタレッロ-プレスト、イ短調、4分の4拍子、ロンド形式。
この終楽章こそは彼が最も力を注ぎ、また苦心した部分で、ローマ地方のダンスであるサルタレッロのリズムによる二つの主題が提示される。 さらに3連音が均等に流れる第3の主題はナポリ地方の舞曲タランテッラのリズムである。


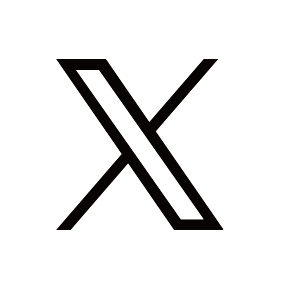
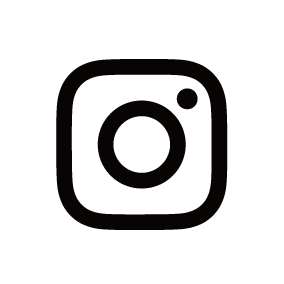

コメントを残す