メンデルスゾーン 「真夏の夜の夢」序曲
4つの和音が誘う、ファンタジーの世界。
かすかな森のざわめき。飛び交う妖精たち。
突然のまばゆい陽光。祝祭の喜び。愛の幸福。
見える世界と見えない世界のクロスオーバー。
やがて、すべてはまどろみ、眠りにつく。
メンデルスゾーン、17歳。シェークスピアの戯曲「真夏の夜の夢」を題材とするこの序曲は、なんと霊感と才気に満ちあふれていることか。
裕福な銀行家の家に生まれ、また、バッハを敬愛し、古典への造詣の深かったメンデルスゾーンの作品は、端正で優美、上品さを感じさせるものが多い。その中でも、この「真夏の夜の夢」序曲は、前年に作曲された弦楽八重奏曲と並んで、若きメンデルスゾーンの生んだ傑作といえる。シューマンは、「この曲は、この作曲家の他の作品には見られないほどの青春の輝きを発している。熟練した大家が、最も幸福な瞬間に、最初で最高の飛躍をしたのである」と語ったという。
この曲でのメンデルスゾーンの管弦楽法は、ほとんど室内楽のような精密さと、常識を超える大胆さが表裏一体となっており、それが曲にみずみずしい色彩感と面白さを与えている。冒頭の木管の和音や分割されたヴァイオリンの刻み、独特の和声配置や最弱音の多用、テューバ(本来は、オフィクレイドという現代では廃れてしまった金管の低音楽器)の効果的な使用、などなど。
それだけにこの曲は、オーケストラの実力が問われる、ある意味とても恐ろしい作品なのだが、同時に、あまりにも魅力的な作品だ。ブルーメン初の再演曲にこの曲が選ばれたのも、単なる偶然ではあるまい。
なお、メンデルスゾーンは34歳の時に、この序曲に続く一連の劇音楽を作曲し、ポツダムの宮殿でこの劇音楽によるシェークスピアの「真夏の夜の夢」が上演された。序曲とこれらの劇音楽は、17年もの時の流れを感じさせない連続性、一体感があり、「スケルツォ」、「間奏曲」、「夜想曲」、そして有名な「結婚行進曲」など、序曲の霊感を受け継ぐ魅力的な作品が含まれている。現在は、組曲の形で演奏されることが多いが、これまたいつか演奏してみたいものだ、と個人的に思っているところである。
ハイドン 交響曲第100番 ト長調 「軍隊」
ブルーメンがハイドンの作品を取り上げるのは、交響曲第99番(第5回定期)、同97番(第16回定期)に続き、三度目である。
ハイドンは1761年(29歳)からオーストリア東部の小都市・アイゼンシュタットに居を構えるエステルハージ侯爵に仕える身となった。侯爵は熱狂的といってよいほどの音楽愛好家であり、その宮殿には400人以上を収容できるオペラ劇場をはじめ、それぞれ専用の喜劇場、人形劇場が備わっていた。盛時には年間250を超える上演回数をこなしたとの記録もあり、もはや一つの文化発信拠点であったといえるだろう。宮廷楽長ハイドンは作曲だけでなくあらゆる音楽の指揮を任され、お抱え音楽家たちの下稽古を助け、オーケストラにおいては自身クラヴィーアを担当し…といった超人的な活躍を28年に渡って続けたのであった。この間、午前中に鍵盤楽器の前に座って即興演奏に興じることでテーマを探し、昼食後はいわゆる「お仕事」、夜には午前中にメモした主題を元に作曲を行う、と極めて規則正しい生活を送っていたという(青年期のエピソードが少ないのも頷ける。妻はいたが不仲だった。子供もない)。
金銭的には恵まれた待遇であり、作曲家としての名声は宮廷を通じてヨーロッパ中に轟くようになったが、片田舎アイゼンシュタットから離れられない自分にとってウィーン、パリ、ロンドンといった大都市への憧憬が常にあった、と後年述懐している。
1790年に侯爵が亡くなり、自由の身となったハイドンのハートを射止めたのはロンドンで活躍していたヴァイオリンの名手・ザロモンであった。自ら大オーケストラを編成し、コンサートマスターとして演奏会を主催していたボン出身の彼は、新作の交響曲を含む作品を、作曲者自らの指揮で演奏するという企画をもってハイドンを訪れたのである。入場料を払って演奏会場を埋め尽くす大観衆を前に演奏できるという機会はハイドンの目にも大いに魅力的に映ったのだろう。既にモーツァルトが没し、ベートーヴェンがウィーンで活躍しはじめた年代において、ハイドンはイギリスへの進出を果たし、また自らと大衆のために音楽を作れるようになったのだ。
今回取り上げるト長調交響曲は、ウィーンで着手され、ロンドンで完成された。初演は1794年。ザロモンの依頼による12曲の新作(ザロモン交響曲)の中でも特に好意的に迎えられたという。
第一楽章は他のザロモン交響曲同様、アダージョの序奏に導かれたソナタ形式のアレグロである。第一主題は二本のオーボエを伴奏に従えたフルートによって奏される。ヴァイオリンにあらわれるチャーミングな第二主題は、ボッセ氏いわく、「ボッティチェルリの絵画『春』にある花(Blumen)のように」。
第二楽章は行進曲風のアレグレット。この楽章のみクラリネットが加わる。後半にはオーストリア軍の進軍ラッパを模したファンファーレが登場し、打楽器群を伴ったトルコ風のマーチが続く。
第三楽章はオーソドックスなメヌエットとトリオ。ボッセ氏の笑顔に応えられるか。
第四楽章はプレスト。ハイドン特有のユーモアが散りばめられている。コーダでは再び打楽器群が加わり、華やかに曲を締めくくっている。「軍隊」というよりは、「軍楽隊」といったところが正しいように思う。
なお、ハイドンにとっては「100番目の交響曲」という認識はなく、もちろん「軍隊」という副題もなかった。いずれも後世名づけられたものであることを付記しておく。
ベートーヴェン 交響曲第1番
作曲:1799~1800年
初演:1800年4月2日 ウィーンのブルク劇場にて、ベートーヴェン自身の指揮で。
献呈:スヴィーテン男爵
ある日のブルーメン・フィルの練習で、トレーナーのS先生がベートーヴェンを始める前にこうおっしゃった。「みなさん、この曲はハイドンの105番のつもりで弾いてください」。
104曲の交響曲を残したハイドン(「交響曲の父」と呼ばれた)の愛弟子であるベートーヴェン。受け継ぐところは多かったかもしれない。ベートーヴェンは1770年ドイツのボンで生まれた。音楽家を志望していた彼は、1787年に音楽の都ウィーンへ旅行。当時ウィーンでは、ハイドンとモーツァルトという二大巨匠が活躍中であった。ベートーヴェンはモーツァルトに面会を求め、彼の前で即興演奏を披露。モーツァルトは「今に彼は世の話題となるだろう」と周囲の人たちに語っている。ベートーヴェンはそのままウィーンに滞在したかったが、母親の危篤のためボンに帰った。そしてそれを待っていたかのように彼女は亡くなった。
1792年、1回目のロンドン旅行からの帰り道、ボンに寄ったハイドンはベートーヴェンに会い、彼の作品を見た上で、彼の弟子入りを許した。そしてその年の11月、ベートーヴェンはウィーンに旅立ち、ハイドンの許で本格的に作曲の勉強を始めた。しかし、ベートーヴェンは必ずしもハイドンの教えに満足してはいなかったようだ。課題に対する添削をちゃんとやらなかったらしい。ハイドンは、1794年からの2回目のロンドン旅行にベートーヴェンを連れていくつもりだった。少なくとも、ハイドンにとってはベートーヴェンは弟子のつもり。ベートーヴェンがハイドンのロンドン旅行に何故同行しなかったのかはわからないが、あるいはそんな感情が働いていたのかもしれない。あこがれの地ウィーンで音楽家として生活することを夢見ていたベートーヴェンは、精力的に活動する。ハイドンがロンドンへ行ってしまったのをいいことに、他の先生を探し出し、勉強を重ねた。そんな彼のウィーンでの集大成がこの第1番の交響曲だった。完成は1800年。ハイドンやモーツァルトといった大先輩たちの影響を脱却すべく、数々の技巧と個性を駆使して作曲された。
ハイドンとベートーヴェンが決定的に仲違いをしたのは1801年のこと。ベートーヴェンの気持ちを何となく察していたハイドンは、ベートーヴェンのバレエ音楽「プロメテウスの創造物」を見た際「なかなかいい作品だ」とそれでも弟子を褒めたのだが、それに対してベートーヴェンは「あれは長い間かかった創造ではないですよ」と、ハイドンが苦心をして作り上げた大作「天地創造」を皮肉ったために、ついにハイドンも怒り心頭、「君のは創造物でもなんでもない、とんでもない作品だ」とけなしつけたのだった。
ある日の練習でボッセ氏がこうおっしゃった。「この曲を作ったころは、ベートーヴェンも若かったんだよ」。
確かに曲からはベートーヴェンの若さと自信がしっかりと感じられる。あまりにも偉大な「105番」が完成したといえるだろう。しかし、この時期すでに彼は耳の変調を感じはじめていたのだった……。
第1楽章 Adagio molto – Allegro con brio
当時としては珍しく長い序奏を伴う。しかも、ハ長調といいながらもハ長調を認識できるのはしばらくたってからのこと。Allegroに入ってからはソナタ形式。第1主題をヴァイオリンで演奏するのは当時のセオリー通り。第2主題は木管楽器が流れるように歌う。
第2楽章 Andante cantabile con moto
初演当時、この楽章はモーツァルトの交響曲第40番に似ていると話題になったそうだが、もっと爽快でチャーミングなもの。流れるような部分とリズミックな部分の組み合わせが印象的。ソナタ形式。
第3楽章 Menuetto : Allegro molto e vivace
従来の優雅なメヌエットとは違った、躍動的な音楽。メロディーは音階が中心のシンプルなもの。トリオ(中間部)は一転して同じ音を繰り返す管楽器に風のようにヴァイオリンが飾りをつける。
第4楽章 Finale : Adagio – Allegro molto e vivace
強打一発。しかし、第3楽章をひきずるかのように、しつこく音階を作ろうとする序奏が続く。Allegroに入ってからも、音階から始まるメロディーが高揚感を感じさせる。ソナタ形式。各楽器に出てくる音階の絡みからは、緊張感とともに音楽の素晴らしさがあふれ出る。曲の締めくくりは、ベートーヴェンならではの立派なものがすでに確立されている。


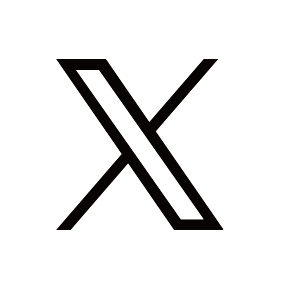
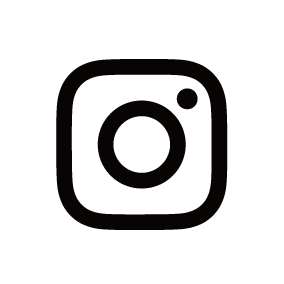

コメントを残す