シューマン:交響曲第3番「ライン」
1850年、ロベルト・シューマン40歳。
この年は彼にとって大きな転機の年であった。長いこと定職のない時代が続いていたが、デュッセルドルフ市の合唱団指揮者に推薦され、散々迷った挙句ついに 引き受けることに決めたのである。シューマンは、このライン河畔の街に転居してから、わずか1ヶ月間でこの交響曲第3番を完成させた。ラインの明るい風光 を反映した作風から、この曲は通常「ライン」と呼ばれている。
交響曲第3番「ライン」は、シューマンの交響曲(全4曲)の中では人気が高く、おそらく最も演奏される機会が多い曲である。しかし、私にとって、この曲 は、長いことよく分からない曲だった。「ラインの明るい風光が反映された曲」と言い切ることのできない、異様な昂揚感、緊張感をこの曲の随所に感じるので ある。
たとえば1楽章。堰を切ったようにあふれる第1主題はヘミオラのリズムを刻みながらうねり、やがて、その合間をぬって、胸がしめつけられるような切ない旋 律の第2主題が現れる。この両者の相克と、お互いを巻き込みながら前に前にと進んでいく、この勢い、ひたむきさに「明るい」などという形容詞はまったくそ ぐわない。
また、2楽章の民謡風の鄙びた旋律は、ほのかな諧謔性を秘めているし、3楽章のささやくような旋律は、温かさに満ちているが、同時にため息の翳を帯びてい る。そして、葬送行進曲のようにモチーフが繰り返し立ち現れる4楽章…。何よりも私が不思議に感じるのは5楽章である。5楽章の第1主題は交響曲第2番の 終楽章のそれとよく似た音形だが、底流をなす心情は2番のそれよりずっと穏やかである。
ダンスのステップを踏むように躍動する若々しい旋律は、幸せの絶頂を歌っているようでありながら、もうその幸せは手中にはないという印象を抱かせる。2番 の終楽章が爆発的な歓喜の歌であるのに対し、3番のそれは過去の幸せを手の中で慈しんでいる、いわば過去形の歌のような気がしてならない。これは単なる思 い込みだろうか。
シューマンが初めてラインを見たのは19歳の春であった。彼はラインの印象を以下の様に書き記している。「目を開けると…前にラインが横たわっていまし た。そっと静かにおごそかに誇り高く、古いドイツの神のように」。このライン旅行は天気に恵まれ、彼は始終、上機嫌だった。「自ら(馬車の)手綱をとった のです。うわあ!馬が走ったことといったら!僕は何もかも忘れて陽気でした。こんな神様のように陽気だったことは今までなかったと思います」。このような 手記から、後年、精神を病み、ラインに身を投げるシューマンを想像することは難しい。彼に何が起こったのだろうか。
21歳、シューマンはピアニストを目指し猛練習を始めるが、無理な練習のせいで(梅毒という説もあるが)23歳で指を故障、ピアニストの道は断たれてしま う。意気消沈したシューマンは深刻な鬱状態に陥った。後に、その時の精神的危機について、シューマンは以下のように書いている。「1833年10月17 日、18日、急に恐ろしい考えに襲われた。人間が持ちうる限りの、天が人を罰しうる最も恐ろしい考えに…理性を失うという考えに。この考えに激しく囚われ てしまうと、慰めも祈りも嘲りも何の力もなくなる。この恐怖から僕はあちこちとさまよい…こう考えて、息が止まった…考えるということができなくなったら どうなる!…クララ、ここまで破壊された人間に病気も悩みも絶望もありはしないのだ…!(中略)…どうにもならない状態にまで追い込まれたら、自分の生命 に手をかけないとも保証できない、その恐ろしさ…」。文献によっては、この年、最初の自殺未遂を起こしたともいわれている。痛ましい限りだが、数ヵ月後、 日記に「正気。文筆の仕事を始める」という言葉が出るように、ひとまず回復。その頃からピアノ教師の娘クララとの間に少しずつ恋が育っていく。やがて二人 は深く愛し合うようになり、1837年に婚約。彼女の父親の猛烈な反対にあうが、裁判にまで持ち込んで、1840年、ようやく結婚にこぎつけた。幸せいっ ぱいのシューマンはこの1840年の1年間に大量の歌曲を作っている(136曲も!)。
しかし、結婚生活を送っていくうちに、シューマンの精神状態は再び悪化していく。9歳年下のクララは華奢で可憐なその風貌に合わず、メンデルスゾーンに 「鬼神のように弾く」と言わしめた実力派ピアニストで、すでに社会的に非常に高い評価を受けていた。それに対し、シューマンは「音楽評論家」兼「指揮者」 兼「作曲家」で、一部の人から高く評価されていたとはいえ無名の青年にすぎなかった。合唱団の指揮をしたり音楽学校で教鞭をとったりすることはあったが、 いずれも長くは続かず、当時、4人の子どもを抱えたシューマン家の生計は、ほとんどクララが支えていたと思われる。演奏旅行に同行すれば「クララの夫」と いう立場に甘んじなくてはいけないことも多かった。シューマンの焦りと悲しみは想像に難くない。
そして34歳、ついにシューマンは鬱、不眠、幻聴、幻覚を伴うひどい精神疾患の発作を起こしてしまう。芸術家によっては精神的危機の時でも(むしろその時 の方が)豊かな創造力を発揮する人もいるが、シューマンは発作が起こるとまったく仕事が手につかなくなってしまうタイプだった。同年、シューマンは音楽評 論の仕事を辞し、療養のためドレスデンに転居する。それから5年近くは、小康状態と鬱状態を行ったり来たりする生活を送ったようだ。
40歳、徐々に健康を取り戻していたシューマンに舞い込んできたのが、前述の、デュッセルドルフの合唱団指揮の仕事だった。この仕事を引き受け、5人の子 どもと6人目を身ごもったクララを連れて、デュッセルドルフに転居してきたシューマンの決意、覚悟の厳しさは想像に難くない。そんな意気込みを持つシュー マンの瞳に、ラインはどのように映ったのだろうか。19歳当時に感動した明媚な風光はそのままだっただろう。しかしそれを見つめるシューマン自身はなんと 変わってしまったことか。あの頃の屈託のなさと快活さは、深い精神疾患を患ったシューマンには、もう決して取り戻すことのできないものであった。
この曲が孕む異様な緊張感と昂揚感の原因は、このあたりにあるのではないだろうか。シューマンの「まだ俺は大丈夫だ」「ここで生きるのだ」という気迫、再 生への祈り、そして、若い日の幸せな思い出に対する憧憬の切実さが、この曲には満ち満ちている。今日の我々の演奏がそこまで表現できれば、これほど嬉しい ことはない。(ちなみに、シューマンはこの曲を作曲した4年後、ラインに身を投げた。救助された後は精神病院に収容され、2年後に死去。享年46歳であっ た。)
シューベルト:交響曲第3番
シューベルトの交響曲を当団が演奏するのは4、8、9番に続いて4曲目となる。
およそ古今の作曲家は天才揃いだが、シューベルトの天才ぶりはモーツァルトと並び群を抜いているように思う。彼は生涯に1000曲もの名曲を残しているが、その人生はわずか31年。つい先日彼の年齢を上回ったばかりの筆者としては、ただただ驚嘆するのみである。
さらに、この交響曲3番が作曲されたのはわずかに18歳の時で、1815年のことである。今で言えば、ちょうど高校を卒業したくらいの年齢だが、彼は既に学校の助教員を務めている。
さて、1815年と言えば今を去ること200年余、日本では江戸時代後期の文化・文政と呼ばれる時代である。時の将軍は11代徳川家斉、二本差しの武士が闊歩していたころである。
日本史の授業めいて恐縮だが、この時代は伊能忠敬が蝦夷地を探検し(1800)、間宮林蔵が樺太を探検し(1808)、異国船打ち払い令なるものが発布さ れ(1825)、わが日本は鎖国の真っ只中にあった。そんな時代に、遥か彼方のオーストリアではベートーベン、シューベルト、ウェーバー達が活躍していた のである。さらに余談だが、シューマンが「ライン」交響曲を作曲した1850年は、ペリーが浦賀に上陸して開国を迫った3年前にあたり、攘夷か開国かをめ ぐる幕末の動乱の萌芽が兆していた時期になる。
曲は型どおり4楽章からなる。1楽章はアダージョの序奏を持ったソナタ形式で、主部ではクラリネットのかわいらしい第1テーマと、オーボエの跳ねるような 第2テーマが印象的である。2楽章は本来は緩徐楽章だが、この曲ではアレグレットであり、同時期に作曲されたベートーベンの第7、第8交響曲の影響がみて とれる。
中間部ではクラリネットの旋律が微笑ましい。3楽章はメヌエットの表示であるが、スフォルツアンドが頻出しスケルツオとしての要素も認め られる。トリオではオーボエとファゴットが鄙びた旋律を歌う。終楽章はタランテラという飛び跳ねるようなリズムにのったプレストで、頻出する転調はシュー ベルトならではである。
さて、この交響曲は演奏によって、様相が一変する。この曲をこよなく愛したトーマス・ビーチャムはゆったりとしたテンポで美しい風景を眺めながら散歩する ような演奏であるが、カルロス・クライバーは一陣の風が吹き抜けるような爽快なテンポで駆け抜けている。われらがマエストロ金山によって当団がどのような 演奏を繰り広げるか、ご期待下さい。


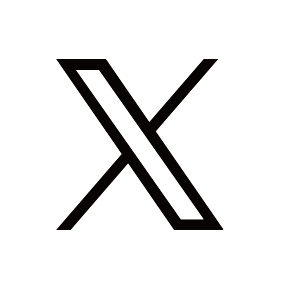
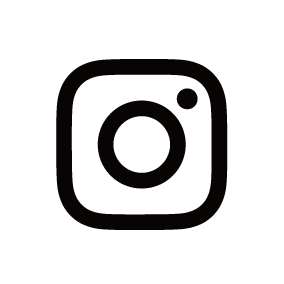

コメントを残す