ハイドン/交響曲第88 番ト長調「V 字」
ハイドンは1761年から1790年までの約30年間、ハンガリーの有力貴族であるエステルハージ家に宮廷音楽家として仕え、そこで数多くの、そして様々なジャンルの作品を残した。特に交響曲においては、常に大胆な作曲手法を試み、器楽の地位を高めることに成功した。
本日演奏する88番が作曲されたのは1787年とされている。これはちょうど「パリ交響曲(82~87番)」と「ザロモン交響曲(93~104番)」の間にあたり、おそらくハイドンがもっとも「ブイブイ言わせていた」時期でないだろうか。熱狂的ともいえる音楽愛好家であったエステルハージ家の君主から多量な作曲を依頼される、いわば「おかかえ宮廷楽長」だったハイドンの名声がひろくヨーロッパに轟き、外部からの作曲依頼が飛躍的に増加していたような頃のことである。
第1楽章は、雄大なアダージョの序奏からソナタ形式のアレグロへ導かれる。弦楽器によって第1主題が呈示され、小気味よく、しかし緊張感を保ちながら繰り返されていく。
第2楽章はオーボエとチェロの美しい重なりから始まる心地よいラルゴ。身も心も溶かしてしまいそうなその旋律に加え、中盤ではトランペット・ティンパニが独創的に用いられる。
第3楽章は装飾から始まる軽快で明るいメヌエット。途中、民族舞曲風のトリオには奇妙なバクパイプ風の効果があり、それにちなんでドイツでは88番全体が≪バクパイプ付き(mit dem Dudelsack)≫と呼ばれることも。なお日本で名の知れている≪V字(Letter V)≫という呼び名はイギリスの
出版社が付した整理用の番号がたまたまアルファベットの "V" だったからにすぎないとか。(私ははじめ、オーケストラの編成を上から俯瞰すると隊列がVの字に見えたりするのかしら、などとしょうもないことを考えていたが…)
第4楽章はアレグロ・コン・スピーリト。複雑に工夫が凝らされた、輝かしい響きを持った曲である。ソナタ=ロンド形式は美しく、高声部と低声部の弦楽器によってフォルティシモで次から次へとカノンが続いていく。属七の和音でいったん終結すると、なだれこむようにしてコーダに向かい、喜ばしいままに終わりを迎える。
≪戯れたり、興奮させたり、笑いをひきおこしたり、深い感動をあたえる、といったようなことを、ハイドンほどうまくできる人はだれもいません≫
ハイドンと親交の深かったモーツァルトは、1781年から1785年の間に作曲した6つの弦楽四重奏曲(いわゆる「ハイドン・セット」)を献呈する際、そう語ったという。この88番も、まさにそんな曲ではないだろうか。
(Vn. G. Y.)
モーツァルト/オーボエ協奏曲ハ長調
この作品は、1777 年、モーツァルトが21 歳のころに作曲されたものといわれる。当時モーツァルトは、故郷ザルツブルクで、貴族の庇護のもと宮廷音楽家という安定した身分を与えられ、明るく快活な作品を多く生み出していた。しかし、幼少期から父に連れられてウィーン、パリ、ロンドンなどで最先端の文化に触れ続けてきた彼にとって、人里離れた山中にある田舎町のザルツブルクでは物足りなかったのだろう。この年の9月、モーツァルトは宮廷音楽家を辞め、活躍の場を求めて故郷を去っていく。
この作品は、モーツァルトが書いた唯一のオーボエ協奏曲である。世界で最も有名なオーボエ協奏曲であり、今日ではコンクールやプロオーケストラの入団試験でも必ず課題にあげられる曲となっている。巷でオーケストラブームを巻き起こした漫画「のだめカンタービレ」の中でも、普段は武士然と渋い演奏をしていたオーボエ奏者の黒木くんが、のだめに恋して“ピンク色”の演奏をするという場面で使われていた。こうした人気ぶりからは信じられないことだが、この作品の楽譜は長い間行方不明であり、20 世紀に入り発見されてようやく陽の目を見ることとなったのである。
さて、オーボエの魅力といえば何よりその柔らかく深みのある音色にある。加えてこの作品では、華やかな明るさ、軽やかさ、伸びやかさ、優美さなど、オーボエの持つ様々な魅力を存分に味わうことができるだろう。技巧的な部分の多い難曲でもあるが、そこを重苦しく聴かせないところは、さすがモーツァルトである。
本日は、日本屈指のオーボエ奏者である古部賢一氏のオーボエ独奏兼指揮により、オーボエの魅力を満喫していただきたい。各楽章最後のカデンツァ(即興独奏)もお楽しみに。
第1 楽章:Allegro aperto ハ長調 4/4 拍子
協奏風ソナタ形式。オーケストラ伴奏により2 つの主題が提示された後に、オーボエが単独で2 つの主題を演奏する。短い展開部、続く再現部
を経て、カデンツァで終章する。
第2 楽章:Adagio non troppo ヘ長調 3/4 拍子
ソナタ形式。オーケストラ伴奏による序奏の後、オーボエ独奏により2 つの主題が提示されるが、展開部と第1主題の再現を欠くまま第2 主題のみ再現されて、カデンツァで終章する。
第3 楽章:Allegretto ハ長調 2/4 拍子
ロンド風ソナタ形式。冒頭でオーボエ独奏による第1 主題が提示され、第2 主題が演奏された後、これら主題が交互に繰り返されて、カデンツァで終曲する。
(Ob. K. S.)
シューマン/交響曲第3 番変ホ長調「ライン」
1850 年9 月2 日、ロベルト・シューマンはフェルディナント・ヒラーの推薦によってデュッセルドルフ市の音楽監督に就任し、ライン川湖畔の同市に転居した。9 月29 日には妻クララ・シューマンと共にライン川を遡ってケルンに旅をしており、クララの日記にもこの町の観光を楽しむ様子が記されている。
29 日の日曜日、私たちはケルンへと気分転換の旅に出た。ドゥーツの初めの景色からすっかり魅了され、とりわけ大聖堂の壮麗さは素晴らしく、より近くから見るとそれは、私たちの期待をさらに上回るものだった。…(中略)…私たちは見晴らし台へと行った。そこからのラインの眺めも本当に美しいものだった。…
夫妻は11 月4 日から6 日までケルンを再訪しているが、この旅とラインラントの町から受けた印象が変ホ長調の交響曲につながったとされ、「ライン」の名前で呼ばれている(シューマン自身はこういう表題はつけなかった。この呼称も没後のものである。しかし、シューマン自身もN.ジムロックへの手紙でラインラントの生活の様々な姿が作品の中に映し出されていることを認めている)。1248 年から建造が開始されたケルンの大聖堂は19 世紀になっても完成しておらず、高々とそびえる塔は未完成だったが、壮大なドームがシューマンにどのような感想を抱かせたかは、クララの日記や第4 楽章(後述)から想像に難くない。5 楽章からなるこの交響曲のうち、2 つの楽章には当初叙述的なタイトルがつけられた。スケルツォの「ラインの朝」、第4 楽章の「荘厳な儀式の伴奏の性格にて」がそれである。後にシューマンは「自分の心象をあらかじめ公にする必要はない」との理由からタイトルを取ってしまうが、この交響曲とラインラントとの深い関係を見ることができるであろう。また、作曲は1850 年11 月2 日に着手され12 月9 日に完成したが、11 月12 日に執り行われたケルンのヨハネス・フォン・ガイゼル大司教が枢機卿に承認された際の祝典に触発され、第4 楽章が書かれたといわれており、トーヴェイはこれを「対位法を用いた教会音楽としてはバッハ以降、最高の作品」と評している。
初演は完成翌年の1851 年2 月6 日、シューマン自身の指揮によってデュッセルドルフで行われ、同月25 日にはやはりシューマンの指揮でケルンで演奏されている。
第1 楽章
ソナタ形式で書かれたこの第1 楽章は、序奏部なしに全楽器の強奏で力にあふれた第1 主題で始まり、ライン川の雄大さをイメージさせる。95小節目から第2 主題がト短調でオーボエとクラリネットによって現れる。第2 主題を中心とした長めの展開部を経て、ホルンによる第1 主題を契機に演奏は徐々に力を増し再現部に突入する。
第2 楽章
スケルツォと名付けられているが、素朴な民俗舞踊曲風で形式としてはロンド風である。ここでも第1 楽章の主題が浸透し、その明るさと確実さが晴れやかな気分を保たせている。
ライン川沿岸ののどかな風景を彷彿とさせる。
第3 楽章
木管楽器の優しくあたたかな主題で始まり、付点リズムで上下する音型と優美な旋律が交錯する。全楽章の間奏曲のような位置付け。
第4 楽章
ホルンとこの楽章で初めて登場したトロンボーンによる主題により第1 部が始まる。多声部にテーマが出てくるため、大聖堂に響き渡るような宗教的な雰囲気がある。第2 部では主題がカノン風に扱われ派生音型が展開される。第3 部は一層壮麗になり、弦のトレモロにのって主題が壮大に復帰し、オルガン風の和声が響くうちに終結する。
第5 楽章
ソナタ形式による晴朗な楽章。明快な低音部の動きに乗って秋の収穫祭を思わせる主題から始まり、ところどころに響く金管楽器などのファンファーレが祝祭的な気分を盛り上げる。第2 主題は控えめで、展開部に第4 楽章の主題が加わって総合されていく。ホルンによる上昇音型が現れて高潮し、再現部となる。ファンファーレが出てきた後、テンポアップしてコーダに入り、輝かしくも賑やかに終盤を迎える。
(Hr. N. K.)


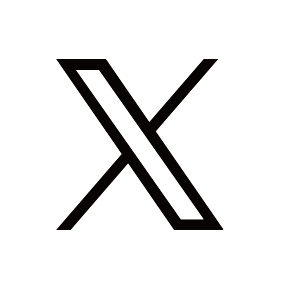
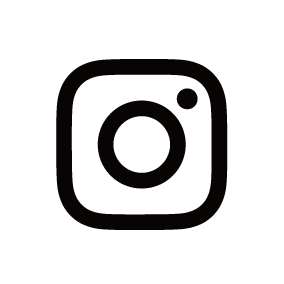

コメントを残す