パリー/ブラームスへの哀歌
英国の作曲家というと、多くの場合ホルストやエルガーを思い浮かべるであろう。しかしパリーについて調べてみると、彼らに引けをとらぬ偉大な功績を残していることがわかる。
1848 年に生まれたパリーは、若かりし頃保険会社として知られるロイズに勤務していたが、1884年にロンドン王立音楽大学の創立と同時にその教授に迎えられ、1894 年には学長に就任、その後オックスフォード大学音楽科の教授も兼務。ヴォーン・ウィリアムズやホルストらを育てた教育者であるとともに、その力強い作風はエルガーにも影響を及ぼしており、近代イギリス音楽界の礎を作った作曲家であると言えよう。
彼は5つの交響曲、ピアノ協奏曲、多くの室内楽曲や声楽曲、音楽に関する数々の著作や論文を残している。ワーグナーと親交があったものの、その作風はドイツ・ロマン派においても特にブラームスの影響を受けたとされる。実際に、交響曲の5番を聴いてみると、やはりその響きは純粋なイギリス音楽ではなく、ブラームスの面影が多くの場面で感じられる。また晩年の作品であるオルガン伴奏による聖歌「エルサレム」は、エルガーの編曲によるオーケストラ伴奏版が、ロンドンで毎年開催される「プロムス」の最終夜に国家とともに必ず演奏されており、英国では誰もが知る彼の代表作である。
そして本日演奏する「ブラームスへの哀歌」は、彼が最も尊敬していたブラームスが没した1897年に作曲されたもので、特に展開部におけるクラリネットによる美しい旋律や、ドイツ的ともイギリス的ともとれる、終結部の響きが印象的である。なお、本作品はパリーの生前に演奏されることはなく、1918 年の彼自身の追悼コンサートにおける演奏が初演となった。 (K. T.)
ダルベール/チェロ協奏曲 ハ長調
「オイゲン・ダルベール(Eugen d’Albert)」とは、不思議な名前である。彼はスコットランドで生まれ育ったというが、「オイゲン」という響きはいかにもドイツ風、「d’Albert」というつづりはいかにもフランス風である。ドイツ音楽の演奏で名演を残した大ピアニスト、ウィルヘルム・バックハウスが師事したのが他ならぬダルベールであるが、ではそのダルベールが書いた音楽とは?ドイツ的なものを体現した作品なのだろうか?否、スコットランドで生まれたフランス風の名前の人間が、緊密な構成の曲を書くのだろうか?気になるところであるが、彼のチェロ協奏曲に触れる前にまずはその生い立ちを紐解いてみよう。
ダルベールは1864 年にスコットランドのグラスゴーに生まれた。作曲家である父はドイツ生まれのイタリア系フランス人、母はイングランド人である。幼少期から独学で音楽を学んだ彼は神童と称され、ロンドン王立音楽院に入学した。奨学金を得てウィーンに留学した1881 年にはハンス・リヒターの紹介でフランツ・リストに出会い、翌年からワイマールでリスト門下となる。その後、ピアニスト・作曲家として活躍し、1932 年に67 歳で亡くなった。ドイツ移住後に彼はドイツの文化、音楽に親和性を感じ、自らをドイツ人であると宣言した。私生活では6度の結婚を経験するという波乱に満ちた生涯だったようで、強烈な個性と激情を秘めた人物像が浮かんでくる。
ピアニストとしての彼は幅広いレパートリーを持ち、 中でもベートーベンやリストの評価が高かった。師であるリストのみならず、ブラームスもその才能を認めていたという。劣悪な音質ではあるが、彼が演奏したベートーベンやリスト、ショパン、さらには彼にとっては現代音楽であったドビュッシーの録音が今に残されている。作曲家としての彼は多産であった。現在では演奏される機会は少ないが、交響曲や協奏曲を含むピアノ曲、室内楽や歌劇など多くの作品を残している。彼の唯一のチェロ協奏曲は1899 年に作曲され、名チェリストのフーゴ・ベッカーに献呈された。今日では演奏機会が減ってしまったが、かつてはチェリ
ストにとって重要なレパートリーであったという。
この作品は全曲が切れ目なく演奏される形をとっており、シューマンのチェロ協奏曲からの影響をうかがわせる。曲はまずAllegro moderato で始まり、独奏チェロの分散和音を背景にオーボエが魅力的な旋律を歌い始める。この第1主題はクラリネットに引き継がれた後、ようやく独奏チェロに渡される。
この協奏曲が、独奏の技巧に焦点を当てるというよりは、独奏とオーケストラを一体として扱うという性格を有していることがこの冒頭部分から早くもわかるだろう。中間部のAndante con moto は別世界の音楽である。夢見るような旋律を、またしても独奏者に先立ってオーケストラが提示するところから始まる。曲想は次第に盛り上がり、上昇への意思を見せるような音階の連続、そして沈潜。音楽はtranquillo となり、天上に昇華するようなフレーズが奏されると、突如Allegro vivace に突入する。嵐のような音楽が過ぎ去ると全曲の冒頭部分が回帰し、力強く全曲を締めくくる。
彼の生い立ちに由来しているのだろうか、筆者はこの作品に(切れ目なく演奏されるという点以外にも)シューマン的な要素やイギリス音楽の要素など様々なものを感じる。皆さんはどうお感じになるだろうか? 本日の演奏を楽しみにしていただきたい。 (M. Y.)
ブラームス/交響曲第1番 ハ短調
「僕の交響曲は長ったらしくて、その上ちっとも愛すべき作品ではないんだよ」(カール・ライネッケへの手紙より)
ブラームスの最初の交響曲は、20 年以上に及ぶ構想から産み出されたものであることはあまりにも有名である。
北ドイツ(当時の国名は「プロイセン」)の港町・ハンブルグの貧民街に生を受けたヨハネス・ブラームスは、弱冠ハタチにしてシューマンの熱烈な歓迎とプレッシャーを受けつつも、「ドイツ(語の)・レクイエム」により国内外の知的階級の期待に応えた(33 歳)。「ハンガリー舞曲集」の興行的大成功を経た1872 年には39 歳の若さでウィーン楽友協会の芸術監督に就任していることからも、社会的にも経済的にも充分な地位を得た稀有な音楽家となっていたことがうかがえる。
「長すぎる」作曲期間にまつわるエピソードがあまりにも有名であり、楽聖・ベートーヴェンが打ち立てた「交響曲」という名の金字塔に相対する精神的闘
争や、苦悩からの勝利・解放へ、といった先入観とともに語られがちなこの曲だが、実際に通して聴いて(演奏して)得られる印象はやや異なったものである。
既に楽壇において揺るぎない地位を占めていた青年ブラームスにとって(写真参照)、交響曲の発表は「満を持して」のものであったに違いない。
第1楽章
冒頭、全管弦楽(in Es ホルン2本、トロンボーン除く)により開始される序奏(Un poco sostenuto)では、ティンパニ、コントラバス、コントラファゴットによるC 音の連打が印象的であるが、弦楽器の上昇進行と木管楽器の下降進行とがぶつかり合う緊張感もまた推進力となっている。Allegro となる主部ではヴァイオリンに第一主題が出るが、次第に運命的な動機「タタタ・ター」の支配力が強くなる。
コーダではやや速度を落としながらも序奏よりはやや早く(Meno allegro)、長調に転じた第一主題が穏やかに結ばれる。初演当初、コーダは冒頭と同じくpoco sostenuto であったが、あまりにも「遅く」演奏されてしまうことを恐れ、速度記載が変更されたという。なお、この楽章の草稿は1862 年の段階でシューマン未亡人(嫌な言葉だが)クララに送られている。
第2楽章
柔らかくあたたかいホ長調。哀愁を纏うオーボエによって謳い上げられる旋律を、クラリネットがたゆたいながらも受け流すが、ついには交響曲史上前代未聞ともいえるオーボエ、ホルン、さらには独奏ヴァイオリンのトリオ・ソロによる直球勝負となる。愛するもの、あるいはかつて愛したものへの憧憬、か。
第3楽章
変イ長調。メヌエットでもスケルツォでもないun poco Allegretto e grazioso。前楽章に続きつつも、ややそっけない「うつろい」がたまらない。
第4楽章
弦楽器によるピッチカートが特徴的な序奏に続き、アルプホルン(アルプスの角笛)に由来するとされる雄大なホルンの旋律が現れる。歌はフルートに引き継がれ、ここまで温存されてきたトロンボーンによるコラールの響きを導く。人間目線から 「聖なるもの」 への遷移だろうか。続いて第九『歓喜の歌』 主題をまざまざと想起させる主題が導かれ、ベートーヴェンとの比較を確信犯的に聴き手に強いる。コーダではコラールが再現され、力強く曲を閉じる。
頑迷とも捉われかねないほどに徹底された構成美と、あこがれの発露とも思える剥き出しの感情とが等しく内包され、対立しつつも高次元に昇華された作品であるとは言えないだろうか。
「彼は人間を愛し、また求めていましたが、他人が彼を求めたときには自分の殻に閉じこもってしまうのです。彼は与えることが好きでしたが、自分に対する要求や期待は撥ねつけました」(シューマン夫妻の遺児、四女・オイゲーニエによるブラームスへの回想より)
*
かつてブルーメンでは第12 回( 1998年) ~ 17回定期( 2000年) の4回にわたり「ブラームスチクルス」と銘打って演奏会を行い、その後もドイツ・レクイエム、管弦楽曲のほか、「2番」「4番」は再演の機会にも恵まれた。創立20 周年には幸いにもベートーヴェンの「第九」をとりあげることもできた。当時のチクルスを経験したメンバーは約15 年を経た今も少なくなく、かつ、多くの新しい仲間を迎えたオーケストラとしてこの曲をふたたび演奏できることは極めて喜ばしい。「いぶし銀」などと称されることもある彼の作品には、確かに若かりし頃には気づけなかった「なにか」が含まれているようだ。斜に構えがちな若者はそのような「容易に解釈できないもの」に惹かれるのかもしれない。いまやすっかり「第1番」作曲当時のブラームスと同年代となり、「お○゛さん」の呼称をもはや免れられない者として、「与えられた」音符に刻み込まれたものをそれぞれの「想い」として表現できれば幸いである。
参考文献 ・新潮文庫 カラー版 作曲家の生涯『ブラームス』 三宅幸夫
・音楽之友社『ブラームス、4つの交響曲』 ウォルター・フリッシュ(天崎浩二/訳)
(I. T.)


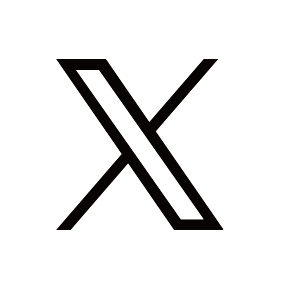
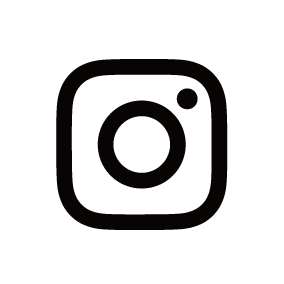

コメントを残す