ベートーヴェン/「レオノーレ」序曲第3 番
一切の光も届かぬ秘密の地下牢、そこに無実の罪で投獄されているフロレスタンは、レチタティーヴォで悲痛な叫びをあげたのち、アリア「人生の春の日に」を歌う──ベートーヴェン唯一のオペラ『フィデリオ(レオノーレ)』第2 幕のこのような冒頭シーンをなぞるかのように、「レオノーレ」序曲第3 番の序奏でも、ユニゾンによるショッキングな強奏から、聴き手を地下深くへといざなうかのようなゆっくりとした下降音型ののち、このアリアの冒頭部分が引用される。ソナタ形式の主部の第2 主題にも使用されるこのアリアは、絶望の淵にあるものの嘆きとは思えないほど悲痛さとは程遠い温和で穏やかな音調にあふれているが、それはまさに自らの正義のために殉ずるというフロレスタンの高潔な精神を、ベートーヴェンが鋭い筆致で描き出したものにほかならない。
『フィデリオ』のストーリーはさらに以下のように進む──悪徳刑務所長ドン・ピッツァロの悪事を大臣に告発しようとして逆に囚われてしまったフロレスタン。その妻レオノーレは男装しフィデリオと名乗り、ピッツァロのもとで下働きをしながら夫を救出するチャンスを狙う。ピッツァロは大臣が刑務所へ視察に来る前にフロレスタンを殺してしまおうとするが、レオノーレは身を挺して夫をかばう。絶体絶命のその時、大臣の到着を知らせるトランペットが高らかに鳴り響き・・・かくしてピッツァロの悪事は暴かれ、フロレスタンの正義と、レオノーレの夫への愛が謳われ、歌劇は大団円を迎える──この、フロレスタンとレオノーレの窮地を救う「デウス・エクス・マキナ(機械仕掛けの神)」としてのトランペットもまた、序曲のちょうど真ん中に引用されている。序曲全体がオペラの第2 幕を凝縮し、予感させるような構造になっているのである。
演奏会の序曲として取り上げられることの多いこの「レオノーレ」序曲第3番だが、こうして劇中のアリアとファンファーレの意味を踏まえてみると、堂々たるハ長調の部分もいっそうの力強さをともなって響いてくるのではないだろうか。
(Perc. W. N.)
モーツァルト/ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調
ヴァイオリンとヴィオラのための協奏曲
コンチェルト
風たちが奏づるよ水無月/永井陽子『小さなヴァイオリンが欲しくて』
モーツァルトをこよなく愛した永井陽子の歌。のっけから短歌の引用で恐縮だが、この曲は私にとってまさに「風」が舞う曲。風がさっと吹くように始まり、風に乗って空を飛んでいくような、のびやかで軽やかな曲である。
この曲はモーツァルト23 歳、1779 年の夏に作曲された。それはモーツァルトにとって、どのような時期だったのだろうか。
この2 年ほど前から、モーツァルトは旅に出ていた。アウグスブルク、ミュンヘンなどを経て、マンハイムとパリに滞在。安定した収入と就職先を求めての長旅だったが、これといった成功もなく、やりがいのある職も得られなかった。しかも、つきそってくれていた母が旅行中パリで病死。悲しみのうちにパリをあとにし、帰国途上で立ち寄ったマンハイムでは恋人の心変わりを知る。母の死と失恋という大きな挫折と喪失を経て、悄然とザルツブルクに帰ってきたのが、この1779 年1 月だった。
帰郷すると、モーツァルトは、父が用意したザルツブルクの宮廷オルガニストという新しい就職先におさまった。当時のモーツァルトの暮らしぶりは、姉や友人の日記に記録されているが、職務以外は散歩したり、友人と室内楽やカード遊びをしたり、平穏で刺激の少ない毎日だったようだ。
さて、そんなもぬけの殻のような時期であるが、当時の作品にはマンハイムやパリの影響が色濃くあらわれていると言われており、傑作も多い。
この協奏交響曲(シンフォニア・コンチェルタンテ)という形式自体、当時マンハイムやパリで流行していたものなので、この曲はモーツァルトの旅土産と言ってもよいだろう。「協奏交響曲」とは、複数の独奏楽器を擁した協奏曲のこと。それぞれの楽器の特性をいかした複数楽器の独奏とオーケストラの協奏は、聴いていてとても楽しい。
なお、モーツァルトはこの曲で、独奏ヴィオラに、半音階高く調弦する指示を残している。弦の張力を強くすることで音色を明るく華やかにするため、と言われているが、本日はこの方法を用いず、普通の調弦で演奏する。ヴァイオリンほどの明るさはないが、穏やかで優しい本来のヴィオラの音と、華やかなヴァイオリンの音の協奏を楽しんでいただきたい。
第1 楽章 Allegro maestoso
堂々とした第1 主題、牧歌的な第2 主題が演奏され、力強いコーダとなったあと、オクターブでふわりと浮き上がるように独奏楽器が登場。2
つの独奏楽器は、万華鏡のように少しずつ色を変えながら交互に歌い、活発な応酬を経て、最後は輝かしく集結する。
第2 楽章 Andante
深い憂いと悲しみをたたえた楽章。独奏楽器が慰めあうように対話する。途中少し光がさすが、すぐ短調に戻る。
第3 楽章 Presto
一転して快活なロンド。独奏楽器の丁々発止なかけ合いは、いたずらを競い合う子どものよう。いきいきと弾むように進んでいき、コーダで独奏楽器のかけ合いが頂点に達すると、曲は多幸感に満ちたまま華やかに閉じられる。
(Vn. S. H.)
シューベルト/交響曲第8(9)番ハ長調「ザ・グレート」
【番号】
シューベルトの7 番目以降の交響曲には、生前には番号が付与されず、番号の扱いが様々である。この交響曲は20 世紀初頭までは「第7 番」と呼ばれ、20 世紀半ばに作成された作品目録では9 番目、そして20 世紀後半に改定された目録では8 番目であり、国際シューベルト協会では「第8番」としている。現在では昔の通称との混乱を防ぐために「第9 番」との併記が多く、今回のプログラムでは「第8(9)番」と記載している。
【副題】
通称「ザ・グレート」と呼ばれている。シューベルトは他にもう一つハ長調の交響曲第6 番を書いており、後世になって区別するために「大きいほうの」ハ長調の交響曲と呼ぶようになったため、この呼び名がついた。
このようにもともとは第6 番に比べて大きいという程度の意味しか持っていなかったが、曲自体はその名にふさわしい曲想や規模を持っている。
指示通りに演奏すると1 時間以上かかる大曲であり、現代では珍しくないが、19 世紀前半においては通常想定される枠をはみ出た存在である。
【初演】
作曲は、1825 年頃と言われている。シューベルトはウィーン楽友協会へ提出したが、長すぎるとの理由で当時は演奏されなかった。
シューベルトの死後の1839 年に、その部屋を管理していたシューベルトの兄フェルディナントの元へシューマンが訪れ、自筆譜を確認した。そしてシューマンの友人メンデルスゾーンの指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏によって初演された。
【天国】
シューベルトは「歌曲の王」として知られている。この交響曲においても、全編に渡って美しい旋律を綴っている。シューマンは「天国的長さ」と評したが、単に長いのではなく、単なる繰り返しでもなく、美しい旋律が「天国のように」どこまでも続いているのである。その美しさをあげればきりがない。弦楽器はもちろんのこと、1 楽章・2 楽章の両楽章とも冒頭から2 フレーズ目を担当するオーボエ、2 楽章中間つなぎの部分のホルンなど。
特に同時代の他の曲に比べて目立つ点は、「神の声」とも言われるトロンボーンの多用である。天使となり悪魔となり、あらゆる箇所にその姿を現す。
【影響】
ベートーヴェンから影響を受けていることは想像に難くない。前年1824 年の作である交響曲第9 番からは、トロンボーンの活用、そして主題の引用など明らかな関連がある。一方、シューマンは自筆譜を確認した翌々年1841 年に交響曲第1 番を作曲、初演を指揮したメンデルスゾーンは翌年1840 年に交響曲第2 番を作曲しており、これらへの影響が想像される。
【楽章】
第1 楽章 Andante – Allegro ma non troppo
序奏は、遠くから鳴るホルンのユニゾンによるテーマから始まる。続いて木管、弦楽器と受け渡され、そしてトロンボーンを中心として最前面にテーマが押し出される。主部は付点のリズムによる主題、物哀しい主題、トロンボーンによって提示される力強い上昇音形の主題があり、それぞれに3 連符を絡めて構成される。
第2 楽章 Andante con moto
スタッカートを特徴とする動機を持つ主題A と、下降音形のレガートを主体とした主題B とによる、ABABA の形式である。1 回目の主題B から2 回目の主題A へのつなぎの部分のホルンは、シューマンが「天の使い」と評した美しさである。
第3 楽章 Scherzo Allegro vivace
同時代としては大掛かりな、スケルツォ楽章である。力強い主部とシューベルトらしい歌で綴られるトリオとで構成されている。
第4 楽章 Finale Allegro vivace
自由なソナタ形式によるフィナーレである。1 楽章と同じく付点のリズムと3 連符の組み合わせで構成される。天国的と称される交響曲の締めに相応しく、ソナタ形式を基本としながらスケールを大きくした構成となっている。ベートーヴェン交響曲第9 番の歓喜の主題を改変して引用しており、ベートーヴェンに対するオマージュと考えられている。
【今日】
ドイツ古典からロマン派を中心として活動してきたブルーメンの、20 周年の記念に相応しい曲である。指揮者を踊らせるような第3 楽章・第4
楽章は、第1 楽章・第2 楽章でじっくり旋律を歌った後でこそのものである。「ザ・グレート」という副題とは相反する、「短すぎる、まだ聴いていたい」という気持ちを、ホール全体に満たしたい。
(Hr. M. S.)


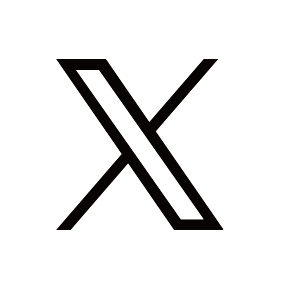
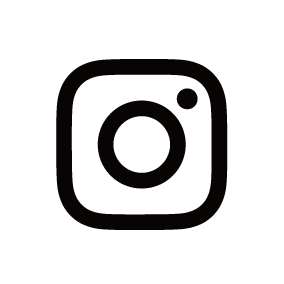

コメントを残す