ウェーバー/歌劇「魔弾の射手」序曲
ドイツに生まれ、父の率いる歌劇団で各地を巡る幼少期を過ごしたウェーバー。13 歳にしてオペラを作曲し、17 歳のときには劇場の楽長に就任、とその才能は早くから開化。その後、プラハの名門歌劇場の指揮者に就任し、傾きかけていた歌劇場を見事に再興させ、ドレスデン歌劇場の音楽監督に抜擢される。ピアノ奏者でもあり、身体は小柄だったが10 度の和音をとらえる長い指を持ち、素晴らしい演奏技術を誇った。
さて、イタリアオペラが主流だった19 世紀初頭のヨーロッパ。そんな中に登場した、ドイツ人による、ドイツ語を使った、ドイツを舞台とし、ドイツの人々に古くから読まれてきた民話が元になっているウェーバーの歌劇「魔弾の射手」。
舞台は深い森―。主人公・狩人のマックスは、恋人アガーテと結婚するため、射撃大会に出るも、一発も命中しない。そんな様子を見たアガーテの父から、明日の射撃会の結果次第ではアガーテとの結婚を認めないと言われる。
悪魔と契約し、アガーテを生け贄にしようと企てていた狩人のカスパール。カスパールはマックスをそそのかし、明日の大会で魔弾の力に使うよう仕向ける。マックスは迷ったが、7つの魔弾を造り大会で使うことに。
翌日の射撃大会。6発は的に的中。7発目をマックスが撃ったとき、その弾はアガーテに!!…と見せかけて、カスパールに命中。
事の真相を打ち明けたマックスは永久追放の処分が下されるが、聖なる隠者の助言により1年間の試練を与えられ、行いが正しければアガーテとの結婚を許されることに。
いつの時代もハッピーエンドとホルンは愛されるものなのでしょうか。日本の童謡「秋の夜半」(あきのよわ)でも使われている冒頭のホルンの旋律。何度聞いてもしびれます。
(Tp. N. I.)
シューベルト/交響曲第5番 変ロ長調
交響曲第5番が作曲された1816 年は、19 歳のシューベルト(1797-1828)にとって大きな転機となる年であった。それまで勤めていた父親の学校での教職を辞し、音楽に生きることを志したのである。当時はまだ出版社から楽譜が出ることもなかったシューベルトを、友人たちは衣食住にわたり惜しみなく援助した。そのおかげでシューベルトは次第に作曲のみに専念するようになり、彼らの家では私的な演奏会が夜ごとに開かれた。
半年ほど前に作曲された交響曲第4番「悲劇的」のドラマチックなメロディーとは打って変わり、この第5番ではシンプルで軽快なリズムやフレーズが印象的である。オーケストラ編成の小ささ、調性の展開、それに個々のフレーズ等、多くの点でモーツァルトとの類似性が指摘されている。シューベルト自身がおそらく意図して、敬愛するモーツァルトへのオマージュとして作曲したのであろう。
実際、シューベルトが同年にモーツァルトの弦楽五重奏曲を聴いた日の日記では、以下のようにモーツァルトを絶賛している。「おお、モーツァルト! 不滅のモーツァルト! どれだけ多くの、おお、どれほど尽きることのない、軽やかでより良い生の刻印を、慈悲深くも我々の魂に刻み付けたことか!」
第1楽章 Allegro 変ロ長調、ソナタ形式
シューベルトの交響曲では初めて緩徐な序奏が存在せず、管楽器による4小節のカデンツのみが導入部である。5小節目から提示される第1主題は、軽快なスタッカートのリズムを伴った上昇形の分散和音であり、楽章を通じたモチーフとなっている。通常のソナタ形式とはやや異なり、再現部では変ロ長調の下属音である変ホ長調で主題が演奏される。
第2楽章 Andante con moto 変ホ長調、ロンド形式
歌曲のような甘美な主題が2回提示されるや否や、変ハ長調へと転調する。この転調はシューベルトの作品に特徴的なものであり、単にモーツァルトの模倣をしているわけではないことがうかがえる。その後も転調を繰り返し、ロ長調、短いながらも印象的なト短調を経て変ホ長調に戻る。
第3楽章 Menuetto. Allegro molto ト短調
シューベルトの他の交響曲のメヌエットとは趣の異なる、スケルツォ風の楽章。むしろ、モーツァルトの交響曲第40 番の第3楽章との類似がしばしば指摘される。ト長調のトリオは全体として穏やかで、低弦楽器の持続音により、どこか田園的な印象も漂う。
第4楽章 Allegro vivace 変ロ長調、ソナタ形式
楽章を通して舞曲のような軽快なモチーフで構成されており、こちらはハイドンの交響曲との類似性が指摘されている。
(Cb. K. W.)
ドヴォルザーク/交響曲第8番 ト長調
ドヴォルザークは、後期ロマン派のチェコの作曲家であり、スメタナと並びチェコ国民楽派の代表格とされる。ブラームスに才能を認められ国際的な人気作曲家となったこと、その後アメリカに渡り活動し、ネイティブ・アメリカンの音楽や黒人霊歌を作品に吸収したが、郷愁に駆られ帰国したことは、逸話として有名である。
一般的にドヴォルザークの作曲家としての特色は、ブラームスとともに標題音楽の支配する新ロマン主義の19 世紀後半において、「古典的な絶対音楽の形式を重んじながら、民族的な要素を結び付けたこと」が挙げられるが、一方でオペラや交響詩にも背を向けず、歌曲・宗教曲等、広範囲な創作を残している。どのような背景の中で、独自の作風を醸造させて行ったのか、生い立ちを追ってみたい。
―1841 年プラハの北部、北ボヘミア地方に生まれる。生家は肉屋と宿屋を営んでいたが、父はツィターを演奏し、民族音楽が周囲にある環境で育つ。小学校に通い始めヴァイオリンの手ほどきを受けると、アマチュア楽団のヴァイオリン奏者となり、音楽的才能を見せ始めたが、父親は家業を継がせるつもりであったため、12 歳で伯父の住むズロニツェという町へ肉屋の修業に行かせてしまう。ところが、この町の職業専門学校の校長は、教会のオルガニストや小楽団の指揮者を務め、教会音楽の
作曲も行う人物で、ドヴォルザークにヴァイオリン、ヴィオラ、オルガンの演奏の他、和声学をはじめとする音楽理論の基礎も教えることとなった。
その後、経済的な理由により、父親はドヴォルザークを退学させ家業を手伝わせようとしたが、伯父の援助により、16 歳でプラハのオルガン学校へ進むこととなる。
19 歳で卒業すると、ホテルやレストランで演奏する楽団のヴィオラ奏者を経て、新しく建設された国立劇場のオーケストラのヴィオラ奏者となる。この頃よりモーツァルト、ベートーベン、シューベルトの技法を学び、室内楽・交響曲の作曲を始めるが、楽団員として実地の音から学び、独学で作曲技術を獲得していく。
またオペラの分野についても、オーケストラピットの中でチェコ国民オペラの誕生に立ち会う中で、創作意欲を高めていく(1866 年には国民劇場にスメタナが指揮者として着任、歌劇「売られた花嫁」の初演には、ヴィオラ奏者として参加している)。ただし、専ら興味を覚え、影響を受けたのはワーグナー作品であった。
作曲に専念するために劇場の職を辞したのは30 歳のときであり、その後、33 歳で教会オルガン奏者の職を得、さらにオーストリアの国家奨学金を受け、金銭的に余裕もできる(当時ボヘミア地方が政治的にハプスブルク帝国の属国下にあり、チェコ人も奨学金の適用対象となった)。
何より、審査員であったブラームスの知遇を得たことの影響が大きく、作風の面でもワーグナーの影響からも脱していく。以後、ドヴォルザークはブラームスの支援を受け、国際的な作曲家としての一歩を踏み出すこととなる。かくして、円熟期のドヴォルザークは、ベートーベン、シューベルトなどの古典音楽に育まれた音感の上に、夢中になったワーグナーの語法、ブラームスから直接学んだドイツ音楽の構成法、幼児(幼時?)から身に着けた民族的な舞曲や民謡の色彩感、それらのものを渾然と消化していったのである。
本日演奏する交響曲第8番は、多忙な音楽家として活躍するなか、1889 年48 歳の夏から秋にかけて、別荘の田園生活のなかで構想を得て作られた。ブラームスの模倣から距離を置き、独自のボヘミア色に溢れている。
1890 年2 月2 日プラハでの初演は、ドヴォルザーク自身によって行われ大成功を収めた。
第1楽章 Allegro con brio ト長調
チェロによる短調の美しい序奏で始まり、フルートによる第1主題から主部となる。副主題は2
つあり、展開部、再現部を経て、最後はト長調で明るく終わる。
第2楽章 Adagio ハ短調
弦のやわらかい旋律で始まる。不規則な三部形式をとり、随所に小鳥の鳴き声のようなフレーズ
が現れる。最後は明るくハ長調で終わる。
第3楽章 Allegretto grazioso ‒ Molto vivace(加えてOK ?) ト短調
美しい旋律で始まるワルツ風の舞曲。中間部の旋律は、歌劇「がんこな連中」からとられたもの。
ト長調・4拍子となる力強いコーダもまた同じ素材をもとにしている。
第4楽章 Allegro ma non troppo ト長調
主題と18 の変奏。トランペットの輝かしい序奏に続いてチェロが主題を奏でる。変奏曲を交響曲の終楽章に持ってくることは、ドヴォルザークの交響曲の中ではこれが唯一である。
(Va. H. S.)


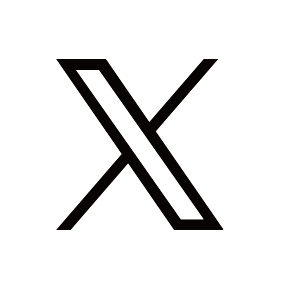
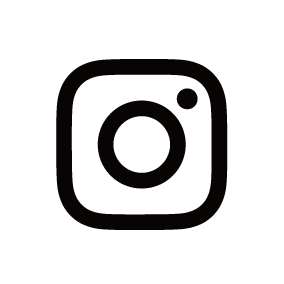

コメントを残す