武満 徹/弦楽のためのレクイエム
武満 徹(1930-1996)は20世紀の日本の作曲界で国際的に成功した作曲家のひとり。65年間の生涯を閉じたのが1996年2月20日。現在を生きる我々とも時を重ねている作曲家である。
本日演奏する「弦楽のためのレクイエム」は、タケミツの初期の作品である。1957年5月に東京交響楽団からの委嘱により作曲され、同年6月20日に日比谷公会堂で東京交響楽団の第87回定期演奏会にて上田仁指揮により初演された。当初国内での評価は決して芳しいものではなかったが、1959年に来日中のストラヴィンスキーの耳に留まり Very Intense との評を得たことを機に状況が一転。タケミツの名と作品はアメリカそしてヨーロッパへと広まっていき、ニューヨーク・フィル125周年記念委嘱作品『ノヴェンバー・ステップス』などで国際的な成功を収めるに至る。また、タケミツの作曲の幅はオーケストラ作品のみにとどまらず、勅使河原宏監督「利休」などの映画音楽、テレビ番組、コマーシャルなど多岐に渡っている。
さて「弦楽のためのレクイエム」。レクイエムという曲名がつけられているが、伝統的なレクイエムの形式ではなく、単一主題による、レント-モデラート-レント という自由な三部形式で構成されている。この曲の解説にはタケミツ本人の言葉が最も相応しいと思われるので、一文を引用させていただく。
「はじめもおわりもさだかでない、人間とこの世界をつらぬいている音の河の流れの或る部分を、偶然に取り出したものだといったら、この作品の性格を端的に明かしたこととなります」
我々は三次元の空間と一次元的な時間の流れの中で生きている。しかし、それぞれがこの実在空間とは別の次元で精神世界を持っている。タケミツが偶然に切り出した音の河は、精神世界を絶え間なく流れている音ではないかと。みなさまの音の河はいかなるものでしょうか?
我々の演奏を通じて譜面から浮かびあがるタケミツの音の河。みなさまそれぞれにも何かを感じていただければ幸いである。
シューベルト/交響曲第4番 ハ短調 「悲劇的」
シューベルトの歌曲は、親しみやすい『野ばら』や『音楽に寄せて』の他、『魔王』のように劇的なものや『セレナーデ』のように叙情的なもの、さらには『菩提樹』を含む連作歌曲『冬の旅』等々、有名なものだけでも挙げてもきりがないほど多くの名作にあふれている。そして31年というあまりに短い一生の間に書かれた歌曲は600をゆうに超え、その膨大なレパートリーは、繊細で美しい旋律と妙味に満ちた伴奏とによって、魅力あふれるドイツ・リートの世界を紡ぎ出しており、「歌曲王」の名にふさわしい足跡を音楽史上に残した。もちろんこれら歌曲の持つ叙情性はそのまま器楽曲や管弦楽曲にも通底しており、シューベルトの音楽全体の大きな魅力となっていることは言うまでもない。
1797年ウィーンに生まれ、幼いうちからその音楽的才能を発揮していたシューベルトは、11歳にはすでに親元を離れコンヴィクトと呼ばれる王立寄宿制学校へ入学し、かのサリエーリのもとで作曲を学んだ。そして1813年に16歳でコンヴィクトを去ったのち、初等教員養成学校へ1年ほど通い、父が校長を務める学校で教師の職につく。そして数年の間そこで教鞭を執るかたわら、いつかはモーツァルトやベートーヴェン、あるいは師サリエーリのような大作曲家になれることを夢見て作曲にいそしんでいた。この頃のシューベルトの並々ならぬ意欲は膨大な創作量となってあらわれている。とくに1815年には『魔王』や『野ばら』を含む145の歌曲をはじめ、数々のピアノ曲の他、交響曲2曲やミサ曲2曲なども作曲されたが、なかでも注目すべきはこの年に4つもの劇場作品が書かれていることである。「歌曲王」としての多大な成果の陰に隠れてしまいがちであるが、シューベルトには生涯にわたってオペラあるいはジングシュピールの作曲家としての成功も夢見つつ、結局叶えることができなかったという側面もあったことを見逃してはならない。
さて、今回演奏する『悲劇的』交響曲はその翌年である1816年に書かれたものである。当時のシューベルトが「オペラがダメなら交響曲で勝負だ!」と考えていたかどうかはわからない。しかし自ら総譜に「悲劇的」と書き込んだこの交響曲は、モーツァルトやハイドン、そしてベートーヴェンを範と仰ぎつつ、立派な交響曲を書き上げようという若きシューベルトの意気込みにあふれている。とくに、楽章および旋律を短いモチーフの積み重ねによって構成しようとする意図が明らかであるほか、楽章間に連関を与える工夫として、第一楽章主要主題と第二楽章副次主題、そして第三楽章のトリオが、すべて同じモチーフで開始されている。また他方で、楽器同士の対話や情景描写的な伴奏など、交響曲というよりはむしろオペラを念頭に置いているような書法も随所にあらわれており、シューベルト自身のオペラへの強い関心や、かつての大オペラ作家サリエーリからの強い影響も見受けられる。
第一楽章:アダージョ・モルト-アレグロ・ヴィヴァーチェ 重苦しく沈鬱な序奏がやや長めに続いたのち、憂いを含んだメランコリックな主要主題が弦楽器によって奏される。副次主題は明るく伸びやかだが、そのかげで休むことなく刻む伴奏は安らぎを拒むかのようである。全体にモーツァルトを思わせるような素朴な構成だが、時折姿を見せる劇的で大胆な転調が、聴くものの意表を衝く。そして意外にもハ長調で明るく締めくくられる。
第二楽章:アンダンテ
ベートーヴェンに倣ったのか、長三度下の変イ長調が使用されている。優美な旋律による甘美で情緒豊かな主部と、調を変えて二度あらわれる劇的な要素をもった短調の中間部分とが対照的である。
第三楽章:メヌエット、アレグロ・ヴィヴァーチェ-トリオ
弱拍へのアクセントとヘミオラのリズムが特徴的な、テンポの速いメヌエット。トリオは木管楽器が伸びやかに歌い上げる。
第四楽章:アレグロ
木管楽器の呼ぶ声に導かれ、第一楽章と同じ雰囲気を持った旋律が駆け抜ける。ざわめくような伴奏にのせてヴァイオリンと木管楽器とが対話する副次主題はオペラのワンシーンを見ているかのように魅惑的である。そして第一楽章と同様、短調で開始しながら長調で終止し、決然と(あるいは投げ遣りに?)叩きつけるようなハ音の斉奏で全曲が閉じられる。
マーラー/交響曲第4番 ト長調
ボヘミアの片田舎出身のユダヤ人であったグスタフ・マーラーが、オーストリア=ハンガリー二重帝国の帝都ウィーンの宮廷歌劇場の指揮者に任命されたのは1897年、37歳の春であり、同年秋には同歌劇場の音楽監督、翌年にはさらにウィーン・フィルハーモニー管弦楽団指揮者をも兼任している。当時のウィーンは政治・文化両面において世界の中心のひとつと言ってよく、市民はハプスブルグ家700年の伝統と、建築・絵画・音楽・デザインなどの新芸術の波が共存する世紀末ウィーンの繁栄を謳歌していた。この第四交響曲は、マーラーがそのウィーン音楽界に「指揮者として」君臨したころ、すなわち1899年と1900年の夏季休暇中に作曲され、1901年、ミュンヘンにて自身の指揮で初演されている。しかしながら、第四楽章のみは別途『子供の魔法の角笛』歌曲集の『天上の生活』と題して1892年に書かれ、単独で演奏もされている。当初は第三交響曲の第七楽章に収めることが意図されていたというこの曲のために、新たに第一楽章から第三楽章がいわば「後付け」された。このため先行する3つの楽章には第四楽章の主題が随所に散りばめられており、それぞれが『天上の生活』を導き、あるいは引き立てる役割を果たしている。
第一楽章:ほどよい速さで、急がずに ト長調 4/4拍子 ソナタ形式
印象的な鈴とフルートによってロ短調で開始されるも、フレーズ末尾でリタルダンドされるクラリネット、続く第一主題(ヴァイオリン)とはずれが生じるよう指定されている。主題は装飾音的な動きも含んだハイドン風なものである。第二主題はチェロがゆったりと歌う。展開部では、4本のフルートのユニゾンによって新しい旋律が現れる。これは、第四楽章の主題の先取りとなっている。その後音楽は展開部において混沌とした様相を示し、第五交響曲の第一楽章冒頭を想起させるトランペットによるファンファーレ動機によって強制的に中断される。第一主題の再現は唐突で、しかも主題の途中から再現される。
第二楽章:落ち着いたテンポで、あせらずに スケルツォ ハ短調 3/8拍子 三部形式
長二度高く調弦した独奏ヴァイオリンが登場する。草稿において「友ハイン(死神)が演奏する」と注を入れたこともあるマーラー自身が「このスケルツォは、諸君が聴くとき、髪の毛が逆立つほど神秘的で昏迷した超自然的なものだ」と述べているように、ホルンが先導する素朴な旋律に道化役の木管が絡み、弦楽器のグリッサンドが多用されるなか、彼岸との異常な対話が展開される。
第三楽章:やすらぎに満ちて、少しゆるやかに ト長調 4/4拍子 変奏曲形式
中低弦で静かに始まり、2つの主題が交互に変奏される。第九交響曲の第四楽章を先取りしたかのような雰囲気が漂う。第二変奏から次第に軽快になり、拍子、テンポ、調性がめまぐるしく移り変わる。楽章の終わり近くで突然盛り上がり、ホ長調で第四楽章の主題が勝利を歌うかのように高らかに強奏される。最後は属和音のニ長調となり、静寂のうちに第四楽章を準備する。
第四楽章:きわめて快適に ト長調 4/4拍子
クラリネットが小鳥のさえずりのような音形をもって穏やかな雰囲気を作ると、いよいよソプラノ独唱が天上の楽しさを歌う。弦楽器はゆらゆらと揺れ動き、イングリッシュ・ホルン、フルート、ハープがこれ以上なく牧歌的に響く。
ソプラノはまず、「私たちはいま天上の喜びを味わっている。だから俗世のことなど気にならない。俗世の騒ぎなど天上にいると少しも聞こえてこない…」と天上の幸福な様子を歌うが、突然、騒がしくなり強いリズムが示される。これは第一楽章の冒頭で鈴によって暗示されていたものである。ソプラノは不安げに第二の部分を歌いだす。「聖ヨハネが小羊を連れてくる。屠殺者ヘロデがそれを待ち受ける。私たちができることといったらその純粋な小羊を死に導くことくらい…」。神の小羊、主イエスに対する罪の告白とも取れる。再び鈴による中断があり、今度は穏やかな第三部となる。「あらゆる種類の野菜や果物が天上には生い茂っている。上等のアスパラガスにインゲン豆、リンゴ、梨、ぶどう酒…。なにもかも望み通り…」。みたび鈴がやってきて第四の部分になる。そののちイングリッシュ・ホルンがバグパイプの音をまねる。「この天上には音楽だってある。地上のどんなものも比べ物にならないような音楽が。…すべての感覚を喜びに目覚めさせる。そしてすべてを幸福にさせる」。曲は安らぎに満ちたまま静かになっていき、イングリッシュ・ホルンとハープの響きを残して永遠の彼方に消え去っていく。


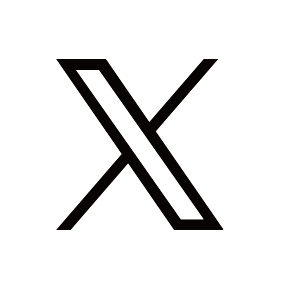
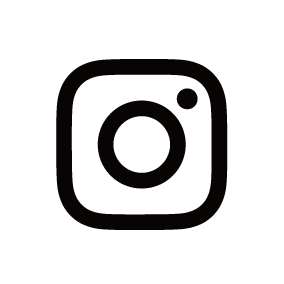

コメントを残す