「今年はモーツァルトの生誕250周年!」皆さんもうお馴染みのフレーズでしょう。世界中の演奏会場でモーツァルトの音楽が鳴り響き、日本でも空前のモーツァルト・ブーム。頭が良くなるだとか健康に良いだとか、何やら怪しげな謳い文句とともに、企画CDや関連書籍が大いに売れています。確かに、モーツァルトの音楽には、広く人びとの心に訴えかけて止まない簡明な美しさとでも言うべき魅力が溢れていますし、BGMとして流しっぱなしにしても煩くない一方で、一対一で厳しく対峙して切り込んでいくような聴取態度にも底を割らない懐の深さが備わっています。
結成以来、古典派・ロマン派の二管編成の管弦楽曲を中心的レパートリーに据えて活動してきたブルーメン・フィルにとって、モーツァルト・イヤーの今年、例えばオール・モーツァルト・プログラムで定期演奏会を開催することも容易に考えられたに違いありません。もし実現していたなら、聴衆、団員の双方にとって、それはそれできっと幸せなひと時となったことでしょう。ところが、これまでも一筋縄ではいかないプログラミングを提案・実現してきたブルーメンの選曲委員の面々は、おいそれと時流に乗ることを潔しとしなかったようです。むしろ、演奏の難しさでは定評のあるモーツァルトですから、聴衆、団員の双方にとって幸せであるどころか、不幸を招きかねないとさえ危惧したのかもしれません。……と冗談はともかく、ここに選ばれたのがサリエリであるというところに、得も言われぬ面白みを感じます。
アントニオ・サリエリ。ほとんど「モーツァルトを毒殺した男」としてのみ名前を伝えられてきた不運な音楽家です。ベートーヴェンの筆談帳にその噂が書き記され、プーシキンには劇詩の題材として利用され、それを元にリムスキー=コルサコフにオペラまで作曲され、挙句の果てには映画『アマデウス』の世界的大ヒット。いくら「根拠のないデタラメなんだけどね」と注釈を付けられても、やはりその週刊誌の見出し的インパクトの強力さには敵いません。ようやく近年になって、古楽の復興と足並みを揃えるかのように、サリエリ研究が進み、その音楽も演奏される機会が増えてきたようですが、完全な名誉挽回にはまだまだ時間を要することでしょう。
1750年、J. S. バッハ死の年に北イタリアのレニャーゴに生まれたサリエリは、16歳の時にウィーンの宮廷作曲家だったガスマンに見出され、弟子としてウィーンに移住します。以降、早くも20歳でオペラ作曲家として彼の地で名前を馳せ、24歳で宮廷作曲家、38歳で宮廷楽長の地位に就き、1825年にウィーンで亡くなる前年まで同職を全うしました。当時の音楽家としては最高に恵まれた生涯を送ったといえるわけです。ただし、流行の変化の凄まじい時代にあって、50歳半ばにはほとんど作曲から手を引き、以後は主に教育者として、幾多の音楽家を世に送り出す手助けをしたのでした。
サリエリに師事した生徒たちの名前の豪華なこと。有名どころだけ挙げても、ジュスマイヤー(一時モーツァルトの弟子でもあり、レクイエムの補筆で知られます)、フンメル、チェルニー、マイヤベーア、モシェレス、さらには何とリストまで! サリエリがいかに音楽的に幅の広い時代を生き抜いてきたかが分かります。そして、今夜お聴きいただく他の2人の作曲家、ベートーヴェンとシューベルトも、サリエリの教え子でした。
1770年にボンに生まれたベートーヴェンがウィーンに定住したのは21歳の時。当初ハイドンの教えを受けていましたが、ウィーンで音楽活動を続けているうちにサリエリとの知遇を得て、1795年には、サリエリの指揮する演奏会において、ベートーヴェン自身のピアノでピアノ協奏曲第1番が初演されています。すでにボン時代に作曲の基本的な素養を身に付けており、後年「ハイドンからは何も学ばなかった」と語っているベートーヴェンですが、こと声楽曲の作曲においては自信を欠いており、この点でサリエリは最適な教師だと見えたようです。1800年頃からおよそ3年間にわたって、イタリア歌曲とイタリア・オペラの様式に関して系統的なレッスンが行われ、その習作は、《サリエリのもとでの多声イタリア歌曲練習曲》WoO99として、25曲が現在にまで伝えられています。その後は、気難しいベートーヴェンのことですから、オペラ《フィデリオ》に対するサリエリのアドバイスを無視したり、自身の演奏会の開催日を、サリエリが指揮する音楽家協会慈善演奏会の開催日にぶつけてみたり(その時に初演された作品の1つが、今夜お聴きいただく交響曲第6番です)、ベートーヴェンが一方的に絶交を宣言するに至った時期もあったようですが、サリエリの大人の対応で事なきを得て、後年も交流が続いたと言われています。ベートーヴェンがウィーンで亡くなったのは1827年、サリエリの死後わずか2年のことでした。
一方シューベルトは、1797年に生まれて1828年に31歳で没するまで、生涯をウィーンで過ごしました。シューベルトとサリエリが初めて出会ったのは1808年、ウィーン帝室宮廷礼拝堂少年合唱団の団員補充試験でのこと。試験官がサリエリで、応募者の中の1人がシューベルトだったのでした。合格したシューベルトは、同時に寄宿神学校に入学することになり、やがて合唱団や学校のオーケストラでその音楽的才能を存分に発揮するようになったのです。その才能に驚いたサリエリは、自ら進んで週2日の個人レッスンを施すことを決め、それは1812年から3年間続いたのでした。ベートーヴェンと同様に、イタリア様式の声楽曲の手ほどきを始め、オーケストラ総譜のピアノでの初見演奏法なども教授したと伝えられています。結果的に見て、シューベルトはオペラの分野では成功せず、歌曲においても、イタリア様式とは対極的なドイツ・リートの開拓者として独自の道を歩んでいくことになったわけですが、師サリエリに対しては生涯変わらぬ尊敬と感謝の念を抱き続けたのでした。
このように、音楽家として頂点を極めながらも、その立場に安閑とせず、自分の得た知識と経験を若い世代に積極的に伝えようと尽力してきたサリエリ。教え子の代表格2人の作品とともにその音楽を聴いて、しばしこの不運な音楽家に思いを馳せる。今夜の演奏会は、まさにモーツァルト・イヤーに相応しい企画だと言えるのではないでしょうか。開演が楽しみになってきました。
シューベルト 「魔法の竪琴(ロザムンデ)」序曲
ウェーバーの歌劇《オイリュアンテ》の台本作家として知られる女流作家ヘルミーネ・フォン・シェジーの新作戯曲『キプロスの女王ロザムンデ』上演のために、1823年12月、シューベルトは劇音楽の作曲を依頼されます。しかし本番までほとんど期間がなかったために、劇中の10曲は何とか作曲できたものの、序曲は間に合わせることができませんでした。そこで初演に際しては、前年に作曲していた歌劇《アルフォンゾとエストレッラ》の序曲をそのまま転用して急場を凌いだのですが、その後、1820年に作曲していた劇音楽《魔法の竪琴》の序曲のタイトルを《ロザムンデ》序曲に変更して、4手用のピアノ作品として出版しました。そういった経緯から、管弦楽版の劇音楽《ロザムンデ》の序曲としても《魔法の竪琴》序曲が演奏される形が一般化し、現在に至っています。
曲は、展開部を欠く序奏つきソナタ形式で書かれています。悲劇的な序奏、軽快な第1主題、優美な第2主題、そして心沸き立つコーダ、いずれの部分においてもシューベルトならではの明快にして繊細な音楽が堪能できます。
サリエリ 「ラ・フォリア」の主題による26の変奏曲
サリエリ晩年の1815年の作品で、作曲に至った経緯、初演の様子などは明らかになっていません。主題が提示されたあとに26の変奏が続き、最後にコーダが付された、全体で20分ほどの作品ですが、これほど大部の管弦楽のための変奏曲は、おそらく空前にして、後を継ぐのはようやく1873年になってから、ブラームスの《ハイドンの主題による変奏曲》の登場を待たねばなりません。
フォリアとは、もともとはポルトガル起源の3拍子系の急速な踊りを指す言葉でしたが、17世紀に入るとむしろ落ち着いたリズムを持つ舞曲へと性格を変えたばかりか、固定された低声部と旋律の枠組みを持つ、1つの定型へと収斂していったのでした。この素材を世に広める嚆矢となったのが1700年に出版されたコレッリのヴァイオリン・ソナタ作品5-12「ラ・フォリア」で、以降、ヴィヴァルディ、バッハ、ケルビーニ、リスト、ラフマニノフなど、数多くの作曲家がそのフォリアを取り込んだ作品を書いています。サリエリの変奏曲もまさにこの流れの中に位置づけられるもので、クラリネットとファゴットの四重奏で提示されるフォリアの主題は、コレッリのソナタの冒頭で聴ける形とまったく同じものになっています。
もともとの主題が帯びている哀調ゆえに、過ぎ去った日々を回顧する老境のサリエリの姿が目に浮かぶかのようですが、1つひとつの変奏曲は、管弦楽を扱う確かな技法の上に創意工夫が溢れ、間然とするところがありません。
ベートーヴェン 交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」
交響曲第5番と並行して作曲が進められ、1808年に完成したこの曲、今夜演奏される3曲の中で最も早い時期の作品であるという点が、やや意外に感じられるかもしれません。前述したように、サリエリと衝突するきっかけともなった初演の日程、1808年12月22日、その日のプログラムは、交響曲第5番と第6番にピアノ協奏曲第4番、そして合唱幻想曲、その他、全体で4時間を超えるという凄まじいもので、会場となった真冬のアン・デア・ウィーン劇場は寒く、演奏者、聴衆ともに集中力を欠き、散々な出来に終わったことが伝えられています。
交響曲第5番がそれこそ絶対音楽の権化であるかのような隙のない構造を持つ厳しい音楽であるのに対し、ベートーヴェン自身が各楽章に標題を与え「田園交響曲」と明記したこの第6番は、情景を思い浮かべながらリラックスして聴ける穏やかな音楽であることは確かでしょう。ただ、第1楽章における徹底的な動機の活用、第1楽章の素材の後続楽章での再利用、複数楽章の切れ目なしでの接続、終楽章における到達点としての音型の類似などなど、作曲技法の点では、第6番は第5番の双生児であると言える特徴を備えています。同様の手法を用いながら、かくも対照的な情感を呼び起こさせる音楽を創り出す、まさにベートーヴェンの天才のなせる業です。
(文責:麻生哲也)


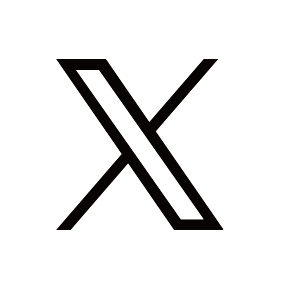
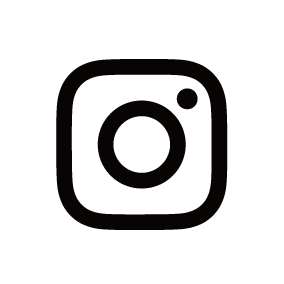

コメントを残す