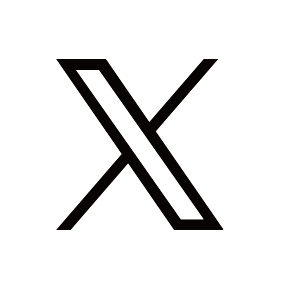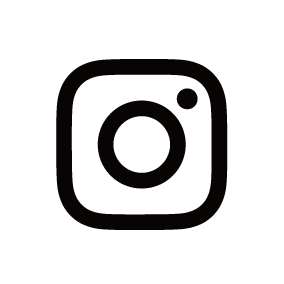バルトーク:ヴィオラ協奏曲
作曲者が死によって完成させることのできなかった作品を、弟子や学者が本人に代わって完成させるということは数多い。文学や絵画においては希なこの「補筆完成」という作業は、時に非常な困難を伴う。
バルトークは1945年、ヴィオラ奏者ウィリアム・プリムローズからの依頼でヴィオラ協奏曲を作曲したが、草稿の段階で白血病による死を迎える。 遺された草稿はバラバラの五線紙15枚に走り書きされたままのもので、もちろんオーケストレーションはされていないし、楽章の構成さえもはっきりと判別できるものではなかった。
この遺稿を判読、補筆完成させたのが、バルトークの弟子で友人の一人、ティボール・シェルイ(1901-1978)である。 彼はやはりバルトークの未完成作品、ピアノ協奏曲第3番を補筆していたが、こちらは最後の十数小節をオーケストレーションするだけの作業だった。 しかし、ヴィオラ協奏曲は上記のような状態で遺されていたので、音符の判読だけにに4ヶ月もかかり、さらに内容を再構成してオーケストレーションを完成させることになった。
完成したスコアを見てみると、テクスチャーの極端に薄い部分が目立つが、バルトークが死の直前にプリムローズに宛てた手紙の「オーケストレーションはかな り透明なものになるでしょう」という一文に拘束されたものである。そしてヴィオラパートは「プリムローズ編」となっているが、プリムローズは演奏効果が上 がるように(難しく)書き換えた部分もあるようだ(このせいで、後のヴィオリスト達は必要以上に苦労することになる)。
そして1995年、シェルイ版とは別に、ピーター・バルトーク(バルトークの息子)とネルソン・デラマッジョーによる新しい「改訂版」が出版された。 つまりこれからは、モーツァルトの「レクイエム」のように複数のヴァージョンが存在するのである。 今日の演奏はシェルイ版によって行われる。
(バルトークのヴィオラ協奏曲が補筆され、出版されたことの背景には、もちろんバルトークが偉大な作曲家であったことによるが、「ヴィオラ協奏曲」というジャンルの絶対的な曲不足も少なからず影響している。)
第1楽章 Moderato ソナタ形式。アタッカ:
第2楽章 Adagio religioso 変則的な3部形式。アタッカ:
第3楽章 Allegro vivace ロンド形式。
主な未完作品の分類
タイプA:未完の状態のまま演奏されるもの
J.S.バッハ フーガの技法
タイプB:途中の楽章(幕)まで演奏されるもの
マーラー 交響曲第10番 Adagio
ブルックナー 交響曲第9番
シェーンベルク 歌劇「モーゼとアロン」(最終幕は台詞のみで上演)
タイプC:他人によって補筆完成されたもの(括弧内は補筆者)
モーツァルト レクイエム(ジュスマイアー、バイアー等数種)
マーラー 交響曲第10番(クック)
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」(アルファーノ)
ベルク 歌劇「ルル」(ツェルハ)
バルトーク ピアノ協奏曲第3番(シェルイ)
バルトーク ヴィオラ協奏曲(シェルイ、P.バルトーク&デラマッジョーの2種)。