モーツァルト ディヴェルティメント第2番 変ロ長調 KV.137(Ambarvalia)
モーツァルトはその短い35年という生涯のうち、約10年2ヶ月を旅に費やしたという。特に幼少期の忙しさは尋常ではない。父レオポルドはモーツァルトの神童ぶりを各地にアピールし、彼の就職先を早くから決めておこうと、ヨーロッパ各地を精力的に飛び回った。旅はモーツァルトが6歳の頃から開始され、1762年ミュンヘン、1762~1763年ウィーン、1763~66年ヨーロッパ広域、1767~69年ウィーン、1769年12月~1771年3月イタリア、1771年8月~1771年12月イタリア、という、超がつくほどのハードスケジュールだった。
本日演奏するディヴェルティメント第2番は、その慌しい旅行の束の間の帰国期間、故郷ザルツブルグで作曲された、愛らしい小品である。それは、折しもモーツァルトがちょうど16歳の誕生日(1772年1月27日)を迎えた頃であった。16歳は、日本でいえば高校1年生。その早熟ぶりには、いつもながら圧倒される。
「ディヴェルティメント」とは、イタリア語の「divertire」(楽しませる)に由来する言葉で「喜遊曲」とも訳される。室内で夕食時に演奏されることが多く、軽快で明るい、くつろいだ雰囲気を持つ曲がふさわしいとされている。
しかし、このディヴェルティメント第2番に、その基準は、あまりあてはまらない気がする。
まず変わっているのは、曲の楽章構成である。普通のディヴェルティメントの楽章構成は「急→緩→急」が一般的だが、この2番に限っては「緩→急→急」という構成。つまり楽章ごとにテンポが上がっていく構成となっている(ストレッド型というそうだ)。
また、曲想的に変わっているのは、その第1楽章である。冒頭は、ひとりひっそりと呟くようなヴァイオリンのモノローグで始まる。それは少しずつ悲しみの翳を帯びていくが、だんだんと他の楽器が寄り添うように重なっていき、それから、心のもやもやを、さっと吹き払うような上昇音型が一斉に奏でられる。その頃には、曲全体に幸せな光が満ちていて、これが16歳の少年の手から生まれたものかと思うと、驚きを禁じえない。
第2楽章は一転して、溌剌としたアレグロ。ヴァイオリンが鮮やかな下降音型で駆け巡り、展開部は伸びやかな旋律が広がる。強弱の対比も鮮やか(なはず)。そして、第3楽章は8分の3拍子の愛らしい舞曲風。思わず踊り出しそうな躍動感のなかにも、堂々とした風格が失われていないのが印象的である。
ハイドン チェロ協奏曲第1番 ハ長調 Hob.Ⅶb-1
ハイドンの全作品をまとめたホーボーケンの作品目録には、真偽不明の1曲も含めると、6曲のチェロ協奏曲が記されている。しかしそれらの中で真作と認められているのは第1番から第3番までの3曲で、しかも第3番は楽譜が失われてしまっている。このため現在、真にハイドンのチェロ協奏曲といえるのは第1番と第2番だけであるが、これらの作品も作品発掘からその真贋をめぐる論争まで紆余曲折がある。第1番はおよそ200年間も貴族の書庫や図書館に眠っていたが、1961年にチェコの音楽学者プルケルトによってハイドン時代の写譜が発見され、使用されていた紙の透かしをはじめとする資料的側面から信憑性の高い筆写楽譜と判定されると共に、冒頭主題をハイドン自身が「草案作品目録」に記載していることから真作であると実証された。第2番も、自筆譜の所在が明らかでなくなっていた19世紀以降、自筆譜が発見されるまでの約1世紀に渡り真贋が真剣に議論された時代があった。
本日演奏されるチェロ協奏曲第1番は作品の様式研究などの結果、1765~1767年頃に作曲されたと推定されている。当時30代になったばかりのハイドンは、エステルハージ侯の楽団の副楽長に就任していた。ハンガリー貴族の中で最も裕福で、代々の当主が音楽愛好家であった侯爵家の宮廷楽団には多くの優れた奏者がおり、彼らのためにハイドンは様々な協奏曲を作曲した。チェロ協奏曲第1番は1761年から1769年まで同団のチェロ奏者を務めたヨーゼフ・ヴァイグルのために作曲したのではないかと考えられている。この協奏曲は、トゥッティとソロを鋭く対比させるリトルネッロ形式や単調な伴奏音形など、多くの点でバロックの協奏曲の名残をとどめているが、第1楽章と第3楽章がテンポの速いソナタ形式で書かれているなどバロックと全古典派を融合しつつあった初期のハイドンの姿勢が示されている。
第1楽章 Moderato ハ長調 4分の4拍子
協奏風ソナタ形式をとっているが、ソロとトゥッティを鋭く対比させるリトルネッロ形式の名残が見られる。トゥッティによる快活な第1主題はやがて第1ヴァイオリンを中心とした旋律的な第2主題へと引き継がれ、再びトゥッティによるコデッタにより管弦楽提示部が結ばれると、独奏チェロが華やかに登場する。再現部は独奏チェロを中心に進められ、カデンツァを経て華やかなコーダで締めくくられる。
第2楽章 Adagio ヘ長調 4分の2拍子
三部形式。独奏チェロと弦楽のみで演奏される叙情的な楽章。弦楽合奏による魅惑的な2つの主題を独奏チェロ中心に展開させていく。中間部で用いられる短調の淡い哀愁を漂わせたメロディーが、ハイドンが旋律の大家である事実を感じさせる。そして主調による主題再現から作曲者自身による短いカデンツァを交え、静かに結ばれる。
第3楽章 Allegro molto ハ長調 4分の4拍子
協奏風ソナタ形式。バロック的要素を残す第1楽章とほぼ同じ構成をとっている。動機的な第1主題からより旋律的な第2主題が管楽器によって提示されたのち独奏チェロが登場する。展開部の長時間に渡り保持されたハイ・ポジションの使用は当時の習慣を超えるもので、ヴァイグルが如何に名手であったかが窺い知れる。再現部で主題がより華やかな形で奏され、華麗さ極まったところでトゥッティによる短いコーダで結ばれる。
メンデルスゾーン 交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」
メンデルスゾーンは1809年、非常に裕福なユダヤ人実業家の家に生まれ、何不自由のない環境のもと、17歳で「真夏の夜の夢」序曲を完成させるなど、早くから際だった音楽の才能を発揮した。1847年に38歳で夭逝してしまった点を除けば、(音楽家としては例外的に)順風満帆な人生を送ったとされている。
しかし、こと交響曲というジャンルについてはそう単純な話でもなかったようだ。「真夏の夜の夢」や「フィンガルの洞窟」を中心とした演奏会用序曲、協奏曲、声楽曲を発表することで名声を確立し、ライプツィヒ・ゲヴァントハウスの音楽監督・指揮者として活躍していた彼にとっては、交響曲のみがその業績から欠けていた。
ベートーヴェンは「第九」を1824年に初演し、その3年後に没した。以後おびただしい数の交響曲が作曲されたが、ついに彼の9曲の交響曲に比肩するものは生み出されなかった(「超えられない壁」というやつだ)。現存するオーケストラ・レパートリーとしてあげられるのは、ベルリオーズの「幻想交響曲」くらいのものであろう(シューベルトの大ハ長調「ザ・グレート」ですら、「しまいこまれたまま行方不明になっていた」)。メンデルスゾーンにとっても、ゲヴァントハウスの定期演奏会で取り上げる新作交響曲がどれもひどいということへの苛立ちがあった。「…手元に6曲の新作交響曲がある。それがいかなるものか、神はご存知だろうが、私の気に入るものはないだろう。しかし、この件について悪いのは誰よりも私なのだ。他のものはともかく、この私が交響曲の分野において成功できないとは。なんてこった!」と知人にもらしている。
このイ短調交響曲は、そのような状況の中、円熟した芸術家・メンデルスゾーンが後世に残せるものと唯一認めた交響曲である。若書きとして扱われがちな第1番や、声楽を伴ったカンタータ風の第2番「讃歌」はさておき、今日第4番とされる「イタリア」の校正作業はついに生前終わらず(あきらめたという説も)、第5番「宗教改革」に至っては「まったく我慢できず」「燃やしてしまいたい」とまで吐き捨てている(これらは生前発表・演奏はされているが、出版されたのは彼の死後しばらく経ってからである)。
メンデルスゾーンがこの曲の着想を得たのは1829年7月30日の夕刻、エディンバラのホリルード宮殿を観光中のことであった(詳細な記録が残っている)。作曲家としての自己を確立しようと強く意識した旅行中のことであり、これを自らの個性と実力を示す交響曲として完成し、早い時期に披露して世に問うことを強く望んでいた彼だったが、完成までには実に13年を要した。
彼が「スコットランドの霧とメランコリーを多分に含んだ、スコットランド交響曲のはじまり」と呼んだこの着想は、リート風の楽節で、16小節からなる。当初彼の頭にはクラリネットとフルートの音があったようだが、最終稿ではオーボエとヴィオラが旋律を担当している。続いて、レチタティーボ風のヴァイオリンがこれに応える。ヴァイオリンと2本のフルートによる印象的な応答を経て、ソナタ形式の主部(第1主題=クラリネット1本とヴァイオリン)が導かれている。第2主題はクラリネットによって奏されるが、全曲を通じたこの楽器の重用が目立つ。
第2楽章はスコットランドの民俗楽器であるバグパイプを想起させる節回しが多用される、軽快なスケルツォである。管楽器のタンギングにご注目あれ。
第3楽章のアダージョでは荒々しい付点動機が連続するが、途中チェロとホルンに現れる旋律の美しさはこの曲の白眉である。
前楽章を断ち切るようにはじまる終楽章は、勢いのある跳躍と「刻み」とが競演している。コーダで明快な長調に転じるが、「人類愛」や「苦悩から勝利へ」といった、わかりやすい(大団円的な)感動を喚起するものではなく、「スコットランド」という通称から受けるイメージから遠くない、清々しさを伴ったエンディングであるといえるだろう。
オーケストラは標準的な二管編成であるが、彼にしては珍しく、ホルンを4本用いていることが注目される。調性の異なるホルンを二対用いることで和声的厚みは倍増し、ホルンをソロ楽器として扱った際の管弦楽の響きも損なわれない。実際、第3楽章には3番ホルンに大ソロが控えている。
メンデルスゾーンは、1842/43年にこのイ短調交響曲を発表する際に、着想の起源を厳格に伏せ、存命中はそれを貫き通した。「スコットランド」という通称は、彼の知人や友人たちが作品を語りだすことによって公の場に持ち込まれたものであった。
彼は、音楽を言葉で表現すること自体が不可能だと悟っていた。言い換えれば音楽によってこそ彼の意図が明確に再現されるということになるだろう。
「…真の音楽は、言葉よりも千倍も良いもので私たちの魂を満たしてくれます。…もし私がその時に何を考えていたのかと問われるならば、そこにあるがままの歌そのものだと答えましょう。…音楽であれば、私たちは両者とも真に理解できるでしょう。…」
※参考文献: 星野宏美著『メンデルスゾーンのスコットランド交響曲』(音楽之友社、2003)


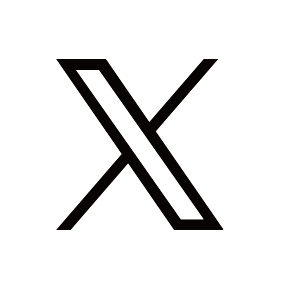
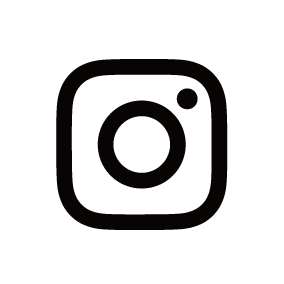

コメントを残す